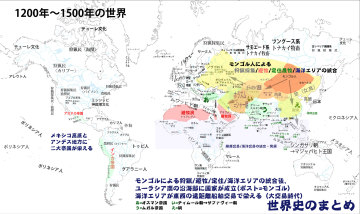 |
ユーラシアでは、モンゴル高原の遊牧騎馬民族が拡大し,連合政権を樹立,ユーラシア東西を結ぶ陸上・海上ネットワークが再編される。
南北アメリカ大陸では、中央アメリカと南アメリカのアンデス地方で交流の広域化がすすむ。
時代のまとめ
ユーラシアでは、モンゴル人が馬の力でユーラシア大陸をまとめ,交流の活発化でヒト・モノ・情報の移動が活発化し,技術革新につながる。
(1) ユーラシア
①モンゴルの時代
モンゴル人は商業を保護し,ユーラシア東西を結ぶ陸海のネットワークを統合する
ユーラシア大陸の東西をモンゴル人が席巻し,ロシア(キプチャク=ハン国【慶文H30】),西アジア(イル=ハン国) 【京都H19[2]】【セH5,セH11】,中央アジア(チャガタイ=ハン国【慶文H30】),中国(元)にモンゴル人の政権が建てられ,モンゴル人の指導者「大ハーン」の権威の下でゆるやかな統合が維持された。
モンゴル人は,ユーラシア大陸各地に建設されていた農牧複合国家の農牧業・商業を保護し,アフリカ大陸からユーラシア大陸東西を結びつける海陸の交易ネットワークが整備されていく。
東南アジア方面の大理【東京H6[1]指定語句】は1254年に滅ぼされ,海上交易の掌握をねらう元が遠征し,ビルマのパガン朝やジャワ島のクディリ朝が混乱,ヴェトナム北部の陳朝は撃退した。
南アジアでは,インド北部のイスラーム政権である奴隷王朝【セH3】【追H30ムガル帝国とのひっかけ】は,モンゴル帝国の侵入を免れた。デカン高原以南にはヒンドゥー教の諸政権が並立し,ペルシア,アラビア半島やアフリカ東部沿岸のスワヒリ地方の都市国家群との交易の利で栄える。
西アジアのアッバース朝は1258年【慶文H29】にモンゴル人に滅ぼされたが,エジプトのイスラーム政権である新興のマムルーク朝がカリフを保護する。
② モンゴル後の時代
14世紀中頃に,ペスト(黒死病【東京H27[1]指定語句】)がユーラシア大陸から北アフリカで猛威をふるい,異常気象や災害も重なり,各地で政権が変化する
ユーラシア大陸の交易ネットワークが緊密化すると,致死率の高いペスト菌の西方への大移動が起きた。アフリカのマムルーク朝が衰退する原因となり,ヨーロッパでは各地の君主国で壊滅的な被害が生まれる。
また,14世紀中頃には東アジアで明王朝がおこる。モンゴル人はモンゴル高原に撤退するが,〈チンギス=ハーン〉の直系一族は,モンゴル高原を拠点に内陸ユーラシアにおいて依然として強い勢力を保った(チンギス統原理)。
西アジアではモンゴル人の後継国家からティムール朝が生まれ,西方に拡大してテュルク系のオスマン朝と対抗する。
西ヨーロッパではイングランド王国とフランス王国を中心とする百年戦争中にペストが大流行し,大規模な農民一揆【東京H8[3]「封建反動」について説明する】は封建社会を揺るがす。
中央ヨーロッパや東ヨーロッパではリトアニア=ポーランドやモスクワ大公国が強大化。後者はモンゴル人からの支配を脱し,領土を拡大させている。
③ 大交易時代
15世紀中頃からユーラシア大陸で「大交易時代」がはじまる
14世紀中頃のペストの大流行にともなう停滞期を経て各地で体制の再編がすすみ,海上ネットワークを中心とする大交易時代が始まる。
ユーラシア大陸各地の政権は海上支配を目指し,中央集権化をすすめていった。明は南海大遠征を実施し,東南アジアのマジャパヒト王国やマラッカ王国,南アジアの諸政権など,インド洋一帯の交易活動が刺激される。
・ヨーロッパでは十字軍の影響で東方交易(レヴァント交易)が活発化し,各地の政権が覇権を争った。活性化する「大交易時代」の物流ネットワークのおこぼれにあずかることのできた。イタリア諸都市がキリスト教に代わる新たな価値観として古代ギリシア・ローマの情報を保護し,文芸復興(ルネサンス)がはじまる。特に西地中海ではピサとジェノヴァ,東地中海ではヴェネツィア(英語ではヴェニス) 【東京H14[3]ヴェネツィアの特産品を,刀剣類,毛織絨毯(じゅうたん),加工ダイヤモンド,ガラス工芸品(正解),手描き更紗(さらさ)から選ぶ(世界史の問題か?)】が交易を独占した。
また,西ヨーロッパを中心に商工業が発達すると,都市を中心とする社会が成熟して封建社会が変質。各地で中央集権化を進めた王権による国家統一が進む。
・オスマン帝国のヨーロッパへの進出が,イベリア半島諸国の海外進出につながる
一方,テュルク系のオスマン帝国がバルカン半島・東地中海に進出すると,イタリア諸都市は衰退に向かう。オスマン帝国は,モンゴル系のティムール朝との間で,インド洋交易ネットワーク(紅海から,アラビア半島沿岸のイエメン,ハドラマウト,オマーンを経由しペルシア湾岸に向かうルート)の覇権をめぐり抗争する。
没落したイタリア諸都市に代わり,イベリア半島諸国(ポルトガル王国,カスティーリャ=アラゴン(のちのスペイン))がインド洋への直接航路・西アフリカの金の直接取引を目指し,新航路の開拓に乗り出すことになる。15世紀末にはスペインの〈コロン〉がカリブ海(現・バハマ)に到達し,ヨーロッパ人にとっての「世界」に南北アメリカ大陸が加わることとなる。
(2) アフリカ
アフリカではサハラ沙漠の横断・縦断ルートが活性化し,ニジェール川上流域のマリ帝国とソンガイ帝国,ニジェール川中流域のハウサ諸国,下流のベニン王国,チャド湖周辺のカネム王国,スーダンやエチオピアの諸王国が繁栄。
インド洋沿岸のスワヒリ都市国家群は,現・モザンビーク沿岸部にも拡大し,内陸交易でマプングブエ,のちにグレート=ジンバブエが栄える。
(3) 南北アメリカ
中央アメリカのメキシコ高原と南アメリカのアンデス地方に広域政権が出現する
南北アメリカ大陸でも南北を結ぶ交易路が存在したものの,ユーラシア大陸と異なり南北の気候・植生の違い(熱帯雨林が大きな障がいとなる),陸上交易の要となる馬や牛のような家畜の不在(山岳部のリャマを除く)が重なり,交易ネットワークは未熟だった。
南アメリカからアラワク人がカヌー(カヌーはアラワク語が語源)で大アンティル諸島(現在のキューバ周辺)に渡っていたように,航海技術が発達していなかったわけではないが,ユーラシア大陸の「海の道」に比べ,遠洋航海技術は未発達であった。
北アメリカ大陸南西部の古代プエブロ人の文化は,過剰な開発や干ばつの影響により衰退へ向かう。ミシシッピ川流域では政治的な統合がすすみ,神殿塚文化が栄える。
カリブ海では,先住のアラワク人の地域に,南アメリカ北部からカリブ人が進出。小アンティル諸島を中心に活動範囲を広げる。
メキシコ高原では都市国家群が栄え,15世紀にアステカ帝国が強大化する。
アンデス地方ではペルー北部沿岸のチムー帝国が広域統一に向かい,ワリ帝国とティワナク帝国崩壊後の権力の空白を埋める。ペルー南部ではティワナク帝国崩壊後には,アイマラ人の諸王国が成立していたが,やがて高山地域のクスコを中心にインカ帝国が南大陸沿岸部から山岳部にかけてを広域統一する。
アンデス山地北部からパナマ地峡,カリブ海の小アンティル諸島,南アメリカ北部のギアナ地方,アマゾン川流域の下流部と中流部では,政治的な統合も進んでいるが,広域を支配する強大な国家には成長しなかった。
(4) オセアニア
ミクロネシア、メラネシア、ポリネシアの火山島・サンゴ礁島で、人々は農耕・牧畜・漁撈・採集を主体とした生活を送っている。
この時期にニュージーランドに到達したポリネシア人(マオリ)は、狩猟を生業に導入する。
オーストラリアの住民(アボリジナル)は外界との接触をほとんど持たず、狩猟・採集生活を送っている。
解説
◆前半にモンゴル人の大移動によって陸海のネットワークの相互関係が深まるが,開発の進展に対し人口増が限界をむかえ,小氷期も重なり各地で飢饉・戦争が起き生産性が低下する
800年~1200年にかけて世界各地で開発や技術革新が盛んにおこなわれ,人口も増加傾向にありました(⇒800~1200の世界)。しかし,このような生産性の向上→人口の増加→経済成長という進展は,長くは続きませんでした。一般に,人口がどんどん増えていくと,増加分の人口を養うことのできる技術革新が起きない限りは,どこかで食料や資源の供給が追いつかなくなるとされます(「マルサス的停滞」)。のちに「1760年~1815年の世界」でみるように,人類がこの「限界」を突破するには,石炭のエネルギーを活用する技術革新(産業革命(工業化))の到来を待たねばなりません。
それでも1200年代には,前時代の経済活動の活発化を受け,モンゴル高原の遊牧騎馬民(モンゴル人)が,ユーラシア一帯に短期間で勢力圏を広げ,草原地帯に拠点を維持しながら,定住農牧民の国家を各地で征服していきました。モンゴル人は陸上だけでなく海上交易も推進し,アフリカ大陸を含むユーラシア大陸の大部分に形成されていた交通・商業のネットワークが連結されていったのです(注1)。
しかし,1250年~19世紀半ばの地球各地の平均気温は,それ以前の中世温暖期よりも寒冷化に向かっていました。この時期を「小氷期」と呼ぶことがあります。モンゴル帝国から分かれた主要な政権は,14世紀半ばの寒冷化の進行・飢饉・疫病の流行(いわゆる“14世紀の危機”)により打撃を受け崩壊します。特に14世紀なかばにユーラシア大陸全体を襲ったペスト(黒死病【東京H27[1]指定語句】)は,各地の社会に壊滅的な被害を与えました。
●ヨーロッパでは,都市社会が成熟し,都市内部に大商人・役人・高位聖職者・手工業者(親方)などの支配層が形成されていきました。その下には小規模な商人や手工業者(職人や徒弟)がいて,さらに貧民層も形成されていきます。富裕となった手工業者や商人は市民(ブルジョワジー)という階層として台頭し,市民同士の紛争も起こるようになります。都市の中は街区に分けられ,それぞれの街区が信仰や行政,助け合い(相互扶助)の基本単位となりました。都市内部には行政をつかさどる市庁舎,司法の裁判所,立法の市参事会がもうけられ,商館や広場,教区の教会,修道院,施療院が形成され,国王や周辺の領主の介入をしりぞけて自治を獲得する都市(自治都市)も増えていきます。またゴシック様式の大聖堂(カテドラル)は,都市の富の象徴でもありました。
このような社会の変化に対応してヨーロッパ各地では,諸侯,都市の市民,聖職者により構成された身分制議会が,国王の政治を監視する形の君主国(モナルキア)が生まれていきました。例えばイングランド王国では1265年に諸侯がリーダーシップを発揮して,都市の代表を含む身分制議会を立ち上げる国政改革が実現しています。また,1295年には聖職者と世俗の代表をメンバーとする身分制議会が開かれて,君主国としてのまとまりが形作られていきました。
イベリア半島では,1137年に成立したアラゴン連合王国と,1143年成立のポルトガル王国がレコンキスタ(国土回復運動)をすすめており,その勢いでポルトガルは大西洋へ,アラゴン連合王国は西地中海への進出もすすめます。
ドイツの神聖ローマ帝国の〈フリードリヒ2世〉【セH8同名のプロイセン王との混同に注意】はシチリア王国の王も兼任し,ギリシア語・アラビア語・ラテン語にも通じ,“世界の脅威”と絶賛されています。彼は行政機構を確率しましたが,アルプス以北の支配がゆるみ,教皇からも波紋を受けました。
〈フリードリヒ2世〉の死後,神聖ローマ皇帝の命運は傾きます。シチリアは独立し,1256年以降の神聖ローマ帝国は大空位時代に突入。強力な君主国を形成することはできませんでした。
各地で君主国が領域内の支配を強めていったのに対し,ローマ教皇〈インノケンティウス3世〉は教会の権威を高め,信仰生活の共通規範を定めるなどして対抗します。1209年にはフランチェスコ修道会,1215年にドミニコ修道会を認め,多くの修道士が都市で辻説法をおこなったり,モンゴルに派遣されたりしました(修道士の時代)。各地に設立されていた大学でもドミニコ会士が教鞭をとり,スコラ学【共通一次 平1】の権威は高まっていきました。
13世紀には,新しい教皇が選出されるまで枢機卿が外部にに出られないというコンクラーヴェという制度が初められます。
14世紀初めには,フランス人司教が教皇となり,フランスの王権を後ろ盾にして,教皇を中心とする集権化,軍事改革,徴税制度の整備をおこないました。この改革は南フランスのアヴィニョンで行われ,教皇庁もアヴィニョンに移動されました。アヴィニョン教皇庁の期間は“教皇のバビロン捕囚”といわれますが,実際には教皇庁の意向によるものでした。
なお,ロシアはモンゴル人の支配を受けていましたが,そのうちノヴゴロド公の〈アレクサンドル=ネフスキー〉(1220?~1263)は貢納によって服属を回避し,スウェーデン,リトアニア,ドイツ騎士団と戦って独立を守っています。彼はモンゴル人とも提携しつつ敵対勢力を抑え,権力を強化しました。
◆ペストの大流行後,世界各地で再び成長期が始まり,ユーラシア大陸東西を結ぶ海域に“大交易時代”が展開する
“14世紀の危機”を経て,世界各地で交易ネットワークが再び活性化します。
モンゴル帝国の海上進出の刺激を受け,バルト海・北海~地中海・紅海・ペルシア湾~インド洋~東シナ海・南シナ海など東南アジアの海域に連なるユーラシア大陸南縁は,1400年頃から1570年〜1630年代をピークとする空前の海上交易ブームである“大交易時代”を迎えます。
ただ,この時期には内陸を押さえつつ,同時に沿海部の交易活動を支配できるほどの強力な国家はありません。内陸の国家が交易を制限しようとするの対し,例えば東アジア近海では倭寇をはじめとする海賊集団の活動も活発化します。各地の貿易の要衝では港市国家が栄え,農業生産力を高めつつ銃砲・火砲を導入して軍事的に強大化する国家も現れていきます。
●中央アメリカではアステカ帝国が,南アメリカのアンデス山脈地域ではインカ帝国(タワンティン=スーユ)が周辺に拡大し,交易ネットワークを支配しています。
●中国では明(1368~1644)の〈鄭和〉(ていわ)が“西洋下り”(1405~1433)と呼ばれる南海大遠征を実行し,東シナ海・南シナ海・ベンガル湾・アラビア海・アフリカ東岸に至るまでの交易ネットワークを活性化させています【セA H30大西洋には行っていない】。
●南アジアでは,1336年に南インドでヴィジャヤナガル王国が建てられ,特産の米と綿布を西方に輸出し軍馬を買い付け,1347年に南インドで成立したバフマニー王国と覇権を争っています。
●西アジアではアナトリア半島からおこったテュルク系のオスマン帝国が,黒死病の流行の去った後のバルカン半島に進出し,1453年にはビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを陥落させています。次の時代(⇒1500~1650の西アジア)には地中海周辺に拡大し,イタリア諸都市と地中海交易をめぐり対決し(⇒1500~1650のヨーロッパ),インド洋交易ネットワークにも参入するようになっていきます(紅海を通してインド洋交易の拠点となっていたエジプトのマムルーク朝のカイロは,14世紀中頃の黒死病で壊滅的な被害を受けていました)。
●西アフリカでは,マリ帝国【セH8】がニジェール川流域を拠点に拡大し,中央アフリカの熱帯雨林地域や北アフリカの沙漠地帯との交易ネットワークを支配しています。1352~1354年には旅行家〈イブン=バットゥータ〉もマリ帝国に滞在しています。
●ヨーロッパでは14世紀中頃の黒死病の流行により,農民の耕作地放棄→廃村の増加→都市への貧民の流入→都市内の対立の激化という展開が生じ,農村では土地領主制が崩れ,自治都市の中でも社会不安が高まります。都市内では下層民による抵抗運動(1378年)や,ユダヤ人に対する迫害(後述)が起きています。
流行が収束すると人口は回復していきますが,経営を立て直そうとした領主に対する農民反乱も起こります。領主は反乱の鎮圧とともに,地代の金納や耕作地を拡大をすすめ,中央ヨーロッパ・東ヨーロッパ(特にポーランドとプロイセン)では輸出向け作物を栽培させるために農奴制が導入されました。
各地わずかな資源をめぐり争いが頻発し(注2),中小の国家が王朝の結びつきや宗派に基づき同盟・対抗関係を結びながら,財政を充実させるために商業活動にも積極的に関与していきます。例えば,イングランド王国とフランス王国は毛織物【セH2綿工業ではない,セH9綿織物ではない】工業の先進地域であるフランドル地方【セH2】をめぐり争い,百年戦争に発展しました(イングランドの〈エドワード3世〉は1340年にフランス王に即位することを宣言)。
一方,神聖ローマ帝国の〈カール4世〉は宮廷をベーメンのプラハ(現在のチェコ)に移し,ボヘミア王とハンガリー王も兼任します。12世紀以降,ドイツ人の東方植民がすすみ,ドイツ人居住地域が東に移動していった結果です。一方,帝国内部の諸侯たちは与えられた封土や官職を私物化し,戦争・相続・購入により領土を増やして地域的な“君主国”(領邦国家)を形成していきました。彼らは国王から司法権や貨幣をつくる権利を奪い,王位や領地を世襲していったので,神聖ローマ帝国の“分裂”がすすんでいきました。なお,この地域のユダヤ人は黒死病の流行時に激しい迫害を受け(混乱の中「井戸に毒を入れた」などの疑いをかけられたのです),居住区や服装が指定されたり,東ヨーロッパへの移住がすすんだりしていきました(東ヨーロッパに移住したユダヤ人をアシュケナジムといいます)。特にポーランド王国は多くのユダヤ人を受け入れ,国力を高めました。〈カジェミシュ3世〉はクラフク大学の創建を教皇により許可され(1364),成文法典も編纂させました。
また,13世紀に新たなアルプス超えルートであるザンクト=ゴットハルト峠が開通して,ヨーロッパの南北交易ルートの重要地点となったスイスでは,ウーリ州【追H20】の諸侯が神聖ローマ帝国の介入に対抗し,他2州とともに1291年にスイス誓約同盟(スイス)【追H20スイスが,神聖ローマ帝国から独立したか問う。時期(ウィーン体制下ではない)】を建設しました。これが現在のスイスの原点です。誓約同盟はハプスブルク家,ブルゴーニュ家と対抗する中で優れた軍事力を発揮し,フランスやローマ教皇庁の傭兵としても活躍しました。
この時期には,従来は「辺境」とみなされていた地域の開発も進み,タラのような魚が増加する人口向けの重要なタンパク源として注目されました。
北ヨーロッパはバルト海を中心とする商業圏を充実させ,デンマーク王国の〈マルグレーテ〉女王を中心に1397年にノルウェー王国,スウェーデン王国はカルマル同盟【立教文H28記】を結成して,バルト海東部方面から進出するドイツ人商人に対抗しています。北ヨーロッパの商業圏は,内陸の商業圏と結びついて,地中海の商業圏とつながっていました。
地中海沿岸のイタリアの海洋国家ジェノヴァ共和国やヴェネツィア共和国は交易と金融業で栄えますが,オスマン帝国の進出を受け,西アフリカの金の直接交易や,インド洋への直接進出を図るようになります。イスラーム商人の影響を受けて会計の記録技術も発達しました。〈パチョーリ〉による1494年の『スムマ』は現存する最古の複式簿記に関する記述です。
ローマ=カトリックの教皇庁は1378~1417年の間,“大シスマ”といわれる分裂を経験しましたが,公会議によって解決されました。しかし,都市経済の発達を背景として,従来の教義に対する批判的な思想も芽生えていきました。イングランドの〈ウィクリフ〉の「聖書を大切にしよう」という主張の影響を受けたベーメンの〈フス〉によるローマ教皇庁批判は,ベーメンのスラヴ系住民の独立運動を押さえようとするドイツ諸侯軍による軍事介入(フス戦争)に発展しましたが,ベーメン側が新兵器であるマスケット銃と走行荷車(移動可能)を使用したため,1436年にはフス派の穏健グループと教皇との和解に終わっています。農民ですら扱えるマスケット銃の登場は,従来型の騎兵を投入した戦法を無効にするほどの威力であり,その後の騎士の没落【セH2】や戦術の変革に向かうことになります(軍事革命)。16世紀からは稜堡式城郭のように突き出た稜堡(りょうほ)を持つ城壁がさかんに建設されるようになりました【東京H14[3]その背景を答える「火器」】。
イスラーム政権と長年にわたり対決していたイベリア半島の諸王国のうち,ポルトガル王国はすでに1340年代には北大西洋のアフリカ西岸近くのカナリア諸島に進出していました。大西洋における漁業の発展や西アフリカの金の直接取引への欲求が背景となり,15世紀半ばに東方の造船技術を参考にしてカラベル船【セH6図版(三段櫂船とのひっかけ)】を開発し,1482年に西アフリカに拠点を設けます。さらにのちにスペイン王国に発展するカスティリャ王国は15世紀にカナリア諸島に進出。カナリア諸島から北方に向かい,偏西風に乗ってヨーロッパに向かって帰るルートの途中にあったマデイラ諸島では,1450年代からアフリカから輸送した奴隷を用いたサトウキビ【セH11アメリカ大陸原産ではない】のプランテーションを開始します。プランテーションとは,大土地で大量に一種類の売れる作物(商品作物)を栽培し,工場のように収穫・加工して輸出する方式の栽培法のことで,のちカナリア諸島でも実施され,南北アメリカ大陸にも拡大していくことになります。
なお,ロシアでは1480年に〈イヴァン3世〉がキプチャク=ハン国からの自立を達成し,いわゆる“タタールのくびき”(モンゴル人による支配)から脱しています。
◆南北アメリカ大陸の文明は,ユーラシア大陸とは異なる歩みをたどっている
この時期の南北アメリカ大陸は、15世紀末に至るまで、アフリカ大陸・ユーラシア大陸との交流はありません。
(注1)「アフリカ大陸を含むユーラシア大陸」とあるように,このネットワークにはオセアニアの大部分や南北アメリカ大陸は含まれていないことに注意しましょう。
(注2)ヨーロッパは現・中華人民共和国の面積と比べると,視覚的にこのくらいのサイズしかありません(参照:Website
”The True Size
of...” https://thetruesize.com/#?borders=1~!MTcxNzcxOTE.NDEzMDEwMw*MzYwMDAwMDA(MA~!CN*NzE0NzYzNA.MTM3MzI5OTQ)Mw)。
○1200年~1500年のアメリカ 北アメリカ
イギリスの〈ヘンリ7世〉(位1485〜1509)の命で,〈ジョン=カボット〉(〈ジョヴァンニ=カボート〉,1450?~1499?)が,〈息子〉とともに1497年にニューファンドランドに到達し,そこにヴェネツィアとイギリスの国旗を立てました。
沖合に漁場が広がっていることも発見。ここにはヨーロッパ各国から漁船が訪れ,ヨーロッパ市場向けにタラ漁がブームとなります。
タラは船の中で塩漬けにされるか,沿岸で天日干しにして,ヨーロッパ市場に運ばれました。
なお〈カボット〉はセントローレンス湾にも到達しています。
北アメリカ東部ではマウンド(埋葬塚)を建設する文化(マウンド文化)が栄えます。中心の一つであるカホキアには,首長層が巨大なマウンドを建設していました(◆世界文化遺産「カホキア墳丘群州立史跡」、1982)。13世紀初めの地震の影響もあり、1350年には滅んでいます。
○1200年~1500年の中央アメリカ
中央アメリカ…現在の①メキシコ,②グアテマラ,③ベリーズ,④エルサルバドル,⑤ホンジュラス,⑥ニカラグア,⑦コスタリカ,⑧パナマ
◆マヤ文明の中心はマヤ低地北部に移っている
中央アメリカのマヤ地方北部の低地部(マヤ低地)では,12世紀頃から15世紀中頃までマヤパンがチチエン=イツァーに代わって主導権を握りました。マヤパン衰退後のマヤ地域には,有力な勢力は現れず,多数の都市が交易ネットワークを形成して栄えました。
◆メキシコ高原南部のオアハカ盆地にはミシュテカ人の都市文明が栄える
メキシコ高原南部のオアハカ盆地にはミシュテカ人の都市文明が栄えています。
◆メキシコ高原中央部では
北アメリカのメキシコ高原中央部は,テスココ湖の北西のトゥーラなどの諸都市が栄えます。
トゥーラは1150~1200年に衰退。
テスココ湖周辺には、シャルトカン、テスココ、テナユカ、アスカポツァルコ、クルワカン、シコなどの新興国家のほか、ウエショツィンコ、トラスカラ、センポアラなどの以前からの国家などが並び立つ状況でした。
トゥーラの繁栄の後、14世紀後半にメキシコ高原中央部に進出したのは狩猟による遊動生活を送っていたナワトル語系チチメカ人の一派です。彼らは、その現住地とされる「アストラン」から、のちにアステカ人【セH30】と呼ばれるようになりますが、自称はメシーカ(メキシコの語源)です(注1)。
アステカ〔メシーカ〕人は、先住のティオティワカンの都市をみて、これを崇めたてまつって「「神々の都市」(テオティワカン)と命名。そして、テスココ湖の無人島に定住しテノチティトラン【セH11インカ帝国の中心地ではない】【セH21、セH25、セH30】(「サボテンの実る地」という意味)を建設。現在のメキシコシティ【セH25】は、このテノチティトランに築かれた都市です。
アステカ〔メシーカ〕人は近隣の都市国家のうち1428年にテスココとトラコパンという都市と同盟し(三都市同盟)、周辺諸民族を征服し、貢納を徴収しました。征服活動は〈イツコアトル〉(位1427~40)、〈モクテスマ1世〉(1440~1468)、〈アシャヤカトル〉(位1469~1481)、〈アウィツォトル〉(位1486~1502)、〈モクテスマ2世〉(1502~1520)と、間断なく続きます。
〈アウィツォトル〉王の治世には、マヤ高地に近い太平洋岸のソコヌスコ王国(現在のメキシコのチアパス州)をも征服しますが、西方のタラスコ王国や、テスココ湖東方のライバル トラスカラ王国(注2)を滅ぼすことはできませんでした。
つまり、アステカ王国は「メキシコ全土を支配していた」わけではなく、あくまでテスココ湖周辺を中心に、周辺の勢力を従属させていたに過ぎないのです。
(注1)篠原説では「アステカ」は18世紀末までほとんど使用されず「アストラン人」に限定された呼称でした。王国の自称は「メシーカ」ですが、メキシコ全土を指すわけではなく、ティノチティトラン(メシコとも呼ばれます)、テスココ、トラコパンの三都市同盟の支配領域を指しました。篠原愛人監修『ラテンアメリカの歴史―史料から読み解く植民地時代』世界思想社、2005、p.44。
(注2)のちにスペイン人〈コルテス〉の軍は、トラスカラ王国と同盟してアステカ王国を滅ぼすことになります。
メシーカ〔アステカ〕人の経済的基盤は農耕です。
2100mの高山の気候に対応するため,湖に浮き島(チナンパ)をつくることで農地を増やし,その上でトウモロコシ(アメリカ大陸原産【セH11】),トマト,カボチャ,豆などが栽培されます。家畜はイヌと七面鳥です。征服だけではなく,専門の商人によりヒスイやジャガーの皮,穀物やカカオなどの交易も,メキシコ高原周辺の社会との間でさかんにおこなわれています。少ない資源をめぐって恒常的に戦争が起き,戦士が重用される好戦的な社会でした。
社会は階級によって複雑に分かれ,頂点に君臨していたのは国王です。軍事政権を正統化するために神殿で民族神のウィツィロポチトリに多くの生贄をささげることで,世界が終わらないように維持することができるとされました。神殿では人身御供が広く行われていました。
アステカ王国の支配域の人口は最大1100万人を数えます。
彼らはアステカ文字を残しましたが,情報の多くがのちに進入するスペイン人により破壊されたため,現代に残る情報の多くがスペイン人修道士らの記録を通じたものです。
○1200年~1500年のカリブ海
カリブ海…現在の①キューバ,②ジャマイカ,③バハマ,④ハイチ,⑤ドミニカ共和国,⑤アメリカ領プエルトリコ,⑥アメリカ・イギリス領ヴァージン諸島,イギリス領アンギラ島,⑦セントクリストファー=ネイビス,⑧アンティグア=バーブーダ,⑨イギリス領モンサラット島,フランス領グアドループ島,⑩ドミニカ国,⑪フランス領マルティニーク島,⑫セントルシア,⑬セントビンセント及びグレナディーン諸島,⑭バルバドス,⑮グレナダ,⑯トリニダード=トバゴ,⑰オランダ領ボネール島・キュラソー島・アルバ島
カリブ海の島々には漁労採集民のほか,ヤムイモ,マメ,トウモロコシ,カボチャ,タバコを栽培する農牧民アラワク人が分布していました。
南アメリカ東部にかけて,カリブ海の東端に点々と連なる小アンティル諸島では,カリブ人という民族が分布していました。男性は狩猟・漁労,女性は農耕に従事し,カヌーで大アンティル諸島のアラワク人を攻撃していました。
◆〈コロン〉(コロンブス)がカリブ海の「西“インド”諸島」に到達した
1492年【セ試行 ポルトガル船がインドに到達する前か問う】にジェノヴァ【上智法(法律)他H30】の船乗り出身の〈コロン〉(コロンブス) 【上智法(法律)他H30】が,スペイン王〈イサベル〉【上智法(法律)他H30ジョアン2世ではない】の支援を受けカリブ海に到達しました。
現在のバハマにある島をサン=サルバドル島と命名し,キューバ島,イスパニョーラ島(現在のハイチ(ハイティ)とドミニカ共和国)を探検しました(第一回航海,1492~93)。
イスパニョーラ島のサント=ドミンゴ(現⑤ドミニカ共和国の首都)には植民拠点が建設され、スペイン風の低層(ハリケーン対策のため)の石造建築物が建てられました(◆世界文化遺産「植民都市サント=ドミンゴ」、1990)。
第二回航海(1493~1496)では,イスパニョーラ島の先住民(アラワク系のタイノ人)を虐殺する事件を起こしています。
第三回航海(1498~1500)では南アメリカ大陸のオリノコ川河口(現在のベネスエラ)に到達し,イスパニョーラ島に北上しました。〈コロン〉は先住民を奴隷としてスペインに連行しています。また,カリブ海の島々に入植した白人の行為は,大変残虐なものであったと記録されています。
入植者と〈コロン〉との間には対立も生まれ,先住民の抵抗もあって植民地経営は成功しませんでした。〈コロン〉は死ぬまで,自分の到達したのは“アジア”だと主張していました【セ試行 西インド諸島ではポルトガルによる経営はおこなわれていない】。
○1200年~1500年の南アメリカ
地方王国期からインカ帝国の拡大へ
南アメリカ…現在の①ブラジル,②パラグアイ,③ウルグアイ,④アルゼンチン,⑤チリ,⑥ボリビア,⑦ペルー,⑧エクアドル,⑨コロンビア,⑩ベネスエラ,⑪ガイアナ,スリナム,フランス領ギアナ
◆チムー王国などのアンデス地方の伝統を継承し、インカ帝国が広域支配を実現する
アンデス地方が広範囲にわたって統合される
アンデス地方の北部ではシカン文化が栄えていましたが,1375年頃のチムー王国に征服されました。王宮や王墓はチャン=チャンに置かれ、先行するワリ文化を継承し行政・流通などに関わる空間が都市に作られました。
王が代わるたびに王宮が更新されたし、食糧を集めて再分配するための倉庫が整備され、優れた金属工芸がつくられたことは、のちのインカ帝国にも継承される要素となっています(注)。
(注)関雄二「アンデス文明概説」、増田義郎、島田泉、ワルテル・アルバ監修『古代アンデス シパン王墓の奇跡 黄金王国モチェ発掘展』TBS、2000、p.176。
しかし一方,アンデス地方の中央部では,クスコ周辺に分布していたインカ人が1438年頃から〈パチャクテク〉王(位1438~1463)により,北は赤道付近,南は地理の中部までの広大な領域に活動範囲を広げ,クスコ【セH11テノチティトランではない】【セH24ポトシではない,H29ポトシではない】に首都を整備しました(◆世界文化遺産「クスコの市街」、1983)。
1470年代からチムー王国を攻撃して,支配下に加えました。インカ人はこの領域を4つにわけ,タワンティン=スーユ(4つの地方)と呼びました。これがいわゆるインカ帝国です。のちにスペイン人は,皇帝が“太陽の子” 【セH11:太陽神ラーは崇拝されていない。王が「太陽の子として崇拝され」ていたか問う】として強力な権力でアンデス地方を支配していたと報告したため,「ローマ帝国」のような確固たる領域を持つ国のようなイメージがつくられていきました。しかし実際には,そびえ立つアンデスの山々のすべての地域をくまなく支配することは難しく,インカ人の王は各地の首長にさまざまな方法で自らの権威を認めさせようとしていました(注)。
冬至に行なわれる太陽の祭り(インティライミ)は国王の権力を国民に見せ付ける上で,特に重要で盛大な儀式でした【セH11亀甲や獣骨を焼いて,そのひび割れによって神意を占ったわけではない】。
(注)インカ帝国領内の各地にはクラカ(首長)層による支配が続いていました。「クラカ(首長)層の権威は,アイユ(共同体)民にどれだけ大盤振る舞いできるかにかかっており,それをもっとも実現し得たインカ王が互酬関係の頂点にたって周辺諸国を統合した」のです(金井雄一他編『世界経済の歴史―グローバル経済史入門』名古屋大学出版会,2010年),p.54。網野徹哉『インカとスペイン帝国の交錯』講談社,2008年も参照)。
人口調査も巡察使に行わせ,それにもとづき徴税し,記録はアルパカやラマの毛から作った縄の結び目で数量を表すキープ(結縄) 【東京H12[2]】 【セH11象形文字ではない】【セH18,セH21ユカタン半島のマヤ文明ではない,セH29試行,セH30】【中央文H27記】でおこないました。労働による徴税(労務のことをミタといいます)もあり,神殿建設や農作業に従事させました。
そのために張り巡らせたのが,南北にのびる「インカ道」(四大街道(カパック=ニャン))の整備です。駅舎や倉庫をもち,駅伝方式で情報や貢納品を飛脚(チャスキ) 【東京H12[2]】に伝達させたのです。インカの首都には巨大な倉庫があり,貢納品が各地から大量に輸送されました。インカ人の支配層はこのような方法で1000万人を超えたといわれる領域内の人々を把握しようとしたのです。
1911年に考古学者〈ハイラム=ビンガム〉(映画「インディ=ジョーンズ」のモデルと言われます)によって発見された,標高2400mの“空中”都市マチュ=ピチュ【セH17,セH28】(◆世界複合遺産「マチュ=ピチュ」,1983)に見られるように,すき間なく石を積み上げる高度な石造技術も特徴的です。マチュ=ピチュは貴族のリゾート地とも,避難所ともいわれています。ちなみに,標高3400mの首都クスコ【セH11テノチティトランではない】【セH19マヤ文明ではない】にあった太陽神殿は,スペイン人による破壊により現存しません。
なお,彼らの言語はルナ=シミ語といい,スペイン人はそれをケチュア語と呼びました。現在のペルーの第二公用語となっています。
現在のベネズエラのカリブ海沿岸に,1498年に〈コロン〉〔コロンブス〕が上陸。この第三回航海で,彼はベネズエラの豊富な真珠を発見します。〈マルコ=ポーロ〉の『世界の記述』を通したインドか日本に真珠があるという情報から,〈コロン〉は「インドに到達したのだ」という確信を深めます。
(注)山田篤美『真珠の世界史』中公新書,2013,p.79。
○1200年~1500年のオセアニア ポリネシア
ポリネシア…①チリ領イースター島,イギリス領ピトケアン諸島,フランス領ポリネシア,③クック諸島,④ニウエ,⑤ニュージーランド,⑥トンガ,⑦アメリカ領サモア,サモア,⑧ニュージーランド領トラケウ,⑨ツバル,⑩アメリカ合衆国のハワイ
◆ポリネシア系のマオリはニュージーランドに到達し,マオリを乱獲した
ポリネシア人は,その卓越した航海技術により,人類でもっとも広範囲に拡大した民族となります。
ポリネシア人が最後に移住したのはニュージーランドでした。ニュージーランドは,赤道付近の貿易風という東風と,ニュージーランド付近の偏西風という西風に挟まれた地点に位置するため,到達するのが一番難しかったのです。
ニュージーランドに移住したポリネシア人をマオリ【セ試行 絶滅していない】といい,狩猟・採集・漁労文化を発展させました。彼らは当初から「マオリ」と自称していたわけではなく,ヨーロッパの人々と出会って以降,自分たちのことをそのように区別して呼ぶようになったと見られています(「マオリ」はマオリ語で「ふつうの」「正常の」という意味)(注2)。従来のバナナ,パンノキ,ココナツが生育できないことを知ると(タロイモ,ヤムイモも北島でしか育ちません),ワラビやニオイシュロラン(ヤシに似る)や海産物,それにキーウィ,ワカ,モア類のような走鳥類が新たな食料となりました。マオリが到達した頃のニュージーランドには,とべない鳥のモアが生息していましたが,マオリによる乱獲の結果,モア科の鳥は1400~1500年に絶滅してしまいました(注3)。
(注1)クライブ=ポンティング,石弘之訳『緑の世界史(上)』朝日新聞社,1994,p.60
(注2)山本真鳥編『世界各国史 オセアニア史』2000,p.168
(注2)従来は気候変動説が唱えられていましたが,現在ではマオリによる乱獲説が有力となっています。ジャレド・ダイアモンド,秋山勝訳『若い読者のための第三のチンパンジー』草思社文庫,2017,p.308。
○1200年~1500年のオセアニア オーストラリア
なお,オーストラリアの北部のアラフラ海には,東南アジア方面からナマコを求める漁師が到達していたとみられます(注)。内臓をとって薄い塩水などで煮た後,乾燥させたナマコを海参(いりこ)といい,中華の高級食材として,中国人に重宝されたのです。ただ,内陸狩猟採集生活を続けていたオーストラロイド人種のアボリジナルとの直接的な交流はなかったようです。
(注)鶴見良行『ナマコの眼』筑摩書房,1993年。
○1200年~1500年のオセアニア メラネシア
メラネシア…①フィジー,②フランス領のニューカレドニア,③バヌアツ,④ソロモン諸島,⑤パプアニューギニア
○1200年~1500年のオセアニア ミクロネシア
ミクロネシア…①マーシャル諸島,②キリバス,③ナウル,④ミクロネシア連邦,⑤パラオ,⑥アメリカ合衆国領の北マリアナ諸島・グアム
◆モンゴル人は,ユーラシア大陸の定住農牧民のネットワークを統合する
ホラズムは滅び,モンゴルの時代が到来した
ウイグルがキルギズにより840年に崩壊してからというもの,モンゴル高原には統一政権が存在しませんでした。契丹や金が,遊牧民がまとまり強力な政権が生まれないように画策していたためです。
モンゴル人の拠点は,黒竜江(アムール川)上流のオノン川。12世紀後半の時点では,周囲のケレイト部(モンゴル高原中央部)や,ナイマン部(モンゴル高原西部)にくらべて弱小勢力でした。
そこに現れたのが〈テムジン〉【立教文H28記】という男です。彼は有力氏族のボルジギン氏に属し,父はタタル部(モンゴル高原東部)に毒殺されました。
彼は1200年~1202年にかけてモンゴル部族とタタル部族のリーダーとなり,1203年にはケレイト部を倒しました。さらに,ナイマン部を中心とする連合軍を破って,1206年にクリルタイ【東京H18[3]】【セH3】【セH26三部会ではない】【追H21】【立教文H28記】と呼ばれた会議で〈チンギス=ハン(カン)〉(位1206~27) 【セH4】【セH29試行 系図】と名乗ることを認められ,モンゴル高原を統一しました。
遊牧民が,ほかの部族を支配下に入れたり連合したりしてつくる「遊牧国家」は,〈チンギス=ハン〉以前にも存在し,匈奴による遊牧国家以来の伝統がありました。しかし,今までの遊牧国家と異なるのは,部族が連合して政治をおこなうのではなく,権力を〈チンギス=ハン〉とその家系に集めた点にあります。
彼は千戸制(せんこせい,千人隊)を整備し,西への遠征を開始しました。千戸制とは,支配下の全遊牧民を1000家族にわけて,そこから1000人の兵士を出させて,千人隊を組織させたものです。普段の生活と戦争のときの集団の単位を同じにすることで,機動力を高めたのです。千人隊の隊長の子弟には,〈チンギス=ハン〉のもとで生活を送らせ,絆や連帯感をはぐくませました。
華北へのモンゴルの進出は1210年代には始まっていました。とき同じくして黄河の大氾濫が起き,混乱に拍車がかかります。
〈チンギス=ハン〉は巨大な部隊を引き連れ,すでに西遼(カラキタイ) 【セH23,セH27】を滅ぼしていたナイマン部(10世紀~1204) 【セH23ウイグルではない】,トルコ人奴隷(マムルーク)が建国しゴール朝を滅ぼしていたイランのホラズム=シャー朝(1077~1220)【セH13滅ぼしたのはガザン=ハンではない,セH24】【追H20滅ぼしたのはセルジューク朝ではない】と大夏(西夏,1038~1227)を滅ぼしました(注) 。ちなみにデリー=スルターン朝時代のインド西北部も進入を受けています。モンゴルは,ホラズムのような抵抗した支配者に対しては容赦ありませんでしたが,征服した土地の農民や商工業者は労働力として重視されましたから,支配者が従えば徹底的に滅ぼすということはしませんでした。
なお,タリム盆地の天山ウイグル王国の王は,〈チンギス=ハン〉の娘とと婚姻関係を持つことで服属し,〈チンギス=ハン〉の“5番目の子”という称号まで得ました。友好関係を樹立して命運を保ち,兵士・官僚としても大活躍しました。
〈チンギス=ハン〉は広大な領土を東西に二分し,3人の弟に軍民が与えられ「東方三王家」(左翼三ウルス)となりました。ウルスというのは「土地+人々」を合わせた呼び方で「国民」と訳されることもあります。
また,西方には長男から三男に軍民が与えられ,「西方三王家」(右翼三ウルス)となります。このうちロシア方面に置かれたのは長男の〈ジョチ〉(ジュチ)で,のちにキプチャク=ハン国(ジョチ=ウルス)【京都H19[2],H22[2]】と呼ばれることになります。
中央アジアには〈チャガタイ〉(チャーダイ)と〈オゴタイ〉(オゴデイ)が配置され,末子〈トゥルイ〉はモンゴル高原に置かれます(末子相続の風習のため)。
(注)末期の大夏(西夏)は初めモンゴルと軍事同盟を結び金を攻撃し,のちに南宋とも連携して生き残りを図っていました。
◆オゴデイが大ハーンに即位し,首都を整備,駅伝制を施行した
オゴデイ,カラコルム建設,ジャムチ整備,金滅亡
〈フビライ〉の後継者は,末子相続の風習にのっとれば〈トゥルイ〉ということになりますが,実際に継いだのは〈オゴデイ〉(オゴタイ,位1229~41) 【セH2大都に都を置いていない】でした。彼は,モンゴル高原にカラコルム【京都H20[2]】【セH2大都ではない,セH12匈奴が建設していない】【セH19オゴデイのとき,セH18黄河上流ではない,セH28地図上の位置を問う】【追H30建設者を問う】【中央文H27記】という新都を建設し,駅伝制(ジャムチ【京都H20[2]】【東京H6[1]指定語句,H15[3],H20[3],H27[1]指定語句】)を整備しました【※東大の頻度高い】。
通行手形(パイザ,牌符,牌子【東京H20[3]】)があれば領内を安全に通行することが可能でした。
1234年に女真(女直)人の金(きん,1115~1234)を滅ぼしました【セH19】。また,「カン」に代わる「カアン」(大ハーン)という称号を初めて用いました(オゴデイ=ハーン)。これはかつてモンゴル高原を支配した柔然の王の称号「可汗(カガン)」がもとになっているといわれます。オゴタイ以降のモンゴルの指導者の称号は「カアン」です。
彼には契丹人の〈耶律楚材〉(やりつそざい)が仕えていたように,有能な人物であればモンゴル人以外でも重用したことが特徴です。実力があるならば,民族の違いなど関係ないというわけです。ここにモンゴル人の強さの秘密があります。
◆モンゴル人は東ヨーロッパに進入し,ロシア人のキエフ大公国を支配した
さらに〈バトゥ〉(1207~55) 【セH11ガザン=ハンとのひっかけ,セH12フラグではない】が,ユーラシアの草原地帯を走破して東ヨーロッパに進出し,1241年にワールシュタット(ワールシュタット〔ヴァールシュタット〕とはドイツ語で死体の山という意味です【セ試行 モンゴルは敗れていない】【セH3 時期(クビライの「即位後ただちに」ではない)】。
現在はポーランド領レグニツァなのでレグニツァ(ドイツ語ではリーグニッツ)の戦いといいます。)の戦い【セH14時期(ルブルックがカラコルムを訪れる以前かを問う)】で神聖ローマ帝国・ポーランドの連合軍を破ります【セH5ヨーロッパに侵攻したモンゴル人の多くは,キリスト教徒となったわけではない】。この遠征に従軍していたの〈モンケ〉は,次代のカアンに即位します。
また,その〈モンケ=カアン〉(位1251~59) 【京都H20[2]】の命令で,弟の〈フレグ〉(1218~65) 【セH21イスラームを国教化していない】が1258年に西アジアのバグダードを陥落させ,アッバース朝のバグダード政権を滅ぼしました【セH14時期(ルブルックがカラコルムを訪れる以前ではない)】。このときにバグダードは100万人の人口を誇る都市でしたが,包囲戦によって数十万人以上の市民が犠牲になったといわれます。
◆モンゴル人は,バグダードのアッバース朝を滅ぼしたが,マムルーク朝に撃退される。アッバース家のカリフはマムルーク朝の保護下に存続する
諸民族・宗教に寛容な政策で,広域の商業を促す
〈フレグ〉はその後,エジプトを拠点に1250年に建国されたマムルーク朝のスルターン〈バイバルス〉率いるマムルーク朝(1250~1517)とのパレスチナ北部でのアイン=ジャールートの戦い(1260) で敗れ,〈フラグ〉の与えられた領域はジョチ=ウルスと呼ばれ,イランとイラクの地域にまたがる政権となりました。この政権は,イル=ハン国とも呼ばれます【セH11地図:13世紀後半の領域を問う】 【セH21】。首都はカスピ海南東の都市タブリーズです。
なお,最後のカリフ〈ムスタアスィム〉(位1242~58)は〈フレグ〉に処刑されましたが,父方の叔父がマムルーク朝の〈バイバルス〉の元に脱出し,〈ムスタンスィル2世〉としてカリフに即位しました。これ以降,カリフはマムルーク朝の保護下に置かれる形で存続します【セH16「マムルーク朝の支配下,オスマン朝のカリフがここに擁立された」かを問う】。したがって,アッバース朝はその後も存続したとみることもできます。
しかしカリフは事実上マムルーク朝の傀儡(かいらい。操り人形のこと)となり,メッカ(マッカ),メディナ(マディーナ),イェルサレムの三大聖都を統治したマムルーク朝は,一挙にスンナ派のリーダー的国家となりました。1291年には,シリアにあった十字軍最後の拠点アッコンを滅ぼしています(◆世界文化遺産「アッコの旧市街」、2001。現在のイスラエル)。
◆各地のウルス(政権)がゆるやかに結びつき,ハーンの権威の下でまとまりを形成する
モンゴル帝国は“分裂”したわけではない
マムルーク朝を支配下におさめることには失敗したものの,こうしてユーラシア大陸のほとんどがモンゴルの支配下に入ることになり,広大な領域を包み込む交流圏が成立していきます。
中央ユーラシアには,〈チンギス=ハン〉が子どもである〈チャガタイ〉と〈オゴタイ〉に軍民を与えていました。土地と人々を合わせてウルスとよびます。ウルスというのは,「国」とか「国民(くにたみ)」といった意味で,モンゴル人が,人を集団の単位として支配を考えていたことがわかる言葉です(注1)。
このうち〈オゴタイ〉は自分の子どもたちにも軍民を与えたので,〈オゴタイ〉系の諸ウルスが立ち並ぶ状態となりました。ですから,かつて教科書に載っていたような「オゴタイ=ハン国」という国家が,ただ一つ存在していたわけではありません(注2)。
〈グユク=ハーン〉以降は,モンゴル皇族の内輪もめもあって,各地に「ハン国」と呼ばれる以下の①~③の諸政権が成立していきます。
①先ほどの〈ジョチ=ウルス〉(キプチャク=ハン国,ロシア語のゾロタヤ=オルダ(注3)を訳すと金帳汗国(黄金のオルド))(ジョチ=ウルス))→南ロシア
②〈フレグ=ウルス〉(イル=ハン国)【セH11地図:13世紀後半の領域を問う】→西アジア
③〈ハイドゥ〉の政権→中央アジア
〈ハイドゥ〉は,〈オゴタイ〉の孫ですからオゴタイ=ハン国ともいえそうですが,〈ハイドゥ〉の政権にはオゴタイ家の一門以外にも,チャガタイ家の当主やその一門,さらに〈アリク=ブケ〉も参加していましたから,どちらかというと「〈フビライ〉(クビライ)に反対する勢力」の結集した政権といったほうが正確です(注2)。ただし,反フビライ勢力といっても,〈ハイドゥ〉は〈フビライ〉のハーン位をねらっていたわけではありません。
のちに〈フビライ〉も〈ハイドゥ〉も亡くなると,1305年に大元ウルスの〈フビライ〉家の皇帝と〈ハイドゥ〉政権は和解。しかし,翌1306年にチャガタイ家の当主である〈ドワ〉が,〈ハイドゥ〉の跡継ぎ争いに首を突っ込み,これを乗っ取ります。こうして成立したのがチャガタイ=ハン国です。ただ,チャガタイ=ハン国にはオゴタイの一門も含まれていますから,純粋にチャガタイ家の一門の政権というわけではありません。
こうしてモンゴル帝国(大モンゴル国;イェケ=モンゴル=ウルス)は,〈フビライ=ハーン〉の大元ウルスが,①キプチャク=ハン国,②イル=ハン国,③チャガタイ=ハン国や,その他の諸勢力の秩序を維持する形となりました。たしかに,①がマムルーク朝(〈バイバルス〉はキプチャク草原のポロヴェツ人の出身という共通項もあります)に接近して,②と抗争したように,政権同士の対立関係はありました。チャガタイ=ハン国は〈フビライ=ハーン〉の皇帝位を認めており,決して“分裂”していたわけではありません。
また,政治的な区分が生じたとしても,経済的にはアフリカ大陸にも通じるユーラシア大陸(あわせて,アフロ=ユーラシアと呼びます)を陸海に結ぶ経済ネットワークは活発に動いていたのです。
モンゴル帝国は広大な領域を,モンゴル文字(パスパ文字またはウイグル式モンゴル文字)による定型文書によって統治しました。文書の授受にあたっては各地で翻訳文書が作成され,多言語によるコミュニケーションの必要から,対訳語彙集や世界初の外国語会話マニュアルも登場しています(注4)。
(注1)モンゴル語で「国」に相当する「ウルス」,トルコ語の「イル」もしくは「エル」という言葉は,遊牧民に独特の集団概念で「人間集団」を原義とするため,土地や領域の側面での意味合いは薄いのです。杉山正明がいうように《固定された国家ではなく,人間のかたまりが移動すれば,「国(ウルス)」も移動してしまう類の国家》である(杉山正明『大モンゴルの時代』(世界の歴史9)中公文庫,2008年,p.86)。
(注2) 赤坂恒明による解説を参照。『歴史と地理』「世界史の研究」第255号,2018。
(注3)杉山正明『クビライの挑戦―モンゴル海上帝国への道』朝日新聞社,1995,p.29。
(注4)堤一昭「モンゴル帝国と中国」,桃木至朗・秋田茂『グローバルヒストリーと帝国』大阪大学出版会,2013,p.50~p.52。
このうちイル=ハン国(フレグ=ウルス)は,ネストリウス派キリスト教を保護したほか,中国の絵画が伝わってミニアチュール(細密画)という技法で多くの絵が描かれました。これらは別個の国というわけではなく,大ハンのもとでゆるやかに連合していました。詩人〈サーディー〉(1184?~1291?)は『薔薇園(ばらえん)』を著しています。
チャガタイ=ハン国のときに,パミール高原以西のアム川・シル川流域を中心とする西トルキスタンに,テュルク系の人々が多数移動し,定住するようになっていきました。彼らは書き言葉としてテュルク系のチャガタイ語(注)を発展させ,従来のペルシア語とともに使われるようになります。主にペルシア語を使用する人々は「タジク人」と呼ばれるようになりますが,複数の言語を話せる者もいました。
(注)一般に「テュルク語」【セH5インド=ヨーロッパ語族ではない】というと,チャガタイ語やオスマン語ができる前のトルコ系の諸語を指します。テュルク語系の「チャガタイ語」は13~19世紀の中央アジアの文章語を指します。単に,「トルコ語」という場合にはオスマン語と現代トルコ語のどちらか区別する必要があります。
◆クビライ=ハーンは海上進出を図り,ユーラシア大陸を東西に走る陸海のルートを結合させた
クビライは,南方の海民と結び海軍を掌握する
第5代の〈クビライ=ハーン〉(位1260~94) 【セH3チンギス,オゴタイ,チャガタイではない】【セH26ヌルハチではない】は,大ハーン位に就くと,オゴデイ(オゴタイ)家の〈カイドゥ〉(ハイドゥ,?~1301)による抵抗(カイドゥ(ハイドゥ)の乱【セH11「元の中国支配が崩壊するきっかけとなった出来事」ではない】【セH14時期(ルブルックのカラコルム訪問以前ではない),セH30】)の鎮圧に苦慮することとなります。
一方,現在の北京に進出してこれを大都【セH9】として,で元(1271~1368)という国号に改めました。
1279年【セH3時期(ハイドゥの乱の「最中」か問う)】には,すでに首都の臨安を1276年に失っていた南宋の残党・皇族を厓山(崖山,がいさん)の戦いで完全に滅ぼします【セH3】。
さらに,日本や東南アジア各地に遠征軍を派遣。
〈クビライ〉の強さの秘密は,降伏した南宋の将軍を,元の軍司令官としてそのまま重用したことにあります。「支配に役に立つ者はすべてモンゴルとして扱う」という,柔軟な対応のあらわれです。実際に,当時の史料中の「モンゴル」というのは民族の名前ではなく,モンゴルの支配層であれば民族の垣根を超える呼び名であったわけです。
ビルマのパガン朝【セH13トゥングー朝ではない,セH26地域を問う】はこのとき滅んでいますが,ヴェトナムの陳朝大越国【セH16李朝ではない,セH19時期】は撃退に成功しました。陳朝では民族意識が高まり字喃(チューノム)【セH24時期】という民族文字を13世紀頃から作り始め文学作品などで使用されましたが,公用文における漢字の使用は続きました。
なお,当時支配地域を拡大していたアイヌ人(骨嵬)により圧迫されたニヴフ人が,樺太から元に対して支援を求めたことに端を発し,アイヌに対し交易ルートを確保する目的で遠征しています(北からの元寇)。
◆「中国」を草原地帯も含めてとらえることで,中国の士大夫はハーンを皇帝として受け入れた
北方遊牧民地帯も含めた「中国」概念が浸透する
〈クビライ〉はあくまで「ハーン〔カアン〕」として中国支配に臨んでいます。
モンゴル人はユーラシア各地で,統治のための手段として,現地の君主号を受け入れていたのです。
一方,漢人の皇帝に仕えていた「士大夫」層も,積極的に〈クビライ〉を皇帝として受け入れました。モンゴルの君主が,漢人の「中国」を支配しているという現実を認めることで,自分たちの地位を守ろうとしたのです。
従来は「夷狄」ととらえていた北方の遊牧民地帯も含めて「中国」であるという認識は,北も南も含めた「混一(こんいつ)」と表現されていました(注)。
(注)堤一昭「モンゴル帝国と中国」,桃木至朗・秋田茂『グローバルヒストリーと帝国』大阪大学出版会,2013,p.56。
〈クビライ〉は中国を支配するのに,漢人よりも西域出身の色目人(しきもくじん)【東京H6[1]指定語句】を重用しました【セH4唐代ではない,セH9「色目人第一主義」をとったわけではない】【セH19蔑視されていない】。
金の支配下にあった漢人・女真(女直)人や契丹人たちは漢人(北人とも呼ばれました),南宋支配下の住民は南人【東京H25[3]】と呼び待遇にランクをもうけました。
中央の官制は,中書省が統治機関として置かれ,14世紀初めには尚書省を廃して六部から独立させました。
地方支配にあたっては,中書省と同格の行中書省を各地に置き,統治しました。これが現在の中国の「省」の起源です。漢民族の土地制度である佃戸制(でんこせい)は,変更されることなく続きました【セH14】。
元は,以前考えられていたほど中国文化に対して冷淡ではなかったとされています。元に仕えた宋の王族である〈趙孟頫〉(ちょうもうふ,1254~1322)は書画を極め,唐の頃のスタイルを復活させて多くの文人画を残しました。〈黄公望〉・〈倪瓚〉・〈呉鎮〉・〈王蒙〉も,のちのち明や清になってから「元末四大家」と絶賛されることになる南宗画の書画クリエイターです。
たしかに科挙は一時停止され【東京H25[3]「科挙試験を一貫して重視したわけではない」】合格者も少なくなりましたが,科挙は1315年に再開されています。元の支配層にとってみれば,いくら儒教の経典に詳しくても「意味がない」わけです。それよりも即戦力のある人材,専門的な官僚(テクノクラート)がほしいというわけです。
職を失った士大夫層は,宋の時代に異端とされていた〈朱熹〉(しゅき,1130~1200) 【セH11】【慶文H30記】の朱子学【セH11陽明学ではない】【慶文H30記】に飛びつきます。理気二元論【慶文H30記】,大義名分論【慶文H30記】を展開する朱子学は,元=異民族よりも漢人のほうが本来は上にあるべきだという読み方を儒教に提供し,支持されたわけです。朱子学は次の明代に官学化されることになります。
〈クビライ〉は出版事業に積極的で,南宋代から編集のはじまっていた『事林広記』という百科事典が出版され,元曲の台本や,明代に完成する『西遊記』『水滸伝』『三国志演義』【セH9[21]】の原型も出回りました。出版ブームに乗って,子供向けの『十八史略』(南宋の南宋の〈曾先之〉作)や,元の政府が出版させた農書『農桑輯要』などが多数印刷されました。
儒学者にとっては元代は「迫害」の時代とみなされますが,後世の “後付け”という面もあります。後世の儒学者は,この時代の儒学の境遇を,「九儒十丐」と表現し“乞食(丐)が上から10番目のランクなら,儒学者は上から9番目”と表現しましたが,西方の文化を熟知するモンゴル人にとって儒学者の情報が“無用”と映った点はいなめません(九儒十丐には前置きがあって,「一官二吏三僧四道五医六工七猟八民九儒十丐」のように世の中の職業をまとめた表現です)。
元【セH27清ではない】では,イスラームの暦学・天文学【セH19,セH23】の影響を受けた授時暦【東京H6,H27[1]指定語句】【セH2時期(明末ではない)】【セH23イスラーム天文学の影響があったか問う】【追H21】が成立しました。イスラーム天文学【セH2ヨーロッパ天文学ではない】で使用されていた観測機器を用いた漢人の〈郭守敬〉(かくしゅけい,1231~1316) 【セH6】【セH19,セH23,セH27顧炎武ではない】【追H21】により,中国の伝統的な暦法によって作成されました(注)。中国では天子である皇帝が,天文台を設置して正確な暦を作成させることが求められていたのです。これは1281年から施行。暦のタイプは太陰太陽暦です。のちに江戸時代の日本に伝わり〈渋川春海〉により1684年に貞享暦(じょうきょうれき) 【セH6】が作成され,翌年施行されています(のち,清代にイエズス会士〈アダム=シャール〉の時憲暦の知らせを聞き,キリスト教色を排除した宝暦暦(1755~98)が制定されましたが粗悪で,幕府天文方〈高橋至時〉により西洋の暦法をとりいれた寛政暦が制定(1798~1844),1844年以降は1873年のグレゴリオ暦導入までは天保暦を使用)。
(注)山田慶児『授時暦の道―中国中世の科学と国家』みすず書房,1980。
〈クビライ〉はチベット仏教【セH12イスラム教を国教として保護したわけではない】の僧〈パクパ〉(パスパ,1235~80) 【慶商A H30記】を重用し,パクパ(パスパ)文字【東京H10,H30[3]】【セH12漢字をもとにしていない。タングート族の文字ではない】【セH14漢字をもとにしていない】【追H30西夏ではない】というモンゴル語のための文字をつくらせています。〈パクパ〉は11世紀中頃に西チベットではじまったサキャ派のチベット仏教指導者で,〈クビライ〉の支持を背景にして,チベットの支配権を強めました。
イランのコバルト顔料を用い,白磁に青い着色をした染付(青花) 【東京H27[1]指定語句】という磁器【セH24唐三彩とのひっかけ】も作られるようになりました。染付技術が可能になったのも,モンゴル時代のユーラシアに交流圏が成立したおかげです。
モンゴル帝国〔大モンゴル国〕は交通路の安全を確保し,治安維持や駅伝制(ジャムチ) 【セH18金ではない】の整備によって,ユーラシア大陸の陸上交通がさかんになりました。例えば,西方からは十字軍を組織してイスラーム勢力と戦っていたキリスト教が,モンゴルと提携することによってイスラーム勢力を挟み撃ちにしようというもくろみもあり,多数の使節を派遣しました。モンゴル人の宗教はシャーマニズム(目にはみえない世界との交信ができる霊能者が,踊りなどによって何かが乗り移ったような状態で我を忘れ,占いやお祓いなどをするものです。)でしたが,〈クビライ=カアン〉の母(〈ソルコクタニ=ベキ〉)がネストリウス派キリスト教徒であったといわれるように,モンゴル帝国でもキリスト教の信仰はありました。〈モンケ=カアン〉もはじめネストリウス派を信仰していたようです。
その噂もあってか,ローマ教皇〈インノケンティウス4世〉(位1243~54)は〈プラノ=カルピニ〉(1180?~1252) を,フランスの〈ルイ9世〉(聖王) 【京都H20[2]】は〈ルブルック〉【京都H20[2]】【セH3マルコ=ポーロとのひっかけ】【セH14時期(ルブルックがカラコルムを訪れる以前に起きたものを選ぶ)】を〈グユク=ハーン〉(定宗,位1246~48)に送っています。この目的には布教の理由のほかに,当時イスラーム教徒との間で続けられていた十字軍への支援を求める意図もありました。この2人は〈フランチェスコ〉【京都H20[2]】派の修道会士です。
ほかにも,父【セH3】と叔父とともに陸路で旅行したヴェネツィア共和国【セH29場所を問う】【セH3ルイ9世に派遣されていない,セH8ジェノヴァではない(地図上の位置からもわかる)】の商人〈マルコ=ポーロ〉(1254~1324) 【東京H17[3]】【セH3,セH8】 は,大都で元の〈クビライ〉につかえたとされ【セH3「南人」ではない】,帰路は元の皇女を結婚のためイル=ハン国まで運ぶ船に同乗しました。体験談を『世界の記述(東方見聞録,イル=ミリオーネ)』【セH3史料が引用・著者を答える】にまとめ,大きな反響をもたらします【セH3まだ活版印刷術は発明されていない】。
たとえば,台湾の対岸にある泉州(ザイトゥン) 【セH10マカオとのひっかけ】に立ち寄り,「ザイトゥンには,豪華な商品や高価な宝石,すばらしく大粒の真珠がどっさり積み込んだインド船が続々とやってくる。この都市に集められた商品は,ここから中国全域に売られる」と繁栄ぶりを記しています。杭州(こうしゅう)も「キンサイ」として繁栄ぶりを記録しています。ただ,中国側には記録が残されていないため,疑問視する説もあります【セH8マルコ=ポーロの推定移動経路をみて,「メッカ」「カラコルム」を訪ねていないこと,「チャンパ」を経由していることを特定する】。
13世紀末には〈モンテ=コルヴィノ〉(1247~1328) 【東京H6,H27[1]指定語句】【セH8元を訪問したか問う】【追H30】 が,元(大元ウルス)【追H30カラ=ハン朝ではない】【セH8】の大都の大司教として中国初のカトリック布教を成功させています。
首都の大都には運河が延長され,長江から海をまわって北上して大都に至る海運も発達しました。従来の大運河も補修され【セH19】,大都に通じる運河も整備されました(新運河) 【セH9「江南の穀物が華北にある首都まで運河で運ばれた」か問う】【セH19】。
商業の発展とともに,元の時代には庶民文化が発展し,元曲【セH3】という戯曲が多数つくられました【セH3「もっぱら宮廷の舞台で上演されたのではない」】。元曲はかっこつけた仰々しい言葉ではなく,庶民の口語で書かれたところがポイントで,恋愛結婚を題材とした『西廂記(せいしょうき,せいそうき)』【セH9[21]】【セH21時代を問う】のようなラブストーリーが好まれました。
〈クビライ〉の晩年には,クリルタイで彼を支持した東方三王家の乱が起きますが,鎮圧。1294年に亡くなっています。跡継ぎを決める際にはクリルタイはひらかれず,大ハーンの位はクビライ家に世襲されることになります。
しかしその後の元の君主は,チベット仏教(俗にいう「ラマ教」は,仏教とは別の宗教というニュアンスを含むため,チベット人はこの呼称を使いません)に入れ込み【セH14ルブルックのカラコルム訪問以前ではない】,交鈔(こうしょう) 【セH22,H29北魏の時代ではない】【セH8時期(マルコ=ポーロと同時期)】という紙幣を濫発したために物価が高騰し,国力を弱めていきました。紙幣が流通するようになると,かさばる銅銭が余るようになり,「銅」そのものにも価値があるので近隣諸国にそのまま輸出されました。例えば,鎌倉大仏は,銅銭によって作られたのではないかといわれています。
◆「14世紀の危機」によりユーラシア大陸各地のモンゴル政権の支配は揺らぎ,モンゴル帝国の“跡継ぎ”国家や影響を受けた国家が各地で成立していく
1310年頃から1370年頃にかけて,北半球は寒冷化し,各地で不作や飢饉がおきました。さらに,モンゴル帝国によってユーラシア一帯の人の移動が盛んになったこともあって,ミャンマーで流行していたとみられるペスト(黒死病) 【セH5ペストの大流行の時期を問う】が,1320年以降西へと広がり,1335年に洛陽→1347年にイスファハーン・ダマスクス→1348年にヴェネツィア・メッカ・ロンドン…と,またたく間にユーラシア大陸一帯に広がります。交易に支障が出てくるようになると,モンゴル帝国各地で支配にゆるみが生じました。
キプチャク=ハン国では1359年に〈バトゥ〉の血統が途絶え,分裂。東スラヴ系の諸公国・大公国の中から,モスクワ大公国【セH3時期(ハイドゥの乱の時期ではない)】が力を付けモンゴル帝国の血統を権威として用いて強大化していきます。なお,キプチャク=ハン国ではイスラーム教【セH5】が保護されています。
チャガタイ=ハン国は1335年に東西に分裂しました。そのうち西チャガタイ=ハン国から,1370年に〈ティムール〉が領域拡大に乗り出し,ティムール帝国を建設していきます。
なお,マムルーク朝も14世紀中頃のペストの流行により,衰退に向かいます。
◆モンゴル高原でモンゴルは存続し,明代の中国への進出をはかり続けた
モンゴルは存続し,中国では臨戦態勢が続いた
中国の元では,末期に1351年~66年に紅巾の乱【東京H25[3]】【セH4赤眉の乱・呉楚七国の乱・陳勝呉広の乱ではない,セH11元の中国支配が崩壊するきっかけとなった出来事か問う,セH12白蓮教系の組織か問う】【セH19赤眉・黄巣・安史の乱ではない,セH21時期】が起きます。紅巾軍は,弥勒仏(みろくぶつ)【セH12】が現世を救済するために現れると信じる白蓮教系の組織から成っていました。彼らにより大運河が寸断され,江南と北京を結ぶ海運ルートが紅巾の乱とは一線を画して反乱を起こした有力者〈張士誠〉(1321~1367)により遮断されると,補給路を絶たれた元はまさに“一巻の終わり”となります。
白蓮教徒【セH12】の一派である〈朱元璋〉は,まずライバルの〈張士誠〉の反乱を鎮圧し,その上で1368年大都を陥落させました。最後の皇帝〈トゴン=テムル〉(順帝)はモンゴル高原に退却しましたが,帝室は存続したわけですので,厳密にいえば「滅んだ」わけではありません。
20年間,元の帝室は持ちこたえましたが,明による攻撃により〈トグス=テムル〉(位1378~88)が襲われ,逃げている途中に殺害されました。中国(明)側は,これをもってモンゴル(大元)が滅んだという立場から,これ以降のモンゴルのことを「韃靼(だったん)」と呼ぶようになりました。
しかし実際には,モンゴルは滅んでしまったわけではなく,存続しています。ただ,〈チンギス=ハーン〉と無関係なのに「ハーン」を名乗る者が現れるようになりました。
モンゴル帝国以降,〈チンギス=ハーン〉の直系の者にモンゴル高原の遊牧民全体の支配者になる資格があるという原則が生まれます。そこで,支配者になろうとする者は「チンギス=ハーン」との血筋のつながりがある!と主張することで,遊牧民たちを納得させようとしたのです。
例えば,15世紀初めにはオイラト部【セH16】の〈エセン〉【セH13アルタン=ハーンではない】が,チンギス家と結婚関係をもつことで勢力を拡大しました。西方では女真(女直)人を,チャガタイ=ハン国の東半(モグーリスタン)を制圧しています。しかし,明との間で貿易をめぐるトラブルが生じ,1449年に中国に進入して明【セH20前漢ではない】の皇帝〈正統帝〉(英宗)【セH16万暦帝ではない】を捕虜にしました(土木の変【セH13,セH18地図・靖康の変ではない】)。〈エセン〉は1452年にハーンに即位しましたが,それには批判も多く,1454年に殺害されています。結婚関係だけではダメだというわけですね。
◆〈ダヤン=ハーン〉がモンゴルを再統一,チベットではツォンカパがチベット仏教を改革する
モンゴルが〈ダヤン=ハーン〉により再統一される
そこでその後,チンギス家の直系である〈ダヤン=ハーン〉(位1487~1524)が,大ハーンとしてようやくモンゴル高原の広範囲を統一することに成功します。ダヤンというのは大元ということで,元(北元)の復興でもあります。明は「モンゴルは1388年に滅んだ」という立場をとったので,この勢力をタタールと呼びましたが,正確にいうとモンゴルに違いありません。
彼はモンゴルを,直轄地であるチャハル,ハルハ,ウリャンハンと,間接支配地に分けて統治しました。
アルタンは現在も内モンゴルの中心になっているフフホタ(フフホト)を建設し,中国との通商を推し進めて発展していきました。フフホトは現在,中華人民共和国の内モンゴル自治区の省都として発展しています。
チベットでは,元の時代に〈フビライ=ハーン〉に保護されたサキャ派への批判が高まり,さまざまな派が対立しました。その中から,〈ツォンカパ〉(1357~1419) 【セH13・H20,H22時期】がインドから伝わった経典を再編成したゲルク派を開き,黄色い帽子を用いたので黄帽派【東京H12[2]】【セH13・H20】とも呼ばれました。
◆チャガタイ=ハン国西部からおこったティムール帝国は,モンゴル帝国の“跡継ぎ”国家
ティムール帝国は,モンゴル帝国の跡継ぎ
タリム盆地を中心とする西トルキスタンでは,モンゴル系のチャガタイ=ハン国の東半分を占めたモグーリスターン=ハーン国では,〈トゥグルク=ティムール=ハーン〉がイスラーム教に改宗し,本拠地はバルハシ湖に注ぐイリ川周辺で,14世紀なかばにはシル川の東部から天山山脈東部までを領域に加え,東西のトルキスタンを合わせました。
しかし,15世紀の後半になると,ウズベク人がアラル海の北部の草原地帯から南下すると,モグーリスターン=ハーン国は衰え,拠点を天山山脈南部のオアシス地帯に移しました。しかし,ハーンの王子たちが各地のオアシスに分立するようになると,一体性はなくなっていきます。
そんな中,〈チンギス=ハン〉の息子〈チャガタイ〉の千人隊に属していた名門バルラス家に属する〈ティムール〉【東京H8[3]】は,若い頃に指揮官として名を上げ,〈トゥグルク=ティムール〉に認められて指揮権を与えられました。しかし,その後反乱を起こしチャガタイ=ハン国東部の「モグーリスターン」の撃退に成功。
サマルカンド【京都H19[2]】【東京H30[3]都市の略図を選ぶ】を拠点にして支配権を確立した〈ティムール〉は,政略結婚で〈チンギス〉家の婿(むこ)となることで,人々から支配者としてふさわしいと納得してもらうことにも成功し,1370年【追H20時期(14世紀)】にティムール朝【セH5時期(13世紀末~14世紀初めではない)】【追H20】【H27京都[2]】を樹立しました。サマルカンドには,宮殿,モスク,バザール(ペルシア語で市場。アラビア語ではスーク【セH21マドラサではない】)などを建設し,交通路を整備して商業活動を奨励しました。彼は都市の活動を重視し,征服先での不要な略奪は行いませんでした。
彼は「モグーリスターン」,ジョチ=ウルス(キプチャク=ハン国,金帳汗国。首都はヴォルガ川【慶文H29】中域のサライ),デリー=スルターン朝のトゥグルク朝,イル=ハン国(フレグ=ウルス) 【セH11地図:13世紀後半の領域を問う】を次々に攻撃し(イル=ハン国は滅亡【セH15 19世紀のロシアが滅ぼしたのではない】),ティムール朝【セH18】を都サマルカンド【セH2ティムール朝の時代に衰えていない】【セH18】を中心に建設していきました。
1402年にはオスマン朝をアナトリア半島のアンカラで破り(アンカラの戦い)ましたが,その後,明遠征を計画し,20万の大軍を出発させました。その中には,モンゴルから亡命してきたチンギス家の王子がおり,明を倒したあかつきには,彼を皇帝にして,モンゴル帝国を復興させようと夢見ていたのでしょう。しかし,シル川中流のオトラルで1405年にあっけなく病気で亡くなってしまいました。王子(〈オルジェイ=テムル〉(位1408~12))はそのままモンゴル高原に向かい,ハーンに即位して明の〈永楽帝〉と対立しました。
〈ティムール〉の死後,〈シャー=ルフ〉(位1409~47)が政権を握り,安定した支配を実現しました。子の〈ウルグ=ベク〉【慶文H29】が後を継ぎました。〈ウルグ=ベク〉自身も優れた学者であり,サマルカンド郊外の天文台で天文観察を行い,1年を「1年間は365日6時間10分8秒」と恐るべき精度で計算,天文表はアラビア語,オスマン語,ラテン語にも翻訳されるほどの精度でした。惑星の運行法則を示したドイツの〈ケプラー〉(1571~1630) 【追H20】の現れるずっと前のことです。
しかし,しだいに各地で王子たちが独立をするようになり,ウズベク人【追H30匈奴とのひっかけ】【慶文H29】の進入も始まっていました。さらに,イラン方面からはテュルク系遊牧民(トゥルクマーン)の建てた黒羊朝(カラコユンル,1375~1468)や白羊朝(アヤコユンル1378~1508)が進入するようになっていき,サマルカンドとヘラートに拠点をもつ王族の間で内紛も勃発。
テュルク系のアクコユンル(白羊朝)の〈ウズン=ハサン〉は,1468年にカラコユンル(黒羊朝)の〈ジャハーン=シャー〉を破り,アナトリア半島に進出しています。
この間ヘラートでは学芸が盛んとなるのですが,1500年にウズベク人【慶文H29】の〈シャイバーニー=ハーン〉(1451~1510)が進入し,ついに滅んでしまいました。
なお,モンゴル帝国により,中国で発明されていた硝石(硝酸カリウム)をもちいた黒色火薬【セH2】は,モンゴル人によって14~15世紀には西アジアやヨーロッパにも伝わります。早速ドイツ人は,15世紀末に,先込火縄式のマスケット銃を開発しています。こうした小銃の導入により,騎士は没落【セH2】していくことになり,大航海時代(注)における軍事的な優位を手に入れました。
また,オスマン帝国も大砲を導入したことで,かつて難攻不落を誇ったビザンツ帝国のコンスタンティノープルがついに陥落することになります(1453)。
(注)「大航海時代」は日本の研究者による呼称。英語ではThe
Age of Discovery(発見の時代)とか,The Age of Exploration(探検の時代)といいます。「発見」という呼び名はヨーロッパ人の視線からみれば,確かに適切な呼び名です。一般的に15世紀初めから17世紀半ばにかけてポルトガル・スペインに始まるアフリカ大陸ギニア湾岸・インド洋沿岸からアジアにかけてのヨーロッパ諸国の海上進出の時代を指し,広くとれば18世紀後半のイギリスによる太平洋探検までの時期を指します。
○1200年~1500年の東アジア・東北アジア
東アジア・東北アジア…現①日本,②台湾,③中華人民共和国,④モンゴル,⑤朝鮮民主主義人民共和国,⑥大韓民国 +ロシア連邦の東部
○1200年~1500年の東北アジア
◆金が滅ぼされ,モンゴル帝国の支配下に入る
モンゴル人は沿海州~オホーツク海へも拡大
中国東北部の沿海州(オホーツク海沿岸部)を本拠地とするツングース諸語系の女真(女直,ジュルチン)は金(1115~1234)を建国していました。金は南宋と和平を結び,金(1125)は沿海州から淮河付近までの広範囲の遊牧民と定住農牧民を支配下におさめていました。
しかし北方のモンゴル高原でモンゴル人が台頭すると,1234年に滅ぼされました。モンゴル人は沿海州を越えて,樺太(サハリン島)にも進出し,この地で台頭していたアイヌと戦っています(北からの蒙古襲来)。“もう一つの元寇”です。
◆ツングース人とヤクート人によるトナカイ遊牧地域が東方に拡大する
北極圏ではトナカイ遊牧地域が東方に拡大へ
さらに北部には古シベリア諸語系の民族が分布し,狩猟採集生活を送っていました。しかし,イェニセイ川やレナ川方面のツングース諸語系(北部ツングース語群)の人々や,テュルク諸語系のヤクート人(サハと自称,現在のロシア連邦サハ共和国の主要民族)が東方に移動し,トナカイの遊牧地域を拡大させていきます。圧迫される形で古シベリア語系の民族の分布は,ユーラシア大陸東端のカムチャツカ半島方面に縮小していきました。
◆極北では現在のエスキモーにつながるチューレ文化が生まれる
エスキモーの祖となるチューレ文化が拡大する
ベーリング海峡近くには,グリーンランドにまでつながるドーセット文化(前800~1000(注1)/1300年)の担い手が生活していましたが,ベーリング海周辺の文化が発達して900~1100年頃にチューレ文化が生まれました。チューレ文化は,鯨骨・石・土づくりの半地下式の住居,アザラシ,セイウチ,クジラ,トナカイ,ホッキョクグマなどの狩猟,銛(精巧な骨歯角製)・弓矢・そり・皮ボート・調理用土器・ランプ皿・磨製のスレート石器が特徴です(注2)。
(注1)ジョン・ヘイウッド,蔵持不三也監訳『世界の民族・国家興亡歴史地図年表』柊風舎,2010,p.88
(注2)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「エスキモー」の項
・1200年~1500年の東アジア
◆「中国」の範囲が北方まで拡大する
女真の金が淮河まで南下し,北宋を滅ぼしたことで,金と南宋がそれぞれ「皇帝」を称して中国本土を分け合うことになります。
その後,モンゴル人の君主〈クビライ=カアン〉が南下し,大都を首都として西方・北方の遊牧民世界を包括する「大元ウルス」(元)を立ち上げ,遊牧民世界の君主号「カアン」とともに漢人の文化圏における“全”世界を包括する君主号である「皇帝」を名乗ります。
元の支配下で,ユーラシア大陸からアフリカ大陸にさえ通ずるに商業活動が活発化し,中国本土の社会は安定化。
しかし1368年の白蓮教徒による紅巾の乱により,漢人を主体とする明(大明)王朝〔明朝〕が建設されます。モンゴル人の大元ウルスは北方のモンゴル高原に政権を移動させますが,大元ウルスのカアンが,南方の中国本土の皇帝と対峙する状況はつづきます。
◆日本,朝鮮では明の成立の影響を受け,新政権が樹立・強化される
その頃日本では,後醍醐天皇(位1318~39)を中心として鎌倉幕府が倒され,その後南北朝の動乱となります。その混乱に乗じて日本近海では密貿易集団の活動が盛んになり,取締りが厳しくなるとが倭寇(わこう) 【中央文H27記】として沿岸から略奪行為をはたらきました。
元に服属していた朝鮮の高麗では,この倭寇討伐で名をあげた〈李成桂〉(りせいけい(イ=ソンゲ) 【セH23】【セ試行 李舜臣とのひっかけ(豊臣秀吉の海軍を撃破していない)】【追H30】【※意外と頻度低い】,1335~1408)が高麗【追H30百済ではない】を倒し,1392年に王(太祖,在位1391~98)に即位し朝鮮王朝(1392~1910) 【追H9「李氏朝鮮」(ママ)】【セH13,セH23】を建てます。首都は漢城【セH13開城ではない,セH22・H27ともに慶州ではない】,現在のソウルです。官学は朱子学【セH13】【セH8陽明学ではない】と定められ,支配層は両班(ヤンバン)【セH13】【追H30】と呼ばれました。
同じ1392年には日本でも,南北朝に分かれていた政権が統一されています。
その後,室町幕府3代将軍〈足利義満〉(あしかがよしみつ1338~1408) 【セH7】が,明から「日本国王」【セH7】に封ぜられて,勘合貿易【セH4鎖国政策をとっていたわけではない,セH7「倭寇の鎮圧に協力することを条件に」か問う,セH10】【セH13ネルチンスク条約の時期ではない】をはじめました。勘合というのは,海賊船ではなく正式な朝貢船であることを確認するために用いられた,割印の押された証明書のことです【セH10民間の対外交易を促進するための政策ではない】。
・1200年~1500年の東アジア 東北アジア
ユーラシア大陸の西の端っこは,北アメリカ大陸に向けて伸びていて,先っぽ付近では南に垂れ下がるようにカムチャツカ半島が伸びています。半島の先には,北海道(蝦夷ヶ島(注))東部に向けて島々が点々としています。
また,北海道の北には樺太(サハリン)島があって,西側のユーラシア大陸との間にはオホーツク(オコーツク)海が広がっています。
気候的には寒冷なので農業に向かず,緯度の高い寒冷地に適応したモンゴロイド人種の人々が,牧畜や漁労を中心とした生活文化を生み出していました。
13世紀になると,北海道(蝦夷ヶ島)から樺太島にかけての地域に,アイヌ人が従来のオホーツク文化(3~13世紀)を継承し,鉄器など日本列島の文化の影響も受けながら,狩猟採集を基盤とする新たな文化を生み出しました。彼らは,本州の和人との間で,場所を決めて干し魚・毛皮を輸出し,鉄器などを輸入する交易を行っていました。
樺太にはニヴフ人が居住していましたが,1268年にアイヌがユーラシア大陸との交易圏の拡大を求めて侵攻します。するとニヴフ人は,当時急成長していたモンゴル帝国に救援を求めたようで,元は14世紀にかけて何度も樺太に侵攻しました。鎌倉政権の日本に対する元寇(蒙古襲来)【セH11「元の中国支配が崩壊するきっかけとなった出来事」ではない】の前に,すでに“北からの元寇”があったのです。
北海道(蝦夷ヶ島)では14世紀に,安藤氏がアイヌやアイヌと混血した日本人の交易グループを支配下に置き,北海道南部の商館で交易を支配しました。14世紀頃から,津軽(現在の青森県)の十三湊(とさみなと)が繁栄をきわめたのには、このような北方世界の交易ブームが背景にあるのです。
(注)えぞがしま。入間田宣夫・斉藤利男・小林真人編『北の内海世界―北奥羽・蝦夷ヶ島と地域諸集団』山川出版社、1999。
・1200年~1500年の東アジア 現①日本
南からの蒙古襲来は,クビライの海上進出の一端
1199年に,征夷大将軍〈源頼朝〉(みなもとのよりとも,,位1192~99)が落馬によるケガにより亡くなりました。18歳の息子〈源頼家〉(よりいえ,,位1202~03)があとを継ぎましたが,父と違って政治的な能力に欠け,御家人(ごけにん)の不満は高まり,1198年に院政を始めていた〈後鳥羽上皇〉(天皇在位1183~98,1180~1239)も対決姿勢を見せ始めました。
そこで,頼家の母〈北条政子〉(1157~1225)は,父であり執権の〈北条時政〉(在職1203~05)とともに〈頼家〉を伊豆に幽閉して,〈頼家〉の弟の〈源実朝〉(さねとも,位1203~19)に跡を継がせ,翌年〈頼家〉は〈北条時政〉により暗殺されました。
1203年に〈北条時政〉が〈実朝〉の後見役(執権)に就任すると,執権は北条氏に世襲されることになりました。1221年〈後鳥羽上皇〉の倒幕計画(承久の乱(じょうきゅうのらん))は〈政子〉が主導権を発揮して対抗したため,失敗しています。
1274年,1281年に2度にわたって元寇【セH12時期「全真教が成立した王朝」のときのものか問う】(モンゴル襲来;蒙古襲来)が実施されました。
1274年の文永の役の前,1266年に大元ウルス〔元〕の〈クビライ=カアン〉は,日本に通交を求める外交文書を送っています。この中で,「兵を用ゆるに至るは,夫れそれたれか好むところぞ。王,それこれを図れ」(兵を用いるなんて,誰が好むだろうか。王は,これを考えていただきたい)という内容に狼狽した日本は,死者を殺害。これが遠征の引き金となります。
しかし,この部分は,高度に整備された文書行政を行っていたモンゴルの定型文(冒頭定型句)の翻訳に過ぎず,日本側が過剰反応したに過ぎないとの解釈も濃厚です(注)。
(注)堤一昭「モンゴル帝国と中国」,桃木至朗・秋田茂『グローバルヒストリーと帝国』大阪大学出版会,2013,p.51。
この過程で,北条氏はますます御家人への影響力を強めていきます。有力御家人との合議ではなく,家督である得宗が執権という職についていようがいまいが,最高権力者となる得宗専制になったのです。
1292年に〈フビライ〉は日本遠征を再度はかりましたが,幕府は鎮西探題を置いて九州における軍事権を強化しました。結局〈フビライ〉の死により,3度目の遠征はありませんでした。
1230年代に,津軽(現在の青森県)の安藤氏の内乱のすきを狙い,蝦夷(えぞ)の大放棄が起きました。北条氏政権はこれに対処できず,武士の間には次の武家の棟梁として〈足利尊氏〉(1305~58,将軍,位1338~58)を望む声が出るようになっています。
1275年には,朝廷の跡継ぎ問題に幕府が介入し,2つの系統の出身者が交互に即位する「両統迭立」(りょうとうてつりつ)が決まりました。幕府によって皇位継承が決められることになったことに,朝廷から幕府に反発する声も出るようになります。〈後醍醐天皇〉は,「両統迭立」の原則に反して,自分の子孫に皇位を継承しようとし,「悪党」を組織化しつつ,倒幕を狙いました。
1321年にから〈後醍醐天皇〉(位1318~39)は親政を始め,大義名分論を説く朱子学(宋学)の影響を受けつつ,「天皇が絶対的権力を握るのは当然だ」と主張しました。彼の皇子〈護良親王〉(1308~35)の呼びかけにより,〈楠木正成〉(?~1336)らの畿内の御家人ではなかった勢力や悪党,寺社が立ち上がりました。1333年には,武家からの支持を集めた〈足利尊氏〉が京都の六波羅探題を攻め,〈新田義貞〉が鎌倉を占領し,幕府は滅びました。
〈足利尊氏〉は,1336年に「建武式目」を制定し,幕府の再興を宣言しました。幕府を京都の室町に置いたので,室町幕府と言います。しかし,のちに従来,寺社や本所が握っていた荘園をどう扱うべきかをめぐり,政権運営をめぐった支配層が分裂し,1350年,全国の武士の間で争いが起きました(観応の擾乱(かんのうのじょうらん))。この乱によって,守護の権限が拡大され,管轄していた国における実権を拡大し,複数の国の守護職について,世襲する者も現れました(守護領国制)。幕府は,これら有力守護の連合体となっていきます。
1350年以降,朝鮮半島南部における倭寇の活動が盛んになっていました。高麗政府はこれに対処しきれず,鎮圧で名を上げた〈李成桂〉(りせいけい,イソンゲ,在位1392~98)が朝鮮王朝を建国することになりました。
倭寇の活動は中国沿岸にもおよび,1368年に明を建国した〈朱元璋〉(位1368~98)は,日本に「なんとかしろ」と使節を送って要求。外交使節は,当時なんとか九州でねばっていた南朝の勢力のところにやってきました。太宰府をおさえていた〈懐良親王〉(後醍醐天皇の皇子,かねよし(かねなが)しんのう,1329~83)の征西府と交渉し,1371年に明の〈洪武帝〉は〈懐良親王〉を日本国王として封じました。「室町幕府」には,倭寇退治をする実力も余裕もないとみなされていたのです。
しかし1372年に征西府は,室町幕府の置いた九州探題の〈今川了俊〉(1325?~1420)により征服されました。すると,明は南朝ではなく北朝に交渉を切り替えました。これに答えたのが〈足利義満〉です。
〈足利義満〉(在職1368~94)は,ライバルを順に蹴落とし,1394年に官制のトップである太政大臣にのぼりつめた上で,出家しました。出家するということは“無所属”になるということで,単なる公家のトップというだけでなく,同時に武家をも従わせるための作戦でした。そんな中,1401年に〈足利義満〉は明の2代皇帝〈建文帝〉(位1383~1402)から「日本国王」に冊封されました。しかし,明で1402年に靖難の役(せいなんのえき,靖難の変)が起き〈永楽帝〉(位1402~24) 【東京H18[3],H24[3]】が即位すると,〈永楽帝〉は「日本国王之印」の金印と勘合(かんごう)を送りました。こうして〈足利義満〉は,明との貿易独占を可能にしたのです。
この期間は日本だけでなくユーラシア大陸全体の交易が活発化していった時代にあたります。海域や大陸の影響を受け、市場経済が発展していった時代なのです。
中国からは12世紀なかば以降,貨幣が輸入されるようになり,13世紀後半には流通するようになりました。日本の幕府や朝廷は貨幣を発行しなかったからです。15世紀に銅線の代わりに,秤量貨幣(はかりで重さを量って価値を決める貨幣のこと)として銀が使われるようになると,貨幣の流入は減っていくことになります。
しかし、日本の武家政権の雲行きは怪しく、1467年に,室町幕府の継承問題に支配者層の内紛が絡み,大規模な大乱が勃発しました。応仁の乱です。
これをきっかけとして,各地に地域的な権力が独立し,戦国大名が出現しました。彼らは自らの支配領域や家臣を「国家」と呼び,独自の法を施行しました。
そんな中、1498年には明応の大地震が本州中央部を襲います。鎌倉の大仏が大津波で破壊、浜名湖が誕生、伊勢の港市である大湊(おおみなと)も壊滅的被害を受けました。
・1200年~1500年のアジア 東アジア 現①日本 南西諸島
琉球では農耕や陶芸の技術が伝わると貝塚時代が終わり,12世紀~15世紀になると各地に按司(あじ)という有力者が現れるようになります。この時代を,砦(とりで)として築かれた様々な形態のグスク(城)にちなみグスク時代と呼びます。
按司は各地に役人(うっち)を派遣し徴税し,農耕の祭祀は姉妹(オナリ)に担当させました。14世紀には複数の按司を支配下に置く世の主(よのぬし)が現れ,沖縄本島の今帰仁(なきじん)の北山,浦添の中山【セH10】,大里の山南の3王国が有力となり,それぞれ1368年に明と冊封関係を結びました。これらを合わせて「三山」の呼び,それぞれの国名は中国から与えられたものです(「山」は島または国という意味)。
その後,1420年代【セH10 時期(15世紀初めか問う)】に中山【セH10】の按司である〈尚巴志〉(しょうはし,1372~1439)が三山を統一をし,琉球王国(第一尚氏王朝) 【セH4,セH10】を建国し,明との朝貢貿易を実現【セH10明との間に対等な外交関係を結んでいたわけではない】。東南アジアから商品を中国に流す中継貿易をおこないました。明は海禁政策をとり自由な貿易を禁じたため,福建省の商人は東南アジア各地に移住し華僑となり,琉球王国にも交易ネットワークを張り巡らせていきました。琉球王国は明への入貢回数ナンバーワン(2位は黎朝,3位はチベットです)[村井1988]。
琉球に来れば,日本からの日本刀,扇,漆器だけでなく,皇帝から琉球王国に授けられた品物や中国商人の品物が手に入るからです。日本の商人は琉球から,中国の生糸や東南アジアの香辛料・香料などを入手しました。
琉球から明には2隻・300人の進貢使が2年に一度派遣され,初めは泉州のち福州に入港します。一行の一部は陸路で北京の皇帝に向かい,旧暦の正月(2月)に皇帝への挨拶とともに貢物(馬,硫黄,ヤコウガイ,タカラガイ,芭蕉布など)を献上すると,代わりに豪華な物品が与えられます。その間,福州では決められた商人との取引が許可されました。また,琉球王国の国王が代わるたびに冊封使(さくほうし)が中国から派遣され,皇帝から正統性が認められました。皇帝にとってみても,琉球王国が東南アジア(琉球は真南蛮(まなばん)と呼んでいました)にせっせと交易品を獲得しに行ってくくれれば,黙っていても東南アジアの産物が届けられるという好都合がありました。14~15世紀の琉球王国にとっての最大の貿易相手国はシャムのアユタヤ朝【セH11:フィリピンではない。14~18世紀にかけて栄えたわけではない】でした。15世紀にはマラッカ王国とも交易をしており,ポルトガルの〈トメ=ピレス〉は16世紀前半の『東方諸国記』で琉球を「レキオ」と表現しています。
このころの琉球では,のち16世紀の日本で三味線(しゃみせん)に発展する三線(さんしん),紅型(びんがた),タイや福建省の醸造法に学んだとされる泡盛(あわもり)といった文化が,日本や東南アジアとの交易関係の中で生まれていきました。日本への貿易は,室町幕府との公式な交易だけではなく,大坂の堺や九州の博多【東京H27[1]指定語句】の商人との間でも行われました。15世紀後半に幕府の権威が弱体すると,前期倭寇が活発化する中,日本人が琉球王国を訪れ交易は続けられました。
1470年に,那覇を中心に交易で力をつけた〈尚円〉(しょうえん,位1470~76)がクーデタを起こして即位し,第二尚氏王統が始まりました。息子の〈尚真〉(しょうしん,位1477~1526)は首里を中心とする体制を整備し,各地の有力者である按司(あじ)を首里に住まわせ,代わりに各地に官僚を派遣して支配を強化しました。按司には領地からの徴税権を認め,按司は琉球王国における貴族層を形成していきました。
・1200年〜1500年のアジア 東アジア ⑤・⑥朝鮮半島
◆高麗はモンゴル人に服属した
高麗は,12世紀前半に女真(女直)人の金に服属し,12世紀末には内紛が勃発し武臣政権が成立していました。13世紀初めには〈崔忠献〉(チェチュンホン;さいちゅうけん,1149~1219)が文臣の支持も得て実権を握り,高麗の王の下で,教定都監の職は彼以降の4代にわたって崔氏により世襲されました。これを「崔氏政権」(武臣政権)といいます。崔氏の私兵であった三別抄(サムベョルチョ;さんべっしょう)は,高麗の正規軍に代わる軍事力となり,この部隊はのちにモンゴル帝国が1231年以降に高麗に断続的に進出した際,その撃退のために江華島に政権が避難した後も最後まで活躍しました。モンゴル撃退を祈念するため木版印刷による『高麗大蔵経』【セH11:活版印刷で刊行されたか問う。活版印刷ではなく木版。大量の版木が現在でも残されています】を作製させたのが〈崔瑀〉(さいう,位1219~49)で,彼の時代の1232年に政権は江華島に移されました。しかし1258~60年にかけての攻撃で武臣政権は崩壊し,高麗の王太子〈倎〉(次代の国王。位1260~74)が〈クビライ〉(フビライ)を直接訪れ,降伏しました【追H21「チンギス=ハン」のときではない】。
これを認めない三別抄は反乱を起こし,国家組織も珍道(チンド;ちんとう)に移され抵抗が続きました。これにより,1274年の〈クビライ〉(フビライ)の第一回日本遠征(弘安の役)の計画は遅延します。1273年にはモンゴルと高麗により平定され,1274年に高麗は〈クビライ〉(フビライ)に服属しました。1279年には高麗軍主体の(東路軍)に加え,旧・南宋の軍主体の(江南軍)が動員され第二回日本遠征が実行されましたが,失敗しています【セH11「2度にわたる日本遠征が失敗した」ことは「元の中国支配が崩壊するきっかけとなった出来事」ではない】。
元の高麗の政治に対する介入は厳しく,歴代の王名には「忠」の一文字が必ず付け加えられました。
◆倭寇の討伐で台頭した朝鮮王朝では,朱子学を国学とし両班の世襲がすすみ,訓民正音が公布された
1351年,高麗で〈共愍王〉が元の命令により即位しました。高麗の王子は,元に滞在する決まりになっていたため,〈共愍王〉は元に滞在していました。しかし,元で紅巾の乱【東京H25[3]】【セH11元の中国支配が崩壊するきっかけとなった出来事か問う,セH12】が勃発したことが伝えられると,これをチャンスとみた〈共愍王〉は,朱子学者を取り立てるなど,反元運動に乗り出しました。結局中国では元が倒され,1368年に明が建てられています。
やがて朝鮮王朝を建国することになる〈李成桂〉の父は,王の反元運動に反応し,挙兵をしました。その遺志を継いだ子の〈李成桂〉は,全州李氏の生まれとされますが,女真(女直)族の出身であるという説もあります。父は女真(女直)人が多く住む地で高麗に仕える軍人だったため,女真(女直)人とのつながりが深かったのです。
〈共愍王〉が亡くなると,元と接近しようとするグループ(向元派)が勢力を伸ばしました。1388年に,明がかつて元の直轄領だった地域を併合しようとしたので,遼東半島地域に〈李成桂〉率いる高麗軍が派遣されました。しかし,彼は鴨緑江の中洲で軍を引き返し,明を倒そうとした政治家たちを攻撃し,実権を握りました。これを威化島回軍といいます。1391年には,科田法を制定し,官僚の力を弱めようとします。当時の官僚は,徴税権付きの大土地(私田)が支給され,国家はそこからは税金がとれないため,問題になっていたのです。
1392年に,高麗最後の王〈恭譲王〉から王位を譲られた高麗の武官〈李成桂〉(太祖(テジョ);りせいけい(イソンゲ),1335~1408)は朝鮮王朝の初代王に即位しました。明は,高麗の臨時の王として〈李成桂〉を認めましたが,正式な冊封関係は結ばれませんでした。しかし,1393年に「朝鮮」という国号が認められると(明から提示されたもう一つの案は「和寧」でした),〈李成桂〉が正式に「高麗」から譲られた王であることが認められたわけです。
朝鮮王朝は,朱子学を国教化し【共通一次 平1:儒教が不振であったわけではない】科挙【セH27】を導入して,官僚制度を整えます。官僚になるルートには,科挙のうち,文人を選ぶ文科と,武人を選ぶ武科があって,文人と武人をあわせた両班(ヤンバン,りょうはん)といわれる支配階級は,王族の次に位置づけられ,朝鮮王朝の時期には特権階級として世襲化されていきました。
中央には,行政の門下省,財政の三司,軍事の中枢院がおかれ,彼ら政府の高官が合議によって政治を行いました。この合議(都評議使司,のち議政府)に加わったメンバーは,建国の際に〈李成桂〉の側に立ち貢献した者たちでしたが,15世紀初めには議政府の権限は大幅に縮小され,〈太宗〉のときには国王の実権が固まりました。
〈太宗〉の後を継いだのが,最盛期の〈世宗〉(せそう(セジョン),位1418~50)です。1403年には鋳字所(ちゅうじしょ)が置かれ,『李朝実録』といった多くの書物が刊行されました。また28字(現在は24字)から成る訓民正音(くんみんせいおん(フンミンジョンウム),ハングルは後の呼称) 【東京H16[3]】を学者に作らせ1443年に制定し,1446年にその原理と用法を説明した同名の教科書を発表しました【共通一次
平1:高麗代ではない】【追H9ハングルとも呼ばれるか・15世紀に作られたか,セH12高麗代ではない】【セH13,セH15高麗代ではない,セH22・H24ともに時期】【慶商A H30記】。訓民正音アルファベットのように表意文字でありながら,漢字のように「へん」や「つくり」のようなパーツがあるので,子音と母音を組み合わせて一つの音節を表すことができます。また,金属活字による出版【セH2唐代の中国で盛んになっていない】もおこなわれました。〈世宗〉の時代には『高麗史』(1451)も編纂され,白磁が生産されました。
1419年には,すでに退位していた〈太宗〉により,倭寇の本拠地と考えられた対馬を攻撃しました。日本では応永の外寇(おうえいのがいこう),朝鮮では己亥東征といいます。
朝鮮の支配階層は,同じ血縁のグループの系図である「族譜」をさかんにつくっていました。一番古いものは1423年のものといわれ,両班たちは,自分の由緒が正しいということを族譜により主張したのです。
両班は15世紀には,中央政界で指導権を握るようになり,地方でも「郷案」という両班の名簿がつくられ,地方における両班の支配権も強まります。「郷案」に記載されていることが,両班の証でした。両班の下には,中人,良人,賤人という身分の差がありました。15〜16世紀に朝鮮では特に全羅・慶尚道で農地開発が進みました。
中央では,中央政界に進出した士林派という新興勢力が,儒教的な道徳政治の実現を訴えるようになりました。
〈申叔舟〉による『海東諸国紀』(1471)は,日本や琉球について地図や国情が説明されています。また,『老松堂日本行録』(成立年未詳)は,応永の外寇(1419)の翌年に日本に使節として同行した〈宋希璟〉(1376~1446)による紀行文です。
・1200年~1500年のアジア 東アジア 現③中国
モンゴル人の進出により宋が滅び,元が建国された。元の下で中国とユーラシア大陸との結びつきが陸上・海上ともに一層強まっていった
白蓮教徒【セH3太平天国ではない,セH12】による紅巾の乱【東京H25[3]】【セH11元の中国支配が崩壊するきっかけとなったか問う,セH12】をきっかけに各地で反乱が起き,1368年,貧しい農民出身の〈朱元璋〉(しゅげんしょう,1328~98)は,長江下流域の金陵(きんりょう,現在の南京) 【セH2臨安ではない】【セH27長安ではない】で皇帝に即位し,国号を明としました。「洪武」という元号を制定し「洪武帝」(洪武帝,ホンウーディ) 【追H9】【セH24】と呼ばれました。死後におくられた名は太祖です。これ以降の元号は,皇帝の在位期間と連動することになりました(一世一元)。皇帝は“時間をも支配する”というわけです
元を支配していたモンゴル人はモンゴル高原に退却し,明からは北元(1371~88) 【追H9】と呼ばれましたが,事実上モンゴル高原で存続し,南方の明と併存する状況が続きました。
なお,1368年には臨済宗の僧侶〈絶海中津〉(夢窓疎石の弟子,1336~1405)が明に渡り,1376年に帰国しています。
◆明は元末の混乱をおさめるため,農村支配を強め,「海禁」をとった
さて,〈朱元璋〉は儒学者をブレーンにつけ,漢人の民族意識を強めることで農村支配を強化しようとしました。しかし,モンゴル人によって活性化した海陸の交易ネットワークをコントロール下に置くのは困難であり,伝統的な朝貢体制を強化して秩序を維持しようとしました。
〈朱元璋〉は君主独裁体制をはかるため,反対勢力にあった官僚を容赦なく処刑し,従来実権をにぎっていた旧貴族勢力を政府から追放するために,中書省を廃止して,中書省の管理下にあった六部を皇帝直属とし,監察も強化しました。明律【セH25】と明令も制定しました。
また,南宋の〈朱熹〉【セH11】が大成した朱子学【セH11陽明学ではない】を官学化して,科挙を整備して,明律・明令をつくらせました。また,倭寇対策のため,民間人の貿易は禁じられ,朝貢貿易のみとなりました。また,民間人(民戸)の戸籍と軍人(軍戸)の戸籍を分けた衛所制【セH17里甲制ではない,セH23宋代の地方小都市ではない】を整備します。
農村では,110戸をあわせて1里とし,そのうちの豊かな10戸を里長戸とし,残りの100戸の甲首戸を10戸ずつにわけました。里長戸と甲首戸には,それぞれ10年1ローテーションで,里長戸から税金をとったり,治安をまもったりする義務を課せられました。これを里甲制【セH17】といい,モンゴルの千戸制(せんこせい)の影響がみられます。さらに「六諭」(りくゆ) 【追H9〈康煕帝〉の発布ではない。四書と明律・明令の総称ではない】【セH14唐の太宗が定めたわけではない,セH17史料・宗法ではない】【追H21秦代ではない】という6ヵ条の教えを,里甲制【追H9】の下の村落における里老人(村の中の長老)にとなえさせ,民衆【追H9六部の官僚ではない】が守るべき道徳をゆきわたらせました。どこにどんな土地があって,誰がどこに住んでいるのかを把握するために,土地台帳の魚鱗図冊【共通一次 平1:人頭税の台帳ではない】【追H30漢の武帝によるものではない】(土地を描いた図柄が魚の鱗に見えることから)と,租税台帳の賦役黄冊【セH27北宋代ではない】(冊子の表紙が黄色であったことから)を整備させました。
また,沿岸地帯で活動していた倭寇をおさえるために,民間の海上貿易を禁止。「貿易がしたいのなら,朝貢せよ。皇帝が冊封(さくほう)し,臣下となれば,貿易を許そう」と,海禁【東京H14[1]指定語句】【H27京都[2]】した上で朝貢を求めました。これに対して日本・室町幕府の〈足利義満〉(任1368~94)は,「冊封されるのはいやだが,貿易するには仕方がない」と,国王に冊封されることで,朝貢の形をとった貿易を認めてもらうことにします。
◆〈永楽帝〉は北京に遷都しモンゴル人と戦うとともに,南海大遠征をおこない海陸の交易ネットワークを支配しようとした
〈洪武帝〉は自分の息子たちを,モンゴル人に対処するために北方の辺境地帯におくって支配させました。現在の北京である北平【法政法H28記】(元のときには大都と呼ばれていた都市を改称したもの)にいた〈燕王〉(朱棣(しゅてい))は,洪武帝の次に即位した〈建文帝〉(位1398~1402)が,辺境の王たちの領土をなくそうとすると,挙兵して南京を占領,内戦が勃発しました。〈燕王〉は北京【セH4「1402年の遷都」について問う】に遷都して皇帝に即位し,〈永楽帝〉(位1402~24) 【東京H24[3]】【H27京都[2]】を称します。この内戦を靖難(せいなん)の変といいます【法政法H28記】。
北京に建設された王宮を紫禁城といい,今後清の滅亡まで使用されました【セH28宋の時代ではない】。皇帝の政務を補佐するため,内閣大学士【セH4尚書省,中書省,軍機処ではない】【法政法H28記】が置かれました【セH12時期「全真教が成立した王朝」のときのものか問う】。
〈永楽帝〉は,『永楽大典』【セH25時期】【追H21時期】(2万2877巻のさまざまな書物関する書物の大全集),科挙のテキストとなった『四書大全』(全36巻の四書の注釈) 【セH13ネルチンスク条約の時期ではない】,唐の『五経正義』を朱子学の立場から書きなおしたテキスト『五経大全』,朱子学の学説を集めた『性理大全』(全70巻)を編纂させることで,思想の統制をはかりました。この思想統制の動きに抵抗したのが,『伝習録』を著して「致良知」【慶文H30朱熹の教えではない】「知行合一」【セH7】を唱えた〈王守仁(陽明)〉(1472~1529) 【セH7】でした。
◆〈永楽帝〉はイスラーム教徒の宦官に大艦隊を編成させ,インド洋一帯に朝貢貿易を迫った
〈鄭和〉の南海大遠征で,インド洋交易が活性化
〈永楽帝〉は,さらに朝貢貿易【セ試行 民間交易ではない】を推進するため,イスラーム教徒の宦官である〈鄭和〉(1371~1434) 【セ試行 時期(明代初頭か)】 【東京H16[3]】に南海大遠征(「西洋下り」ともいいます)を命じました【セH21時期】【セA H30】。
〈鄭和〉の姓は「馬」といい,「ムハンマド」の最初の音から取られた中国のイスラーム教徒に特徴的な姓です。一族は,曽祖父の〈バヤン〉のときに雲南に移住し,元のときには「色目人」としてつかえたとされています。
「明と貿易したければ,朝貢せよ」と呼びかけた鄭和はアフリカ東海岸のスワヒリ文化圏にまで120メートルの巨大な船で到達し【セA H30大西洋には到達していない】,インド洋沿岸の諸国までが明に朝貢使節をおくっています。そりゃ,317隻に2万7800余りの兵士(初めの遠征時)が武装して来航したら,誰だってビビります。〈鄭和〉の乗船した旗艦は4層の甲板を備え全長120m。電車の車両は通常1両の長さが20mほどですから,だいたい6両分の大きさです(〈ヴァスコ=ダ=ガマ〉の船はだいたい26mほどでしたから,その違いは歴然)。
【セH4明の時代の海外への主要な窓口は,上海と香港ではない】
「明との関係を築いたほうが交易に有利」と,多くの国が朝貢に同意しました。海禁を維持したまま,朝貢政策を維持するという点では,対外政策に変わりはありません。大遠征は次の〈宣徳帝〉(位1425~35)のときまで全7回行われ,第1~3回はインドまで,第4~7回は西アジア・東アフリカまで到達しました(注)。アメリカ大陸にも到達していたのでは?という説もありますが,証拠はありません。
とくにムラカ(マラッカ)王国と,琉球(現在の沖縄)は,明から得た商品を周辺諸国に中継する中継貿易で栄華をきわめます。イスラーム教国【セH15】のムラカ(マラッカ)王国【セH15】はすでに14世紀末に成立していましたが,発展したのは〈鄭和〉の遠征がきっかけです。マラッカ海峡は,インド洋と南シナ海をつなぐ要所です。マジャパヒト王国(1293~1527?)も明に朝貢したものの,ムラカ(マラッカ)王国の発展の裏で衰退に向かいました。
(注)第一次(1405~07)→チャンパー,パレンバン,セイロン,カリカット
第二次(1407~1409)→ジャワ,カリカット,コーチン,シャム
第三次(1409~1411)→チャンパー,ジャワ,パレンバン,マラッカ,アチェ,セイロン,コーチン,カリカット
第四次(1412~1415)→アチェ,カリカット,ホルムズ,アフリカ東岸,アデン,ホルムズ
第五次(1416~1419)→セイロン,ホルムズ,アデン,アフリカ東岸
第六次(1421~1422)→スマトラ,アフリカ東岸,ペルシア湾
第七次(1430~1433)→カリカット,ホルムズ,メッカ,アデン
明にとっては朝貢関係を周辺諸国と結べば結ぶほど,それだけ多くの諸国家を従えているということで,政権の権威も高まります。また,明を中心にした秩序が生まれると,インド洋から東アジアにいたるまでの地域交流が活発化していくようになりました。
ただ,これだけのプロジェクトには当然莫大な費用もかかったわけで,次の〈洪熙帝〉〈宣徳帝〉の代に中止されています。
◆〈永楽帝〉は北方のモンゴルにも遠征,一時,オイラト部が強大化し,明を圧迫する
モンゴルの覇権争いの中,オイラトが強大化
また,海だけでなく陸の交流も活発化し,北方の民族は中国との自由な通商を一層求めるようになっていきました。
モンゴル高原では,14世紀末にフビライ家直系が断絶したので,チンギス家の王族が大ハーンの位を継ぎました。モンゴルは,明からは韃靼(だったん)と呼ばれましたが,自らは「大元」と名乗りました。
〈永楽帝〉は,モンゴル高原に遠征【セH15】します。
一方,15世紀半ばにはモンゴル高原北西部のオイラトが〈エセン=ハン〉(?~1454) 【セH13ネルチンスク条約の時期ではない,セH17時期(16世紀ではない)】【H27京都[2]】の指導で強大化。
当時,朝貢の形式をとらなければ中国との貿易ができず,回数なども厳しく決められていました。そこで彼は通商を要求して明の〈正統帝〉(位1435~49,57~64)を北京北西の土木堡(どぼくほ)で捕虜としてしまいました。明は,現在に残る万里(ばんり)の長城を明代後期以降に修復して,北方民族の進入に備えました。長城の総延長は約6000kmにも達します(2003年の神舟5号の宇宙飛行士によると「月から見える」というのは言い過ぎであったようです(⇒1979~現在の東アジア 中国))。
○1200年~1500年のアジア 東南アジア
東南アジア…現在の①ヴェトナム,②フィリピン,③ブルネイ,④東ティモール,⑤インドネシア,⑥シンガポール,⑦マレーシア,⑧カンボジア,⑨ラオス,⑩タイ,⑪ミャンマー
・1200年~1500年の東南アジア 現①ヴェトナム
北ヴェトナムには陳朝がおこり,元を撃退して民族意識を高めたが,漢字の公的使用は続いた
北ヴェトナムでは1225年に内戦を終結させた〈陳太宗〉が陳朝大越国をたてました。しかし,ほどなくしてモンゴル人の元の侵攻が始まります(1251,84,87)。東南アジアを狙ったのは,豊かな交易ネットワークを手に入れるためでした。王族の〈陳興道〉(チャン=フン=ダオ,1228~1300)はこのときに必死に抵抗したことから,現在のヴェトナム人にとっての英雄となっています。陳朝【セH12】では民族意識が高まり漢字を基にした【追H9】チューノム(字喃;チュノム) 【東京H10[3]】【追H9阮朝の時代ではない・漢字をもととしているか問う,セH12】【慶商A H30記】がつくられましたが,公用文における漢字の使用は続き,儒教・仏教が尊重され,科挙も実施されました。
陳朝が滅ぶと,明の占領を撃退した黎利が王朝を開き,明の制度を導入して栄えた
陳朝が1400年に重臣によって滅ぶと,胡朝が建てられました。しかし胡朝は暴政により,明の〈永楽帝〉の進軍を招き,短期間で滅びます。明の直接統治下にあって,陳朝の末裔が1407年に独立を宣言。しかし,明軍の攻撃にあって崩壊します。そんな中,陳朝の末裔をかついで台頭した豪族の〈黎利〉(レ=ロイ)が,陳朝の王族から実権を握って建国したのが黎朝(10世紀の前黎朝と区別して,後黎朝ともいいます,れいちょう,1428~1527,1532~1789) 【セH20カンボジアとのひっかけ】【追H21陳朝とのひっかけ,元を撃退していない】。首都はヴェトナム北部のハノイ。〈黎太祖(レタイト)在位1428~33〉として即位しました。
〈黎利〉は明の制度を導入し,ヴェトナムで現存する最古の法典を編纂し,朱子学を導入。陳朝のときに考案されたチューノム文学もつくられました。
黎朝は1527年に〈莫登庸〉 (ばくとうよう,マク=ダン=ズン,1483~1541,在位) がクーデタ(クーデタとは支配者の間で暴力的に政権が変わること)を起こして中断しました(~1592年に黎朝はハノイを奪い返しました)。1532年に黎朝が復活しますが,実権は鄭氏(北部のハノイ中心。東京(トンキン)といわれます)と阮氏(中部のフエ中心。広南(コーチシナ)といわれます)にうばわれた状態です。やがて阮氏は,南にも勢力圏をすすめてチャンパーを倒し,メコン川の下流をカンボジア人や華人から奪うことに成功しました。
◆南ヴェトナムのチャンパーは元に服属,さらに黎朝の進出を受け分裂した
1282年に元は占城(チャンパー) 【セH18ビルマではない】を海から攻撃しましたが泥沼化し,84年に撤退します。しかし,その後1312年に陳朝は占城を攻撃し,服属させました。
のち,占城は1369年に明に朝貢し,陳朝(1225~1400)との戦闘は続きます。
ヴェトナム北部の陳朝【追H21黎朝とのひっかけ,元を撃退したか問う】では,しだいに陳氏以外の官僚が中央に進出するようになり,1402年に陳朝が胡氏のクーデタにより滅ぶと,胡氏の大越はヴェトナム中部の占城(チャンパー)を奪います。
占城(チャンパー)がこれを明の〈永楽帝〉に訴えると,1406年に明は大越を併合。南海大遠征を実行した〈鄭和〉は,南部のヴィジャヤ近くにある港町クイニョンを,東南アジアへの進出の拠点とすると,占城(チャンパー)は交易ブームに乗って栄えようとししました。
しかし1428年に明は北ヴェトナムから撤退。このタイミングで豪族の〈黎利〉(レロイ)が黎朝大越国を建国し大越は占城のヴィジャヤを攻撃しました。こうして,1471年にヴィジャヤを拠点とする占城は滅んだのです。
その後も,南部にチャム人の港市は栄えますが,最終的に17世紀終わりにヴェトナム中部の広南阮氏の征服を受けるまで存続しています。
・1200年~1500年の東南アジア ⑤インドネシア
◆元の侵入後にマジャパヒト王国が建国されるが,15世紀末にはイスラームの地方政権が広がる
ジャワでは1222年に〈ケン=アロク〉によりクディリ朝(928?929?~1222)が倒され,シンガサリ朝(1222~92)が開かれました。シンガサリはクディリの東部に位置し,どちらも東部ジャワにあります。5代目の〈クルタナガラ〉王(位1268~92)のときに,スマトラ島やバリなど,島しょ部の広範囲に渡って制服活動を行いました。
しかし時おなじくして東南アジアに南下しようとしていたのは,モンゴル人が中国で建国した王朝の元でした【セH26】。元の〈クビライ=ハーン〉(位1271~1294)は,シンガサリ朝の〈クルタナガラ〉王に使節を送りましたが,顔に入れ墨を入れて送り返したことから,〈クビライ〉は激怒。大軍を派遣したときには,すでに〈クルタナガラ〉(?~1292)はクディリ家の末裔(まつえい)と称する〈ジャヤカトワン〉(生没年未詳)の反乱で亡くなっていました(1292年)。〈クルタナガラ〉の娘の夫〈ウィジャヤ〉は,元と協力して〈ジャヤカトワン〉を捉えました。しかし,その後〈ウィジャヤ〉は元軍を攻撃さし,元はジャワ征服を果たせぬまま撤退します。
その後〈ウィジャヤ〉が〈クルタラージャサ〉王(位1293~1309)としてシンガサリの北部に建国したのが,マジャパヒト王国(1293~1478) 【東京H6[1]指定語句,H25[3]】 【共通一次 平1:時期を問う】【セH3時期(7世紀ではない),セH4タイではない,セH5今日のインドネシアの大部分やマレー半島に勢力を伸ばしたか問う,セH6ジャワ島を中心とするヒンドゥー教国だったか問う】【セH18義浄は訪れていない】【中央文H27記】【慶商A H30記】です。14世紀半ばには〈ガジャ=マダ〉(?~1364)が,「世界守護」という名の大宰相という立場で,王国を支配し最盛期に導きます。積極的に対外進出し,その領域は現在のインドネシアの領域にマレー半島(ムラカ(マラッカ)を1377年に占領しています)を足して,ニューギニア島西部を引いた領土とだいたい同じくらいになりました。
マジャパヒト王国は,元と明に朝貢し,西方では同じくヒンドゥー教のヴィジャヤナガル王国(1336~1647)とも通商関係を築きます(⇒1200~1500の南アジア。灌漑農耕が発達して国力を高め,東南アジアへの交易に乗り出していました)。
1400年以降は王位継承を巡る東西の内紛で衰え,15世紀末にはスマトラ島,ジャワ島,ボルネオ島に次々とイスラーム政権が建てられていきました。マジャパヒト王国はジャワ島の中東部とバリ島を残すところとなり,最終的にはバリ島だけに縮小します。現在でもバリ島にヒンドゥー教の信仰が残るのは,このためです。
その後も,イスラーム教の王国として,15世紀末にスマトラ島【セH20地図,H29セイロン島ではない】にアチェ王国(15世紀末~1903) 【セH25地図上の位置を問う・扶南の港ではない】,16世紀末にジャワ島中部にマタラム王国(1580年代末ころ~1755) 【セH15ジャワ最古のヒンドゥー教国かを問う,セH24地域を問う,H29時期と地図上の位置を問う】【追H20元に滅ぼされたか問う(されていない)】【上智法(法律)他H30】が建国されています。マタラム王国は,8世紀にもジャワ人による同名の国があり,古いほうを古マタラム王国と区別する場合があります。
・1200年~1500年の東南アジア 現⑦マレーシア
◆「大交易時代」を背景にイスラーム化がすすみ,15世紀初めに東南アジア初のイスラーム政権マラッカ王国が自立する
マラッカ海峡にイスラーム政権がおこる
13世紀に入り,スマトラ北部の人々がイスラーム教に改宗をはじめるようになりました【追H9地図:伝播経路を問う】。1293年にスマトラ島の港市に風待ちで立ち寄った〈マルコ=ポーロ〉(1254~1324)が言及しているのが,最初の文献です。このサムドラ=パサイ王国(1267~1521)が,イスラーム化の中心で,のちに〈イブン=バットゥータ〉(1304~1368) 【セH3】【セH18宋の時代ではない】や〈鄭和〉(1371~1434)も訪れています。
1368年に成立した明は,海禁【セH15明代を通じて海外への移住が奨励されたわけではない,セH18】政策をとって,貿易を朝貢貿易に限ろうとしました。
ジャワ島から急成長したマジャパヒト王国(1293~1478)は,1377年にスマトラ半島南部,マラッカ海峡に接する港町マラッカ(ムラカ)を占領。1420年には中国の明の〈鄭和〉が南海遠征で立ち寄っています。
マラッカ海峡地域(三仏斉)の諸国は中国とのよりよい交易条件をめぐり,競って朝貢をしました。14世紀後半にジャワとパレンバンや中国人海賊との間で抗争が起きると,パレンバンの王子〈パラメスワラ〉が,マレー半島で建国しました。これが,東南アジア初のイスラーム教【セH2上座仏教ではない】の支配者による港市国家であるムラカ(マラッカ)王国(1402~1511)を建国しました【追H9時期】【セH2時期(15世紀初めか問う)】【セH21イスラームに改宗した時期】。
マラッカ王国は,西方のイスラーム勢力や東方の琉球王国(りゅうきゅうおうこく,1429~1879。同じく明に朝貢していました【セH26・H30】)【セH19
14世紀に衰退していない,セH20時期】とも関係を結び,マジャパヒト王国をしのぐようになっていきます(注)。
マラッカ王国には西方からイスラーム教の宗教指導者が訪れ,東南アジアでの布教の拠点となっていきました。イスラーム教の拡大に一役買ったのは,スーフィー(神秘主義者) 【セH9ウラマーとのひっかけ】の集団です。「儀式や書物を通しての信仰では,神について知ることはできても,実感することができない!」と考えた人々が,さまざまな修行によって神との一体感を得ようとしたのです。イスラーム教では聖職者がいなかったわけですが,各地に「聖者(せいじゃ)」と呼ばれる人々が教団を開いて,この新しいスーフィーを人々に広めていきました。スーフィーは商人の船団に乗って,はるばる東南アジアにも布教しに向かったわけです。
(注)東西海洋交易の中継港となったムラカでは,外国人商人のなかから4人のシャーバンダル(①グジャラート商人,②マラバール,コロマンデル,ベンガル,下ベルマのペグーやパサイの商人の代表者,③パレンバン,ジャワ,カリマンタンのタンジョンプラ,ブルネイ,マルク諸島,ルソンの商人の代表者,④チャンパー,中国,琉球の商人の代表者)がシャーバンダルとよばれる港務長官に任命されました。担当地域から商船がくると,倉庫を割りあて,商品の価格の算定と市場への搬入を仲介したり,商人漢の争いの調停者としても活躍しました。
一方,中国では市舶司とよばれる役所が港と交易の管理・課税にあたり,宋代には,広州・泉州・明州・杭州などに市舶司が設けられて,その関税が国家財政の重要な収入源となっていました。
この時期の国家は商業を盛り上げ,その利益を吸い上げるようになっていることがわかります。
・1200年~1500年の東南アジア 現⑧カンボジア
灌漑施設の荒廃でクメール人の政権は衰えていく
クメール人のアンコール朝は〈ジャヤヴァルマン7世〉(位1181~1218?)のときに都アンコールに王宮アンコール=トムが整備され,灌漑設備の技術も変革されました。
13世紀初めにチャンパーを占領し,チャンパーの王にクメール人を建てていますが,1250年にアンコール地方を洪水が襲い,1260年には灌漑施設を再整備。すでに荒廃していたバライ(貯水池)による灌漑設備の代わりに,1200年頃から各地に石橋ダムと導水路を建設。しかし,次第に泥土が堆積し,灌漑設備の維持は困難になっていったとみられます。
13世紀末期に漢人の王朝宋(960~1126,1127~1276)の〈周達観〉が訪れたころには,灌漑施設は完全には機能していなかったとみられます(『真臘風土記』に記録されています)。
(注)石澤良昭『アンコール・王たちの物語―碑文・発掘成果から読み解く』NHKブックス、2005年,p,233~p.236。
次の〈ジャヤヴァルマン8世〉(位1243~95)は王位継承争いの末に登位。前王が仏教を保護したのに対し,ヒンドゥー教勢力による介入もあって,〈8世〉は仏教弾圧をおこなっています。この過程で,大乗仏教寺院として建てられたバイヨン寺院は,仏像が削り取られたりヒンドゥー教の図像が彫られるなど,ヒンドゥー教寺院への改装が試みられています(注)。
(注) 石澤良昭『アンコールからのメッセージ』山川出版社,2002,p.94。〈ジャヤヴァルマン7世〉が寺院を建立したことで,アンコール朝は衰退に向かったとする〈セデス〉や〈グロリエ〉の説には懐疑的。
13世紀末頃から,交易による繁栄は,カンボジアの外領であったチャオプラヤー川や東北タイのタイ人に移っていきます(注)。
カンボジアは1434年にクメールを放棄。その後,15世紀後半には王家が3分裂しましたが,アユタヤ朝の介入により〈トゥモー〉(1471~1498)が国王となります。
(注) 石澤良昭『アンコールからのメッセージ』山川出版社,2002,p.102。
・1200年~1500年の東南アジア 現⑨ラオス
なお,14世紀中頃に,タイ人の一派ラーオ人がが現在のラオス北部にラーンサーン王国(100万の象という意味)を建国しました。上座仏教を侵攻し,初めルアンパバーン(ルアンプラバン)を,のちにウィエンチャンを首都としました。ルアンパバーンには,今でも多くの仏教寺院が残されています(ただし,この時期に建てられたものに現存しているものはありません。1551年に建立されたワット=シーサケット(1818?に再建)が最古の寺院)。
のち,タイと雲南の勢力が進出したことで分裂し,周辺勢力によってラーンサーン王国の王権が及ぶ地域は縮小していきました。
・1200年~1500年の東南アジア 現⑩タイ
東南アジア大陸部では,タイ人の勢力が従来のモン人やクメール人に代わり強大化した
チャオプラヤー川流域では,クメール王国の〈ジャヤーヴァルマン7世〉(位1181~1218?1220?)が亡くなると,タイ人の活動が盛んになりました。タイ人とは,インドシナ半島北部の山地を中心に,現在はタイとラオスを中心に分布し,合わせて8000万人を超す人口を誇る民族です。山地には13世紀頃からタイ人の諸王国が成立するようになっていましたが,クメール人の支配を脱した最もタイ人の一派は,〈シー=インタラーティット〉(位1238?~70)のもとで1240年頃にスコータイ朝【共通一次 平1:時期を問う】【セH4地域がタイか問う】【セH19時期】【追H21元に滅ぼされたパガン朝とのひっかけ】を建国しました。この一派はシャム人とも呼ばれ,中国語の文献では暹(せん )と記されます。タイ人の中でも,もっとも南に位置する国家です。1251年に都をスコータイを置きました。スコータイから西に伸びる道をたどれば,ベンガル湾に通じる港町に到達できます。
3代目〈ラームカムヘーン〉(位1279~1298年頃)は1292年にタイ語最古の碑文を残し,上座仏教を保護しました。このとき用いられたタイ文字(シャム文字)は,〈ラームカムヘーン〉がクメール文字を参考につくらせたといわれています(もとをたどると,インドのブラーフミー文字です)。王は,1282年には元に服属して独立を維持。
しかし,スコータイ朝は14世紀後半に,あらたに成立したアユタヤ朝の属国になります。
◆アユタヤ朝がおこり,マレー半島やビルマ,カンボジアに拡大し,交易で栄える
1351年に,現在のタイのアユタヤでアユタヤ朝【共通一次 平1:時期を問う】【セH4時期(7世紀ではない),セH11:時期は14~18世紀にかけてか問う。地域はフィリピンではない】【セH14・H18・H21ともに時期】をおこした〈ウートーン〉はもともとスコータイ朝に仕えており,反乱を起こして〈ラーマーティボーディー1世〉(1351~1369)として即位しました。〈鄭和〉の遠征もあり,中国の明との朝貢貿易をおこない,栄えました。1438年にはスコータイ朝の継承者が断絶したため,これを吸収しました。チャオプラヤー川の広大名水田地帯を抱えつつ,交易ルートを押さえることで,王は“商業王”として君臨しました。
15世紀半ばに明が貿易を制限するようになると,アユタヤ朝はマラッカ海峡の支配権を狙い,一時マラッカにも遠征しましたが,イスラーム教【セH15】の信仰されたマラッカ王国【セH19】は西方のイスラーム世界との貿易関係を結び強大化し,海上交易による利益【セH27】でアユタヤ朝【セH11:フィリピンではない。14~18世紀にかけて栄えたか問う】を圧倒していきました。アユタヤ朝のマラッカに対する進出は止まりましたが,マラッカはアユタヤにインドからの商品(綿布など)を,アユタヤはマラッカに米を輸出するという貿易関係は続きました。
・1200年~1500年の東南アジア 現⑪ミャンマー
ビルマでは,イラワジ川中流域にビルマ人がパガン朝(849~1312) 【セH26地域を問う】【追H21「モンゴル」が「進出した」か問う】を建てていました。この王朝はセイロン島から伝わった上座仏教を保護。このころにはすでに,南インドの文字の系統に属し,モン人の文字に由来するビルマ文字(タライン文字)が使われています。
パゴン朝には次第にシャン人が政権に介入するようになり,1287年にはモンゴル人の元の遠征軍に敗れて服属【追H21「モンゴル」が「進出した」か問う】。そのゴタゴタの最中(さなか)に内紛が起こり1299年にパガン朝の王は宰相に殺害されました。宰相によりたてられた新国王は一時的に元を撃退しましたが,1312年には王権がシャン人に譲られ,パガン朝は完全に滅びます【上智(法法律,総人社会,仏西露)H30問題文ちゅうに「元の攻撃を受けて滅亡した」とあるが,直接的原因ではない】。
◆パガン朝が滅亡すると,イラワジ川流域にはシャン人,パガン人,モン人の政権ができる
・イラワジ川上流 →アヴァ朝(1364~1555)をシャン人が建国。
・イラワジ川中流 →タウングー朝(14世紀~1752) 【セH3イギリスにより滅ぼされていない(それはコンバウン朝),セH4タイではない】【追H20 ジャワではない。16世紀成立ではない】【慶文H30記】をパガン朝の残存勢力(ビルマ人)が建国。
・イラワジ川下流より南→ペグー朝(1287~1539)をモン人が主体となって建国(都は1369年以降はペグー)。
・アラカン地方 →アラカン王国(1429~1785)でラカイン人が建国。アラカン地方は現ビルマの最西端に位置します(1979~現在の東南アジア ミャンマー。2010年代後半のロヒンギャ難民危機を参照)。
○1200年~1500年のアジア 南アジア
南アジア…現在の①ブータン,②バングラデシュ,③スリランカ,④モルディブ,⑤インド,⑥パキスタン,⑦ネパール
・1200年~1500年のアジア 南アジア 現③スリランカ
シンハラ人の国家であるコーッテ王国(1412~1597)は、15世紀中頃にはセイロン島全域を支配していました。
なお、北部にはタミル人の国家であるジャフナ王国(1215~1624)が建国されています。
・1200年~1500年のアジア 南アジア 現②バングラデシュ、⑤インド、⑥パキスタン
◆北インドにイスラーム教徒の政権が成立する
この時期には,本格的にイスラーム教徒がインドに政権を建てることになります。イスラーム教への改宗者も増えましたが,強制的改宗というよりも,神秘主義教団(スーフィズム【セH26ジハード,バクティ,シャリーアではない】)の人々スーフィーによる布教活動のおかげです。彼らは,アラビア語の『コーラン(クルアーン)』を形式的に読み,教義を学べばそれでいいという風潮に反発し,信じる“気持ち”を重視しました。彼らは,厳しい修業を通して,神秘的な経験を得ることで,“言葉”や“理屈”ではなく,“直感”的に神と一体化【セH6「神との合一」】できると考えました。「一体化」とはざっくり言えば,“我を忘れる”とか“我を失う”という状態のことです。彼らは,人間が“我を失う”にはどうすればよいか,という技術を持ち合わせていたといえます。
もともと南インドを中心に,“我を忘れて”神の名を唱えたり愛を伝えるバクティ信仰【セH26スーフィズムではない】や,苦しい修行を通して神との一体感を得ようとするヨーガといった伝統的な信仰も盛んだったため,スーフィズムがすんなり受け入れられる土壌があったのです。
〈カビール〉(1440~1518)は,イスラーム教の影響を受け,ヒンドゥー教のカーストによる差別を批判する活動をおこないました。
ゴール朝の〈ムハンマド(ムイズッディーン=ムハンマド)在位1203~1206〉インド西北部に進出し,チャーハマーナ(チャウハーン)朝の〈プリトゥヴィーラージャ〉を中心にラージプート諸王朝が連合して戦いましたが,内部分裂によって敗北し,インドに本格的にイスラーム教徒が進入するきっかけとなりました。
◆奴隷王朝がインドの北部に進出し,デリーに政権を樹立した
インドにイスラーム政権が成立する
1206年に,〈ムハンマド〉が帰路で暗殺されると,武将でマムルークの〈アイバク〉(?~1210) 【セH3バーブルではない】【セH23シャー=ジャハーンではない】はデリー【共通一次 平1:商業・文化の中心はボンベイではない】【セH22】にとどまり,王朝を始めました。
彼の政権を奴隷王朝【共通一次 平1:デリー=スルターン朝の初めか問う】【セH13デリーを首都にした最初のイスラーム王朝かを問う,セH22時期,H29カージャール朝ではない】【追H30ムガル帝国とのひっかけ】と呼び,インド初の本格的なイスラーム教徒による政権となりました。
彼の配下の将軍は,パーラ朝により建設され,インド最後の仏教教学の拠点であったヴィクラマシーラ大学を破壊しています。
彼はデリー南郊に高さ72.5mものクトゥブ=ミナール【セH30】という石塔を建てています。それから,ハルジー朝,トゥグルク朝,サイイド朝【慶文H29】,ロディー朝【早政H30問題文「アフガン系の王朝」】にいたるまで,ガンジス川【早政H30】に注ぐヤムナー川河畔のデリーを首都とするイスラーム政権がつづきます。どれもカイバル峠の向こう側,中央アジアとのつながりが強い政権です。
これをまとめてデリー=スルターン朝【共通一次 平1:この諸王朝はマラータ王国との間で戦争を続けていない】といいます。デリーはガンジス川の支流であるヤムナー川沿いの都市です。
ちなみに,ゴール朝は,1215年に新興のホラズム=シャー朝によって滅ぼされています。アム川下流域のホラズム地方でおこった国で,一時的にシル川からイランにかけて広大な領土を支配しました。
しかしその直後,西征に出ていた〈チンギス=ハン〉によって,ホラズム朝【セH21滅亡時期】はブハラとサマルカンドを占領され,1231年に滅亡します。モンゴル人は,その後もチャガタイ=ハン国やイル=ハン国(フレグ=ウルス)が北インドに進入しています。
1287年のイル=ハン国(フレグ=ウルス)のパンジャーブ進入により混乱した奴隷王朝では,〈ジャラールッディーン〉が即位してハルジー朝が始まりました。次の〈アラーウッディーン〉は,デカン高原に遠征し,南端にいたるまで支配領域を拡大しました。しかし,チャガタイ=ハン国の進入を受け,デリーを包囲される事態となりましたが,1305年にモンゴル軍を倒した〈ギヤースッディーン=トゥグルク〉が,〈アラーウッディーン〉の死後,1320年にトゥグルク朝を創始。彼は南インドのデカン高原支配に失敗し,派遣されていた武将が自立してバフマニー朝となりました。
一方,北方からは,今度はティムール朝の進入を受け,1398年にはデリーに入城し,略奪を受けました。〈ティムール〉は翌年サマルカンドに帰りましたが,彼の派遣した〈ヒズル=ハーン〉はトゥグルク朝を滅ぼして,1414年デリーでサイイド朝【慶文H29】を建てています。この政権の中央アジアとのつながりのつよさがうかがえます。
そのサイイド朝が弱体化したので,1451年にアフガンの諸部族がロディー朝を建てました。
◆ムガル帝国は,モンゴル帝国(大モンゴル国)の“跡継ぎ”国家を自任していた
〈ティムール〉の子孫である〈バーブル〉(1483~1530) 【セ試行 死後にムガル帝国が分裂したわけではない】【セH3奴隷王朝を建てていない,セH12】【セH20・H22時期・ムガル帝国を滅ぼしていない】【H27京都[2]】は,アフガニスタンから来たインドに入って【セH12経路を問う】,1526年,デリー=スルターン朝最後のロディー朝を滅ぼし,ムガル帝国【セH12】【セH22】を建てることになります。
〈バーブル〉は,ティムール朝で使われていたチャガタイ=テュルク語で回想録『バーブル=ナーマ』を著しているように,その建国にはティムール朝の“復興”という意図がありました【セH7インド亜大陸の南端までは統一できていない】。
こういうわけで,「ムガル帝国」という名称はあくまで他称であり,彼ら自身は「インドのティムール朝」と認識していたのです(ムガルとはモンゴルの訛(なま)りで,ティムール朝をモンゴルと混同した呼び名です)。
◆南インドではヴィジャヤナガル王国などのヒンドゥー教の諸王国が,海上交易で栄えました
【セH7バーブルはインド亜大陸の南端までは統一していない】
チャールキヤ朝とチョーラ朝に代わり,13世紀以降の南インドでは,セーヴナ王国,カーカティーヤ王国,パーンディヤ王国,ホイサラ王国が抗争する時代となりました。
そんな中,デリー=スルターン朝のうち,ハルジー朝とトゥグルク朝が,デカン高原まで支配地域を広げましたが,デカン高原ではそこからヒンドゥー教徒が自立し,ヴィジャヤナガル王国(1336~1649) 【セH22・H23ともに世紀を問う】が成立しました。こうして南インドの分裂状況は,一旦終わりました。インド南部は草原が少ないために馬の飼育に適さないため,特産の米と綿布をサファヴィー朝下のホルムズに輸出し,軍馬【東京H17[3]アラビア半島から買い付けられていた軍用の動物を答える難問。答えは「ウマ」】を買い付けていました。
1347年には,トゥグルク朝の武将が自立し,バフマニー王国を建国したため,ヴィジャヤナガル朝との抗争に発展しました。バフマニー朝はその後,ビージャプル王国,ゴールコンダ王国などのいわゆるムスリム5王国が領域内で自立し,分裂していきます。ビージャプル王国,ゴールコンダ王国は,1649年頃ヴィジャヤナガル王国を滅ぼしました。
インド最北部のカシミール地方では,初め仏教,後にヒンドゥー教が信仰され,14世紀にイスラーム教徒の支配下に入りましたが,ヒンドゥー教を保護する王もいました。
・1200年~1500年のアジア 南アジア 現⑦ネパール
ネワール人のマッラ朝(1200~1769)がネパール(カトマンズ)盆地を中心とした地域を初めて統一しました。
ヒマラヤ山脈山中にある標高1300メートルの盆地で,肥沃な土地で米や小麦が生産されました。国王はヒンドゥー教徒でしたが住民には強制せず、ヒンドゥー教と仏教の融合が進みました。
ベンガル地方の民族による侵攻も受けましたが,ヒンドゥー教に基づく法制度を整備した〈ジャヤ=シンティ〉王(1382?~95?)と,次の〈ヤクシャ=マッラ〉(1429?~1482?)の下,最盛期を迎えました。
15世紀後半にマッラ朝の領土は、〈ヤクシャ=マッラ〉王3人の息子に分け与えられ、カトマンズ、パタン、バドガオンに分裂。
3国は互いに競いながら発展し、盆地周辺のチベットやインドとの交易ルートを支配し栄えました。3国の王宮周辺にはダルバール広場が建設され、多くの寺院が建設されました(◆世界文化遺産「カトマンズの谷」、1979。2015年の大地震で被害を受け、修復が進められています)。
ネパールは地理的に,インドからチベットに向かう交易ルートの中継地点としての重要性を持っているとともに,北インドのヒンドゥスタン平原へのイスラームの進出にともなうヒンドゥー教徒たちの移住先にもなっていました。
○1200年~1500年のアジア 西アジア
西アジア…現在の①アフガニスタン,②イラン,③イラク,④クウェート,⑤バーレーン,⑥カタール,⑦アラブ首長国連邦,⑧オマーン,⑨イエメン,⑩サウジアラビア,⑪ヨルダン,⑫イスラエル,⑬パレスチナ,⑭レバノン,⑮シリア,⑯キプロス,⑰トルコ,⑱ジョージア(グルジア),⑲アルメニア,⑳アゼルバイジャン
◆アッバース朝のバグダード政権がモンゴル人により滅ぼされると,インド洋交易の中心は紅海に移った
12世紀になると,東方からモンゴル人が押し寄せてきました。1258年【慶文H29】にはアッバース朝の首都バグダードが占領され,最後のカリフは殺害され,その親族がマムルーク朝の保護を求めました。
アッバース朝【セH16セルジューク朝ではない】を滅ぼしたモンゴル人〈フレグ〉はイランとイラク(都はカスピ海南西のタブリーズ【セH16・H18サライではない】)にイル=ハン国(フレグ=ウルス) 【京都H19[2]】【セH11地図:13世紀後半の領域を問う】を建て,すでに1250年,エジプトのファーティマ朝をクーデタで倒していたマムルーク朝【セH3時期(16世紀初めか問う)】【セH20世紀を問う】と敵対します【セH9アイユーブ朝がマムルークのクーデタにより倒されたか問う】。
イル=ハン国(フレグ=ウルス)は,はじめネストリウス派キリスト教を保護し,〈ラッバーン=バール=サウマ〉(?~1294)を西欧に使節として送り,フランスの〈フィリップ4世〉やローマ教皇〈ニコラウス4世〉(位1288~92)に謁見させています。しかし,〈ガザン=ハン〉(位1295~1304) 【東京H6[1]指定語句】【セH5イル=ハン国の指導層がイスラームに改宗したことを前提とする史料問題(難問である),セH11「歴史書の編纂を命じ」「イスラム教に改宗した」人物の名を問う。フラグ,バトゥ,オゴタイ=ハンではない】【セH13ホラズムを滅ぼしていない,セH16ジョチ=ウルス(キプチャク=ハン国,金帳汗国)ではない】のときに(イル=ハン国が)イスラーム教を国教化しました【セH14,セH21フレグのときではない,H28ガザン=ハンが建国したわけではない】。彼は,遊牧民としてのこだわりを捨て,イスラームの税制を導入して農業を振興したほか,文化も保護した名君です。彼の宰相〈ラシード=アッディーン〉(1247?~1318)は,『旧約聖書』のアダムとイヴから,イスラーム教の時代,そしてモンゴル人のチンギス家までの世界史(『集史』(ジャーミア=ウッタワーリーフ。歴史を集めたもの,という意味) 【セH11】【セH30】) 【追H21『歴史序説(世界史序説)』とのひっかけ】を,イランの言語のペルシア語で書くという壮大なスケールを持った歴史家でもありました。歴史家といえば,北アフリカのチュニスに生まれた〈イブン=ハルドゥーン〉(1332~1406) 【東京H22[3]】【セH3 史料をよみ「14世紀にインドを訪れた人物」を答えるがイブン=バットゥータのことである,セH6スーフィズムを体系化した神学者(ガザーリーなど)ではない,セH8中国の元を訪問していない】【追H21ラシード=アッディーン(ウッディーン)ではない】【※意外と頻度低い】は,『歴史(世界史)序説』【セH26】【追H21『集史』ではない】【中央文H27記】において,人間の歴史には「定住」と「遊牧」の2つの過程がある。物資が乏しいが血気は盛んな沙漠の遊牧民が農耕定住国家を征服→都市型の定住生活に慣れる→新たな遊牧民勢力が都市を襲う→都市型の定住生活に慣れる→新たな遊牧民勢力が都市を襲う…の繰り返しだ,と主張しました。ある集団の「連帯意識」(アサビーヤ)に注目した彼の筆致は,実に客観的です。
エジプトでは1249年にはアイユーブ朝のスルターンが,第6回十字軍の戦時中に急死するとマムルーク軍が後継ぎのスルターンに対して反乱を起こして殺害し,クーデタにより〈アイバク〉(位1250~1257)がスルターンに選ばれマムルーク朝(1250~1517)【セH20世紀を問う】をおこしました。長年に渡る十字軍の過程で,テュルク(トルコ)系のマムルークらの軍隊の力が強まっており,〈アイバク〉が暗殺されると内紛が激化。
そんな中,モンゴル帝国(大モンゴル国;イェケ=モンゴル=ウルス)の〈フラグ〉(フレグ) 【追H9オゴタイ・フビライ・チャガタイではない,セH12ロシアに遠征していない】【セ試行】【セH28ガザン=ハンではない】【H27京都[2]】がバグダードに入城してアッバース朝【セ試行 滅ぼされたか問う。バグダードを都とするか問う】のカリフを殺害し,多数の住民が犠牲となります。
しかし,シリアに進出した〈フラグ〉は〈モンケ=ハーン〉の死の知らせを聞いて退却を始めたため,マムルーク朝はアイン=ジャールートの戦いで勝つことができました。この勝利に貢献した将軍〈バイバルス〉がスルターンの〈クドゥズ〉を暗殺し,1260年にスルターン(位1260~77)として即位しました。1261年にはアッバース朝の末裔(まつえい)〈ムスタンスィル〉をカリフとして保護しています。
その後,メッカやメディナ【セH22】も支配領域に入れて,すでに1258年にモンゴルの〈フレグ〉により滅んだアッバース朝のバグダードに変わり,イスラーム世界の中心地として栄えました。マムルーク朝はのちにカフカース地方のチェルケス人が支配層となり,アラブ人住民を支配しました。
カイロを中心に経済も栄え,アラビア半島南部イエメンの港町アデンで,インド商人から東南アジアやインドの物産を受け取る中継ぎ貿易を行ったカーリミー商人が各地の物産を大量に運び込みました。カーリミー商人は,アデンから紅海に入ると,ナイル川上流に運び,ナイル川を下って下流のアレクサンドリア港【セH12】で,イタリア諸都市(ヴェネツィアやジェノヴァ)に売り渡していたのです。
1世紀のインドに始まったサトウキビからの砂糖の生産は,7世紀頃イラン・イラク,そしてシリア・エジプトに広まっていました。この時期になると,エジプトではサトウキビからの砂糖生産が盛んにななります。甘くておいしいアラブ菓子も,断食明けのエネルギー補給やお祭りなどのために作られるようになりました。
この時期のカイロの繁栄を目の当たりにした人物として,『三大陸周遊記』をあらわした〈イブン=バットゥータ〉(1304~68?69?77?) 【セH3史料のをよみ14世紀にインドを訪れた人物として答える】がいます。彼はモロッコのタンジェ(タンジール)生まれで,アフリカからユーラシア大陸をまたぐ大旅行をした人物です。
また,ファーティマ朝時代に設立された,カイロ【東京H14[3]】【セH27アレクサンドリアではない】のアズハル=モスクにもうけられた学院【東京H14[3]】【セH16ニザーミーヤ学院ではない,セH21】は,はじめはシーア派の中のイスマーイール派の教育機関として設立されましたが,アイユーブ朝の時期にはスンナ派のイスラームの教義研究の名門となり,イスラーム世界各地から学者(ウラマー) 【セH9スルタン,バラモン,スーフィーとのひっかけ】が留学にやって来るようになっています。
◆オスマン帝国はバルカン半島に進出するとともに,ビザンツ帝国を滅ぼした
ビザンツ帝国が滅び,オスマン帝国がバルカンへ
アナトリア半島では,セルジューク朝が地方政権(ルーム=セルジューク朝)を建てて以降,急速にトルコ人の住民が増え,群雄が割拠しました。オスマン帝国(1299~1922) 【セH8時期(1295年の「直後」に建国)】もその一つでした。都はアナトリア半島西部のブルサ【セH8サマルカンドではない】。勢力を固めたのち,バルカン半島に進出し,この地のキリスト教の有力者と戦ったり,同盟を結んだりしながら,領土を拡大していきました。
〈バヤジット1世〉は,アナトリア半島の中部・東部に勢力を広げようとしましたが,1402年に〈ティムール〉(位1370~1405)に敗れて捕虜になり,それ以降,オスマン朝は一時混乱します。
〈ティムール〉の出身であるチャガタイ=ハン国【慶文H29】は,当時,2つの政権に分裂していました。
タリム盆地を含む東部のモグーリスタンにある,東チャガタイ=ハン国と,アム川・シル川流域の西部(マー=ワラー=アンナフル)にある西チャガタイ=ハン国です。〈ティムール〉はこのうちの西チャガタイ=ハン国から自立し,サマルカンド【東京H30[3]都市の略図を選択する】を中心にしてイラン高原やイラクにまで領土を広げた人物です。
その後,〈メフメト2世〉(位1444~46,1451~81) 【Hセ10スレイマン1世とのひっかけ】 【セH23】は,再びバルカン半島への進出をねらいます。すでにビザンツ帝国は,〈アレクシオス1世〉(位1081~1118)の頃から封建化が進み,皇帝は高級軍人や官吏に国有地を管理する権利やその土地からの全収入,さらに軍事権を与える制度(プロノイア制)【セH29】が導入され,皇帝の権力は衰えていました。
また,ペルシア高原方面からは,テュルク系のアクコユンル(白羊朝)が,カラコユンル(黒羊朝)を破り,アナトリア半島に進出。
一方,〈メフメト2世〉はバルカン半島への進出を決意し,1453年にコンスタンティノープルを占領して【セH23スルターンと時期】,ビザンツ帝国を滅ぼし,オスマン帝国の首都としました。これ以降はしだいにイスタンブル(イスタンブール)と呼ばれるようになっていきます(◆世界文化遺産「イスタンブルの歴史地区」、1985)。
かつて〈ユスティニアヌス大帝〉が6世紀にビザンツ様式(ドームとモザイク絵画【セH13,セH25ステンドグラスではない】が特徴)で再建したギリシア正教【セH12(下記の注を参照)】のハギア=ソフィア聖堂には,4本のミナレット(光塔)が加えられ,アヤ=ソフィアと呼ばれるイスラーム教のモスクに転用されました【東京H30[3]「モスクがキリスト教の教会に転用された」ことを答える】【セH17モスクに改修されたかどうかが問われる】。塔にはキリスト教の教会のような鐘はなく,人の声で礼拝時間を知らせます。モスクにはメッカの方向を示すミフラーブという空間,ウラマーが説教をするミンバル(説教壇)が備え付けられました。〈メフメト2世〉は,トプカプ宮殿【セH23チベットのラサではない】の建設も開始しています。
宮殿にはハレムがおかれ,バルカン半島や小アジア,さらにカフカース地方の有力者の娘や女奴隷たちを住まわせ,オスマン帝国における上流階級の文化・芸術の拠点となった一方,のちに政治に介入する女性も現れています。
(注)【セH12】「(1897年に)オスマン帝国で実施された人口調査によると,イスタンブルの人口は90万人であり,その宗教・宗派別割合は次の図のとおり(円グラフ)である」という問い。円グラフには,イスラム教徒(58%),( a )のキリスト教徒(18%),アルメニア教会のキリスト教徒(17%),その他のキリスト教徒(2%),ユダヤ教徒(5%)とあります。( a )に入る語句を「①プロテスタント ②ローマ=カトリック教会 ③ギリシア正教会 ④ネストリウス派」から選ばせるもの。解答は③ギリシア正教会。オスマン帝国による支配以降も,コンスタンティノープル(イスタンブル)はギリシア正教会の拠点であり続けます。
この頃からバルカン半島側に都が置かれ,今までのトルコ系の騎士に代わり,イェニチェリ【セH6スーフィズムを信仰するインド人の教団ではない】という歩兵が重視されるようになっていきます。バルカン半島(のちにエジプト)は間接統治される領土で,総督が派遣され,常備軍としてイェニチェリ【京都H19[2]】【セH21常備軍であることを問う】が用いられました。大音響で有名なオスマン帝国の軍楽隊(メヘテルハーネ)は,吹奏楽のルーツと言われ,ヨーロッパ諸国にも影響を与えました。なお,イェニチェリとして育成するために,バルカン半島の男子を強制的に徴発する制度をデウシルメ(デヴシルメ)【慶文H29】といいます。
あくまで間接的な支配なので,もともといた支配者や統治のしくみは,そのまま残されていました。オスマン朝は,地図上でみると広範囲に領域の色が塗られているので,さぞかし強力な支配を全土に及ぼしていたのだろうと思うかもしれませんが,後に述べる直轄領以外は,実際にはこのような“ゆるやかな支配”によって統治されていたのです。さまざまな言語・民族の人々がひしめき合い,イスラーム教徒ではない人口のほうが多かったのですから,無理もないことです。非ムスリムには,人頭税(ジズヤ)の納入と引き換えに,地域ごとに宗教や言語別に自治組織をつくることが許されていました。
オスマン朝の支配者は,トルコ語を使っていたわけではありません。15世紀までは,アラビア語やペルシア語が用いられていたのです。アラビア語は,宗教すなわち学問の言葉であり,ペルシア語は文学の言葉でもあります。16世紀以降は,トルコ語の一種オスマン語が用いられるようになります。当たり前のことですが,彼らには自分たちが「トルコ人」であるという意識などありません。現在の「トルコ」は,オスマン帝国が崩壊していく中で,アナトリア半島を領土にし,近代化によってヨーロッパ諸国に対抗しようとして建国された国なのです。
・1200年~1500年の西アジア 現⑭レバノン
現在のレバノン山岳部では,独特の信仰を持つマロン派(注1)のキリスト教徒や,ドゥルーズ派(注2)のイスラーム教徒が,有力氏族の指導者の保護下で栄えていました。
(注1)4~5世紀に修道士〈マールーン〉により始められ,12世紀にカトリック教会の首位権を認めたキリスト教の一派です。独自の典礼を用いることから,東方典礼カトリック教会に属する「マロン典礼カトリック教会」とも呼ばれます。
(注2)エジプトのファーティマ朝のカリフ〈ハーキム〉(位996~1021)を死後に神聖視し,彼を「シーア派指導者(イマーム)がお“隠れ”になった」「救世主としてやがて復活する」と考えるシーア派の一派です。
・1200年~1500年の西アジア 現⑯キプロス
キプロス島は十字軍以降はローマ=カトリックの東地中海における拠点となっています。
1192年に、元エルサレム王国であった〈ギー=ド=リュジニャン〉が国王に即位し、1489年までリュニジャン朝となります。
その後、リュニジャン家は断絶し、1489年以降はヴェネツィア共和国領となりました。
・1200年~1500年の西アジア 現⑱アルメニア
アルメニアはモンゴル人の支配下に置かれますが,支配下では反乱も起きています。14世紀以降,キプチャク=ハン国(ジョチ=ウルス)とイル=ハン国(フレグ=ウルス)【セH11地図:13世紀後半の領域を問う】がアゼルバイジャンの草原地帯をめぐって対立。アルメニアは,14世紀半ばにはペストの被害も受けています。
その後,テュルク系の白羊朝,黒羊朝の支配,のちオスマン帝国の支配下に置かれます。1461年にはアルメニア人がオスマン帝国の〈メフメト2世〉により総主教に任命され,「エルメニ=ミッレト」という宗教的な自治組織をつくることが許可されたといいます(注1)。
〈スレイマン1世〉は国内を35の州(エヤレット),下位区分として軍管区(県;サンジャク),郡(カザー)に編成して統治しました。このときアルメニアにはエルズルム=エヤレットが置かれています(注2)。
(注1)中島偉晴・メラニア・バグダサリアヤン編著『アルメニアを知るための65章』明石書店,2009年,p.62
オスマン帝国ではキリスト教やユダヤ教など非イスラーム教徒の宗教的な自治組織がつくられ,「ミッレト」【京都H19[2]】【追H30アッバース朝で認められたものではない】と呼ばれましたが,実態には不明な点も残されています。
(注2)中島偉晴・メラニア・バグダサリアヤン編著『アルメニアを知るための65章』明石書店,2009年,p.63
●1500年~1650年のインド洋海域
インド洋海域…インド領アンダマン諸島・ニコバル諸島、モルディブ、イギリス領インド洋地域、フランス領南方南極地域、マダガスカル、レユニオン、モーリシャス、フランス領マヨット、コモロ
インド洋の島々は,交易ルートの要衝として古くからアラブ商人やインド商人が往来していました。
◯1200年~1500年のアフリカ 東アフリカ
東アフリカ…現在の①エリトリア,②ジブチ,③エチオピア,④ソマリア,⑤ケニア,⑥タンザニア,⑦ブルンジ,⑧ルワンダ,⑨ウガンダ
◆東アフリカのインド洋沿岸では港市国家が栄え,スワヒリ文化圏が生まれました
エチオピア高原では 1270年には,パレスチナの古代イスラエル(ヘブライ)王国の〈ソロモン〉の末裔を自称する〈イクノ=アムラク〉が,ソロモン朝を創始します。
14世紀には孫の〈アムデーシヨン〉が紅海沿岸にあったイスラーム教諸国を併合して,アデン湾からの交易ルートを確保しました。しかし,その領内は分権的でした。
中国の明の皇帝〈永楽帝〉(1360~1424,位1402~24)は,イスラーム教徒の宦官〈鄭和〉(ていわ,1371~1434?)に南海遠征を命じ,その第4回~第6回の遠征では東アフリカにも寄港しています。第5回遠征では諸国がキリン,ダチョウ,シマウマ,ラクダが貢ぎ物として差し出されました(⇒1200~1500の東アジア 中国)。
ほかにも15世紀末にかけ,モガディシュ(現④ソマリアの首都モガディシオ(イタリア語読み)),マリンディ【セH27】(現⑤ケニアの港町。モンバサの北東約100km),モンバサ【セH30】(現⑤ケニア南東部。大陸部分とサンゴ礁島のモンバサ島から成ります)といった港市国家が,イスラーム教徒【セH27】(ペルシア商人やアラブ商人)との交易で栄えます。東アフリカ沿岸にはバントゥー系の言語にアラビア語をとりいれつつ変化したスワヒリ語による文化圏が広がり【セH19インド西海岸のカリカット周辺ではない,セH21】,イスラーム教。アラブ人とペルシア人のほか,ザンジュと呼ばれる黒人が住んでいました。
1497年にはポルトガルの派遣した〈ヴァスコ=ダ=ガマ〉【セ試行 時期(コロンブスがサン=サルバドル島に到達するよりも後のことか問う)】がマリンディに寄港し,ここから現地の水先案内人を雇って,インド南西岸のカリカット【セ試行 オランダの拠点として建設されたのではない】【同志社H30記】【セA H30西インド諸島ではない,アメリカ合衆国の20世紀末の拠点ではない】【※意外と頻度低い】に到着。香辛料の直接取引をねらいました(南アジアはコショウの原産地)【追H9ポルトガルがインド洋に進出した理由を問う。インド亜大陸の支配・イスラム教徒からの聖地の解放・プロテスタントの布教の支援が目的ではない】。
彼は1498年にはモンバサにも寄港していますが,これ以降,ポルトガル勢力とアラブ人勢力との間に,スワヒリ地方の交易拠点をめぐる戦闘が勃発するようになります。
インド洋沿岸は,スワヒリ語の文化圏に含まれています。港市国家キルワ(現⑥タンザニアの首都ダルエスサラームの南300kmのインド洋に浮かぶ島にあります)では,13世紀にアラビア半島南部のイエメン系の支配者がイスラーム王朝を建てました。ここからは中国の貨幣や陶器も見つかっており,インド洋沿岸の交易ネットワークの広さが浮き彫りになっています(遺跡は,南方のソンゴ=ムナラ遺跡とともに世界文化遺産に登録されています)。
モザンビークの港市国家ソファラ(現在のモザンビーク共和国の中東部のノヴァソファラ)からの金や,象牙・奴隷などを取引して栄えます。
◯1200年~1500年の中央アフリカ
中央アフリカ…現在の①チャド,②中央アフリカ,③コンゴ民主共和国,④アンゴラ,⑤コンゴ共和国,⑥ガボン,⑦サントメ=プリンシペ,⑧赤道ギニア,⑨カメルーン
中央アフリカの首長の連合体であるコンゴ王国は,ポルトガルとの交易を始める
コンゴ川(ザイール川。現在の③コンゴ民主共和国南部から北に流れ,⑤コンゴ共和国との国境の一部となりながら西に向かい,ウバンギ川やカサイ川を併せながら大西洋に注ぎます)は,コンゴ盆地における重要な交通路として利用されていました。コンゴ川を用いて,内陸部と大西洋岸の間の遠隔地交易が盛んになるにつれて,14世紀末にバントゥー系のコンゴ人がコンゴ王国を建てました。熱帯雨林のうっそうと茂る中央アフリカのコンゴ盆地では大帝国は建設されにくく,コンゴ王国の実態も各地の首長の連合体のようなものでした。
一方,レコンキスタ(国土回復運動)を終結させたポルトガル王国の商人は1482年にコンゴ王国に来航し,国王〈ンジンガ=ンクウ〉(位1470~1506)をキリスト教に改宗させました。王は1485年にポルトガルの〈マヌエル1世〉(任1495~1521)との間に対等な関係を結び,キリスト教の布教を認めました。その王子〈ムベンバ〉はポルトガルに留学し,のちに〈アフォンソ1世〉(任1506~1543)として国王に就任すると,コンゴのヨーロッパ化を進めていきます。
◯1200年~1500年の西アフリカ
西アフリカ…現在の①ニジェール,②ナイジェリア,③ベナン,④トーゴ,⑤ガーナ,⑥コートジボワール,⑦リベリア,⑧シエラレオネ,⑨ギニア,⑩ギニアビサウ,⑪セネガル,⑫ガンビア,⑬モーリタニア,⑭マリ,⑮ブルキナファソ
◆サハラ沙漠の交易ルートをマンデ人,のちにソンガイ人が掌握した
ニジェール川流域では,1230年頃,イスラーム教に改宗したマンデ人の王〈スンジャータ〉(位1230?~55)がマリ王国【セH3「黒人王国」か問う】を建てました。その支配領域は,西はサハラ沙漠南縁から大西洋に注ぐセネガル川,東はニジェール川の中流域のトゥンブクトゥ【セH3「黄金の都」】【東京H9[3]】(現在の⑭マリ共和国中部の都市)以東にまでおよびました。
トゥンブクトゥからは沙漠の岩塩が,その西のジェンネ(◆世界文化遺産「ジェンネの旧市街」、1988(2016危機遺産))からは森林地帯の金が運ばれて栄えます。
最盛期の〈マンサ=ムーサ〉(マンサは王の意。在位1312~37)は,メッカを500人の奴隷とともに巡礼し,大量の金をロバ40頭で運んだ結果,マムルーク朝の首都カイロ【セH12首都はアレクサンドリアではない】の金相場が下落したほどだったといいます。伝説によれば使節の総数は77000人だったともいわれます。彼は帰国後に,トゥンブクトゥにモスクを建設しました。巡礼は,サハラ沙漠の横断ルートを開拓するためだったとも言われています。1353年には,〈イブン=バットゥータ〉(1304~1368?69?)がマリ王国の首都を訪問し,半年ほど滞在し,その様子を『三大陸周遊記』に報告しています。
1464年に,稲作と漁労に従事していたソンガイ人【共通一次
平1:新大陸の民族ではない】は水軍を組織してニジェール川中流域のガオ(現在の⑭マリ共和国の中等部)を中心にソンガイ帝国【セH3「黒人王国」か問う】を築き,サハラ沙漠の交易ネットワークを支配【セH3】して栄えました。
西アフリカの西端(現在の⑪セネガル)周辺は,ウォロフ人のジョロフ王国(14世紀~16世紀)が,マリ王国やソンガイ帝国との交易で栄えています。
そこへ金の直接取引を目指してやってきたのはポルトガル王国です。1444年にセネガル最西端であるとともにアフリカ大陸の最西端であるカップ=ヴェール岬(これはのちにフランス人により命名されたフランス語で,もともとはポルトガル語でカーボ=ヴェルデ(緑の岬)という名で呼ばれていました(注))にまで到達しています。このときセネガルの若者たちは一度ポルトガルに連行されてポルトガル語通訳として養成され,1455年に再びヴェネツィア商人による探検の際に同行させられました。このヴェネツィア商人の記録によれば,当時セネガル地域にはセネガ王国が栄えていたといいます。
(注)小林了編著『セネガルとカーボベルデを知るための60章』明石書店,2010年,p.19。
○1200年~1500年の北アフリカ
北アフリカ…現在の①エジプト,②スーダン,③南スーダン,④モロッコ,⑤西サハラ,⑥アルジェリア,⑦チュニジア,⑧リビア
現在の①エジプトでは1249年にはアイユーブ朝のスルターンが,第6回十字軍の戦時中に急死するとマムルーク軍が後継ぎのスルターンに対して反乱を起こして殺害し,クーデタにより〈アイバク〉(位1250~1257)がスルターンに選ばれマムルーク朝(1250~1517) 【京都H20[2]】【セH20世紀を問う】を,首都カイロ【セH12アレクサンドリアではない】に築きました。長年に渡る十字軍の過程で,テュルク(トルコ)系のマムルークらの軍隊の力が強まっており,〈アイバク〉が暗殺されると内紛が激化。そんな中,モンゴル帝国の〈フラグ〉(フレグ) 【セH11ガザン=ハンではない,セH12ロシアに遠征していない】【セH28ガザン=ハンではない】【追H21チンギス=ハンではない】がバグダードに入城してアッバース朝カリフを殺害し,多数の住民が犠牲となります。しかし,シリアに進出した〈フラグ〉は〈モンケ=ハーン〉の死の知らせを聞いて退却を始めたため,マムルーク朝はアイン=ジャールートの戦いで勝つことができました。この勝利に貢献した将軍〈バイバルス〉がスルターンの〈クドゥズ〉を暗殺し,1260年にスルターン(位1260~77)として即位しました。1261年にはアッバース朝の末裔(まつえい)〈ムスタンスィル〉をカリフとして保護しています。
その後,聖都であるメッカ(マッカ)やメディナ【セH22】(マディーナ)も保護下に入れ,すでに1258年にモンゴルの〈フレグ〉により滅んでしまったアッバース朝のバグダードに代わって,イスラーム世界の中心地として栄えました。メッカは10世紀以降は〈ムハンマド〉の子孫(シャリーフ)による政権が建っていましたが,周辺のイスラーム政権は権威付けのためにメッカの政権に介入してきました。マムルーク朝もメッカの政権に介入し,イル=ハーン国やインド洋交易で発展していたイエメンのラスール朝(1229~1454)と対立,14世紀末にはメッカを支配下に置くことに成功しました。マムルーク朝のスルターンは,毎年おこなわれるメッカ巡礼(ハッジ)を保護し,カーバ聖殿を覆う布を奉納しています。
カイロを中心に経済も栄え,アラビア半島南部イエメンの港町アデンで,インド商人から東南アジアやインドの物産を受け取る中継ぎ貿易を行ったカーリミー商人が各地の物産を大量に運び込みました。カーリミー商人は,アデンから紅海に入ると,ナイル川上流に運び,ナイル川を下って下流のアレクサンドリア港で,イタリア諸都市(ヴェネツィアやジェノヴァ)に売り渡していたのです。
◆エジプトではサトウキビの生産がさかんとなり,カイロの学院はイスラーム世界の学問の中心地になった
カイロは,サトウキビと学問の都に
1世紀のインドに始まったサトウキビ【セH11原産地はアメリカ大陸ではない。ニューギニア島原産】からの砂糖の生産は,7世紀頃イラン・イラク,そしてシリア・エジプトに広まっていました。この時期になると,エジプトではサトウキビからの砂糖生産が盛んになります。甘くておいしいアラブ菓子も,断食明けのエネルギー補給やお祭りなどのために作られるようになりました。この時期のカイロの繁栄を目の当たりにした人物として,『三大陸周遊記』をあらわした〈イブン=バットゥータ〉(1304~68?69?77?)がいます。彼はモロッコのタンジェ(タンジール)生まれで,アフリカからユーラシア大陸をまたぐ大旅行をした人物です。
また,ファーティマ朝時代に設立された,カイロ【セH27アレクサンドリアではない】のアズハル=モスクに970年にもうけられた学院【セH16ニザーミーヤ学院ではない,セH21】は,はじめはシーア派の中のイスマーイール派の教育機関として設立されましたが,アイユーブ朝の時期にはスンナ派のイスラームの教義研究の名門となり,イスラーム世界各地から学者(ウラマー)が留学にやって来るようになっています。“入学随時・出欠席随意・修業年限なし”がアズハル学院の売り文句。現在では世俗教育もおこなっています。
国家組織はスルターンを頂点とする中央集権的なものでした。スルターンの下で軍事行政・文書財政に携わることができたのはマムルーク軍人(法行政には当初はウラマーが担当した)で,閣僚や地方の州総督・県知事・地方官,軍団が組織されました。即位中のスルターンが保有するマムルークの発言権が高く,スルターンが交替するとマムルーク軍団同士で対立が生まれました。なお,マムルークには奴隷身分から解放されて自由身分となる道もあり,実力次第ではスルターンにまで上り詰めることもできましたが,その地位を世襲することは認められていませんでした。
また,スンナ派の4つの法学派(シャーフィイー派,マーリク派,ハナフィー派,ハンバル派)を公認し,それぞれの大法官(カーディー)を頂点としたウラマー層による中央集権的な法行政組織が設けられました。これにより,スンナ派同士の対立が緩和されウラマー(学者)層に対する支配も強まりました。行財政組織はワズィール(宰相)を頂点とし,スルターンの財政,国家の財政,イクターの監督,文書行政がコントロールされました。
マムルーク朝は1322年にモンゴル人支配層によるイル=ハーン国と和平を結びました。しかし,1347年以降の黒死病(腺ペスト)の大流行によりエジプトでは人口の3分の1が亡くなり,農村も貨幣経済も打撃を受け,マムルーク朝は衰退に向かいました。のち,1382年にカフカース地方のチェルケス人が初めてスルターンに即位し,1390年以降はチェルケス系の王朝がアラブ人住民を支配しました(1390年以前をバフリー=マムルーク朝,以降をブルジー=マムルーク朝として区別する場合もあります)。しかしその後はクーデタが多発し衰退に歯止めがかからず,農村の荒廃によりイクター収入が減少しマムルーク軍も弱体化しスルターンのいうことを聞かなくなっていきました。スルターンは銃砲を用いた黒人奴隷や都市のアウトロー集団により新軍を整備しましたが,そんな中エジプトに迫っていたのはアナトリア半島(小アジア)で急成長を遂げたオスマン帝国でした。
イベリア半島の北部~中央部のカスティーリャ王国と,北西部のアラゴン王国は,イベリア半島を支配していたムワッヒド朝【追H21時期(10世紀ではない)】との戦いを進めていました。現在の④モロッコのマラケシュに都を置くムワッヒド朝では,ベルベル人を中核とした初期の軍事力が衰えをみせ,1212年にラス=ナーヴァス=デ=トローサ(イベリア半島のコルドバ(現在のスペイン)の東)で敗北し,13世紀後半には滅びました。
ムワッヒド朝が滅びると,⑦チュニジアではチュニス総督を務めていたベルベル人の一派ハフス家が独立を宣言し,ハフス朝を建国しました。
また,④モロッコにはやはりベルベル人の一派がマリーン朝を建国。1269年にムワッヒド朝の都マラケシュを占領し,これを滅ぼしてムワッヒド朝の後継国家となりました。
また,⑥アルジェリアにもベルベル人の一派によりザイヤーン朝が建国されました。
⑦リビアは東部(キレナイカ地方)はエジプトの政権,西部(トリポニタニア地方)は西方の政権の影響を受けましたが,アラブ系遊牧民の活動範囲でした。
◆十字軍は失敗に終わり,東方貿易・学問は活発化,教皇権は失墜,国王の権力は高まる
第四回十字軍は,聖地までの物資輸送の資金が足りず,ヴェネツィア商人の資金力や櫂船・帆船を借りて実施されることになりました【セH25ウルバヌス2世ではない】。
時の教皇は,〈インノケンティウス3世〉(位1198~1216) 【慶文H30記】のときで,教会法(カノン法)を根拠として教皇権を強化させていました(教皇権の絶頂【セH25】)。イングランドの〈ジョン王〉,フランスの〈フィリップ2世〉を破門し,「教皇は太陽,皇帝は月」という言葉を残したほどです。
1215年の第四回ラテラノ公会議では,一般人の結婚に対する教会の管理強化,ミサにおける司祭の権利を拡大,ユダヤ人の服装規定といった事項が定められました。
また,都市にのさばる教会に批判的な修道士に対抗し,民衆の支持を得るため,そして各地における情報を収集するために,信徒からの「告解」を聞いて相談にのるスペースが教会に設けられました。
彼の提唱した第四回十字軍はヴェネツィア商人【セH12フィレンツェではない】の商業的な要求に押され,途中で十字軍を「破門」するという事態に。しかしヴェネツィア商人は,コンスタンティノープルを占領し,ここにラテン帝国【京都H20[2]】【Hセ10十字軍がコンスタンティノープルを占領して建てたか問う】【セH16サラディンとは無関係】を建国してしまいます。この王には,先進工業地帯として発達していたフランドル伯〈ボードゥアン9世〉が即位しています(皇帝在位1204~05)。
ヴェネツィアのビザンツ様式のサン=マルコ大聖堂に飾られている四頭の馬の像は,このときにコンスタンティノープルから持って帰ったものです。ビザンツ皇帝は,ニケアに亡命政権を樹立し,生きながらえています(ニケア帝国)。
エジプトを攻撃目標とした第五回十字軍(1218~1221)が失敗に終わると,神聖ローマ帝国〈フリードリヒ2世〉【セH8同名のプロイセン王との混同に注意】に対して教皇が十字軍の実施を要求。〈フリードリヒ2世〉は要請に答えなかったので破門されましたが,破門状態のまま十字軍を開始しました。彼はアイユーブ朝の〈サラディン〉の死後,一族に相続されていたカイロやダマスクス間の対立を利用し,カイロを拠点とするアイユーブ朝のスルターンと提携する交渉を取りまとめ,イェルサレムを一時アイユーブ朝から奪回しています(注)。
(注)〈フリードリヒ2世〉による十字軍(無血十字軍)を,「第六回十字軍」としてカウントする場合もあります(その場合は,それ以降の回次は繰り下がります)。和約によりイェルサレムの統治権を〈フリードリヒ2世〉に譲渡したアイユーブ朝のスルターン〈カーミル〉はその後イスラーム教徒による厳しい批判にさらされ,1239年にはダマスクスの王により奪回されました。ダマスクスは,アイユーブ朝の〈サラーフ=アッディーン〉の一族の者が分割相続していて,半ば独立王国となっていました。
第六回十字軍(1248~49)・七回十字軍(1270)は,フランス王国の〈ルイ9世〉(位1226~70) 【セH18シャルル7世ではない】がファーティマ朝,のちにマムルーク朝【セH20世紀を問う】に対して起こしました。チュニス【セH18イェルサレムではない】に派兵する現実的な案でしたが失敗しました。1249年にはアイユーブ朝のスルターンが戦時中に急死するとマムルーク軍が後継ぎのスルターンに対して反乱を起こして殺害し,クーデタにより〈アイバク〉(位1250~1257)がスルターンに選ばれマムルーク朝(1250~1517)をおこしました。死後に〈ルイ9世〉は教皇により聖人の位につけられています(称号は「聖王」(英語でセントルイス))。
十字軍の主導権が国王に奪われていた一方,教皇も教義の整備に努めていました。しかし,12世紀以降イスラーム世界から伝わっていた古代ギリシアの〈アリストテレス〉の思想は,神を持ち出さずに,この世界について完全に説明しようとしたもので,神の存在によってこの世界の秩序を説明しようとしたキリスト教の神学者にとっては,脅威でありながら魅力も備えていました。
ドミニコ修道会の〈トマス=アクィナス〉(1225?~1274) 【共通一次 平1〈アウグスティヌス〉ではない】【追H9】は,師〈アルベルトゥス=マグヌス〉(1193?1200?~1280)による「キリスト教思想を〈アリストテレス〉の書いたテキストに即して,理性的に理解しなおそうとする」試みを受け継ぎ,〈アリストテレス〉の思想を批判的に読み砕くことでキリスト教の教義を組み立て直していきました【セH12「〈アリストテレス〉哲学がキリスト教の哲学に取り入れられ,これを体系化した書物が著された」か問う】。その成果である『神学大全』(1273) 【共通一次 平1】【追H9】【セH17】【追H21】は,教皇がキリスト教の正しさを説明するときの重要な柱となっていきます。
「…「神の本質」に関しては,第一には,神は存在するか…が考察されなくてはならないであろう。
…次の3つのことがらが問題となる。
第一 神が存在するということは自明的であるか
第二 それは論証の可能なことがらであるか
第三 神は存在するか」
このような形で600あまりの命題と,各命題に対する反論・解答という形式で展開されています(注)。
(注)木村尚三郎編『世界史資料・上』東京法令出版,1977,p.419
一方,〈アクィナス〉を唯名論の立場から〈フランチェスコ〉修道会の〈ドゥンス=スコトゥス〉(1265?~1308)が批判するなど,キリスト教の教義を理性的な立場から疑う動きも出始めていました。
第六回・第七回十字軍以降は組織的な十字軍はなくなり,最終的に1291年に最後の拠点であったアッコン(現在のイスラエルの北部沿岸)が陥落して,終了しました。
十字軍の期間には,イェルサレムに本拠地のあるテンプル騎士団,病院での医療奉仕を重視した聖ヨハネ騎士団【追H30リード文】のように聖地巡礼者を保護したり病院を設立する宗教騎士団【東京H6[3]】が活躍しました。バルト海東岸のケーニヒスベルクを中心とするドイツ騎士団領【セH21レコンキスタと無関係】のように,国家を形成したりキリスト教を東ヨーロッパや北ヨーロッパに布教したりする集団も現れました。
なお,ヨハネ騎士団が十字軍時代に本拠を置いた城が、現在のシリアのクラック=デ=シュヴァリエです(◆世界文化遺産「クラック=デ=シュヴァリエとカラット=サラーフ=アッディーン」、2006(2013年危機遺産)。後者は「サラディンの城」という意味。)。
ヨハネ騎士団は、のちにキプロス島,ロードス島【追H30リード文】,さらにマルタ島に拠点を移しています(◆世界文化遺産「ロドス島の中世都市」、1988。同「バレッタの市街」、1980)。
ドイツ騎士団は,ポーランド王国から沿岸部を奪い,さらにバルト語派の民族とも戦って,バルト海沿岸にドイツ騎士団領を建設しました。これはのちのプロイセンの元になり,さらにはドイツ帝国の元になっていきます。ドイツ騎士団は,15世紀初めまでにバルト海の交易にも従事し,自らを主要産品の“琥珀(コハク)の王”と称していたといいます。しかし,1410年には急成長してきたスラヴ人のポーランドとリトアニアによりタンネンベルクの戦いで敗れ,領土の西半分を奪われ,東部もポーランドの宗主権下に置かれてしまいました。
また,十字軍の失敗によって,言い出しっぺの教皇の権威は低下し,実際に遠征を指揮した国王の力が高まりました。逆に,火砲の導入もあって,騎士は没落に向かいます【セH8「長期にわたる十字軍とその失敗は,彼らの没落の一因となった」か問う】。
それに対応して,13世紀以降は教皇庁の官僚組織が整備され,世俗の国家と張り合うことのできる行政機構を備えたいわゆる“教皇君主制”に発展していきました。今までの公会議や教皇の出した勅令もまとめられるようになり,15世紀半ばまでに『カノン法大全』がまとめられます。
一方,宗教的な情熱のあまり,ユダヤ人に対する迫害も起きています。とくに14世紀中頃に黒死病(ペスト) 【東京H27[1]指定語句】【セH15時期(10世紀半ばではない),セH19時期(12世紀ではない)】が流行した際には,「ユダヤ人が井戸に毒を入れたのだ」などの根も葉もない噂がヨーロッパ中に広まり,特に神聖ローマ帝国内部では虐殺なども起こりました。1462年には,帝国都市だったフランクフルト=アム=マインにユダヤ人居住区(ゲットー)が建設されています。ゲットーとしては,ベーメンのプラハのものも有名です。この頃,ドイツに居住していた多くのユダヤ人はポーランドに移住しました。人々の不安を反映し「死の舞踏」【セH24最後の審判の様子を表したものではない】という,あらゆる階級の人々がガイコツになって踊り狂う絵がさかんに描かれました。当時の人々にとって「死」は身近な存在であり,“メメント=モリ“(死を思え)というラテン語の標語は,現実世界よりも来世を重視する価値観のあらわれでもあります。
地中海における人や物の移動が活発化したことで,東方貿易が盛んになり,イタリア諸都市が発展するきっかけにもなります。現在のクロアチアのアドリア海沿岸にある,赤レンガの美しい町並みで知られるドゥブロヴニクは,古来,東ローマ帝国やヴェネツィア共和国,ハンガリー王国などの支配を受けていましたが,1358年にラグサ共和国として自立し,地中海交易で栄えます(◆世界文化遺産「ドゥブロヴニクの旧市街」、1979(1994範囲拡大))。
イタリアには,古代のギリシアやローマの文献を保存・翻訳していたイスラーム世界やビザンツ帝国の研究成果が伝わり,これらの成果にもとづき,今後「ルネサンス」(文芸復興)が起こっていくことになります。
○1200年~1500年のヨーロッパ 東ヨーロッパ
東ヨーロッパ…現在の①ロシア連邦(旧ソ連),②エストニア,③ラトビア,④リトアニア,⑤ベラルーシ,⑥ウクライナ,⑦モルドバ
・1200年~1500年のヨーロッパ 東ヨーロッパ 現在の①ロシア連邦,⑤ベラルーシ,⑥ウクライナ
キエフ(大)公国(キエフ=ルーシ)がモンゴル人の〈バトゥ〉【京都H20[2]】【セH11ガザン=ハンとのひっかけ,セH12フラグではない】に服属すると,東方のスラヴ人地域にも拡大するようになっていきました。1387年にローマ=カトリックを国教としましたが,スラヴ人の人口が多いため正教会の信仰も認められました。実際,リトアニア大国国の支配層は,スラヴ語派のルーシ語(ベラルーシ語の元)を話しており,貴族の多くがルーシ人(のちのベラルーシ人)でした。
ドイツ騎士団に対抗するため,1386年にリトアニア大公国の〈ヨガイラ〉は,ポーランド王国の娘と結婚します。これにより,ポーランドとリトアニアは同君連合(ヤギェウォ(ヤゲロー)朝【東京H6[3]】)となり,東ヨーロッパの強国,いや,ヨーロッパ最大の強国に発展していきます。最大領土は,黒海沿岸のウクライナにまで及び,1410年にはグルンヴァルト(ドイツ語ではタンネンベルク)の戦いでドイツ騎士団を撃退することにも成功しました。
東スラヴ人のキエフ(大)公国(キエフ=ルーシ)は,13世紀にはモンゴル人の〈バトゥ〉【京都H20[2]】【セH11ガザン=ハンとのひっかけ】が遠征隊の攻撃を受け,約240年にわたるモンゴル人の支配下に置かれることになりました。このモンゴル人による支配期間のことを,ロシアでは「タタールのくびき」といいます(「くびき」(軛;頸木)というのは,車本体から前方に伸びた轅(ながえ)という日本の棒の先に,横にかけられた横木のことで,これを牛の首にひっかけて車をひかせるものです。この時期にロシアは,タタール人(モンゴル人のこと)によって首に横木をかけられて,大変な目にあったのだという比喩(ひゆ)です)。
やがてジョチ=ウルス(キプチャク=ハン国,金帳汗国)のもとで「大公」(ロシアでは「王」を表す称号です)の位を授かったモスクワの〈イヴァン1世〉(位1325~40)のモスクワ大公国は,周囲の諸国からの徴税の請負で発展し,〈ドミトリー=ドンスコイ〉大公(位1359~89)がクリコヴォの戦い(モスクワの南東)でジョチ=ウルス(キプチャク=ハン国,金帳汗国)を破りました。
ジョチ=ウルスは,その後複数のハン国に分裂していきます【セH15ジョチ=ウルス(キプチャク=ハン国は19世紀後半のロシアによって併合されたわけではない)】。
15世紀になると,1453年に東ローマ帝国が滅亡すると,最後の皇帝の姪(めい)〈ゾエ(ソフィア)〉が,モスクワ大公に嫁ぎました。〈イヴァン3世〉【セH20世紀を問う】は,「滅んだ東ローマから,ローマ皇帝の位がわれわれモスクワ大公に移ったのだ!」と主張し,自らをローマ皇帝(ロシア語でツァーリ【セH28】【追H21 13世紀ではない】)と自称しようとしたという説もあります。ただ実際には当時のロシアにおける「ツァーリ」には「王」程度の意味合いしかなく,どちらかというと「ハーン」(モンゴル人(この地域のモンゴル人はタタル人といいます)の君主)の意味が強いものでした(ツァーリ=皇帝ではないのです)。
こうして1480年には,モンゴル人の支配から完全に脱却したのです【セH7ノヴゴロド公国(ママ)ではない】。
彼はイタリア人の建築家を招き,モスクワにギリシア正教の壮麗な聖堂(ウスペンスキー大聖堂)を建てさせました(◆世界文化遺産「モスクワのクレムリンと赤の広場」、1990)。
〈イヴァン3世〉の孫である〈イヴァン4世〉(雷帝,在位1533~84) 【京都H22[2]】【セH6】【セH18聖職者課税問題とは無関係】は,モスクワのウスペンスキー大聖堂で戴冠式をおこない,さらに中央集権化をすすめていきました。1547年には公式にツァーリの称号(「偉大なる君主,全ルーシ,ヴラディミル・モスクワ・ノヴゴロトのツァーリにして大公」)を使い【セH6】,貴族を抑える恐怖政治をおこない権力を拡大させていきました。さらに,南ロシアに残存していたモンゴル人の諸国家(モスクワ東部カザン=ハン国,ヴォルガ川西部のアストラハン=ハン国)を併合し(注),「カザンのツァーリ,アストラハンのツァーリ」という称号も付け加えました。
(注)多民族を含む複数の領域に分かれ,その中に階層的な秩序がつくられている国のことを「帝国」(山本勇造編『帝国の研究―原理・類型・関係』(名古屋大学出版会,2003))と定義することが増えており,それに基づく立場からみると,この時点からロシア人の国家(ロシア国家)は「ロシア帝国」と呼ばれます。
・1200年~1500年のヨーロッパ 東ヨーロッパ ③ラトビア
リトアニアの北部では,ルト語派のラトビア人が,13世紀以降に入植したドイツ人(ドイツ騎士団など)によってキリスト教化されていきました。バルト海方面へのキリスト教世界の拡大運動を北方十字軍ということがあります。ドイツ人の住民は,その後もこの地で影響力を残し続けました。
・1200年~1500年のヨーロッパ 東ヨーロッパ ④リトアニア
バルト海東岸では,バルト語派のリトアニア人を〈ミンダウガス〉(1200?~1263,ポーランド名はミンドーウェ)が1236年に統一し1251年にキリスト教に改宗,1253年にローマ教皇によって国王が与えられました(ただし「王」を名乗ることができたのは,彼の一代限りです)。しかし彼の死後には,リトアニア大公国は西からはドイツ騎士団,東からもドイツ人のリヴォニアによる進出を受けるようになります。
この頃の,エルベ川以東の地域【セH7中世末期以降,領主制の解体と農奴の解放はすすまなかった】では,15世紀以降,西ヨーロッパ向けの穀物生産がおこなわれるようになっていきます。大土地で穀物を栽培するために,自由身分であった農民の自由を奪って農奴とし,グーツヘルシャフト【東京H16[1]指定語句,H26[3]用語の説明記述】【セH19・H21ともに時期】という農場領主制が成立しました。このような大土地所有者は貴族としても君臨し,グーツヘルまたはその俗称でユンカーと言われます。
○1200年~1500年のヨーロッパ 中央ヨーロッパ
中央ヨーロッパ…現在の①ポーランド,②チェコ,③スロヴァキア,④ハンガリー,⑤オーストリア,⑥スイス,⑦ドイツ
◆〈フリードリヒ1世〉は十字軍に参加,〈ハインリヒ5世〉はシチリア島に進出,〈フリードリヒ2世〉は近代的な国家機構を整備しドイツ騎士団による東方植民を支援
「ドイツ人」の拡大運動が,ドイツ王により推進へ
ここでいう「ドイツ」は,ほぼ神聖ローマ帝国【追H30「14世紀中頃~15世紀末の神聖ローマ帝国の版図」を選ぶ問題】の領域のうちイタリアを外した地域のこと。かつての東フランク王国の領域です。
「神聖ローマ帝国」というおおげさな名前を付けた以上,この皇帝はローマのあるイタリアに進出しようと必死。しかし,これがなかなか難しい。ドイツでは皇帝の権力は強くなく,諸侯の独立性も強まっていきました【セH3神聖ローマ帝国の権力が次第に弱体化していき,次第に諸侯の独立性が強まったか党】。
そんな中,中世温暖期を迎えていたヨーロッパでは人口が急増し,外へ外へ拡大する必要が出てきます。
神聖ローマ帝国の領内のドイツ語を話すドイツ人の受け入れ先として,シチリア島が設定されましたがうまくいかず,ついにエルベ川を東に越えた「東方」への植民計画が実行に移されていきます。これが「ドイツ植民運動」です。
さて,神聖ローマ帝国とローマ教皇との間に引き起こされていた叙任権闘争は,1122年に〈ハインリヒ5世〉(位1106~25)と教皇との間に結ばれたヴォルムス協約で,皇帝にドイツの司教に封土を与える権利があることを確認して,一応の決着をみていました。
〈ハインリヒ5世〉と次の〈ロータル3世〉(位1125~37)には子がなかったので,ザリエル朝が断絶し,諸侯の選挙でホーエンシュタウフェン家の〈コンラート3世〉がドイツ王に選ばれました。彼はイタリアへの積極的な進出をしたために,交易の活発化で成長していたイタリア諸都市の反発を招き,ホーエンシュタウフェン家の皇帝派のギベリン(教皇党【セH3】)と,教皇派のヴェルヘン家によるゲルフ(皇帝党【セH3】)との間に内乱が勃発しました。
◆フリードリヒ1世
しかし,〈コンラート3世〉の甥〈フリードリヒ1世〉が,ドイツ王(位1152~90)と神聖ローマ帝国皇帝(位1155~90)に即位しました。彼は通称・赤ヒゲ王(バルバロッサ)と呼ばれ,第三回十字軍に参加したほか,第三回十字軍(1189~92)にも参加しました。しかし,彼も和平を撤回してイタリア政策【セH8】を推進し,1258年に北イタリアを占領しました。それに対し,ミラノを中心にロンバルディア同盟【セH19】が結成されます。彼はローマ法を整備し君主国の体制を強化しようとしましたが,あまりにイタリアに首を突っ込みすぎたため,国内の諸侯の力をじゅうぶんに押さえることはできませんでした【セH8「イタリア政策は,ドイツにおける集権化を促進した」わけではない】。
◆ハインリヒ6世
〈フリードリヒ1世〉の後継〈ハインリヒ6世〉も意欲的な神聖ローマ皇帝でした。まず,ノルマン=シチリア王国の継承者〈コンスタンツァ〉と結婚し,ローマ教皇を南北から圧迫(北の神聖ローマ皇帝 vs ローマ教皇 vs南のノルマン=シチリア王国という構図)。ノルマン人の支配層を弾圧し,シチリア島へのドイツ人の植民をすすめます。
◆フリードリヒ2世【セH8同名のプロイセン王との混同に注意】
しかし〈ハインリヒ6世〉は,若くして死去。シチリア島民の抵抗も起こる中,〈コンスタンツァ〉は孫〈フェデリコ〉とともにシチリア島でローマ教皇〈インノケンティウス3世〉の保護下に置いてもらう戦略をとりました。こうして,アラビア語など多言語に堪能となった〈フェデリコ〉は〈フリードリヒ2世〉(皇帝在位1215~50)【セH27ハプスブルク家ではない】【慶文H29】としてシチリア島を相続し,神聖ローマ皇帝にも選出されます。
彼はシチリアの宮廷で官僚制を整備するとともに,ドイツ騎士団を支援しました(騎士団総長の〈ザルツァ〉(任1209~1239)を支援)。彼らはバルト海沿岸に侵入し,先住のバルト系プルーセン人の支配とキリスト教化に成功します。これがのちのプロイセンのもととなります。その開拓のためにドイツ植民運動が盛り上がっていったわけです。
〈フリードリヒ2世〉はイタリア北部への拡大政策をとったため,諸都市はロンバルディア同盟を結成しています【セH30】。
○1200年~1500年のヨーロッパ 中央ヨーロッパ
◆〈フリードリヒ2世〉は拠点をドイツに置かず,ドイツは領邦国家となっていった
イタリア政策を重視するあまり,ドイツは不統一
さて,〈フリードリヒ2世〉は,地中海の十字路ともいわれるシチリア島で,イスラーム教徒たちとも交遊しながら,幅広い知識を身に着けていた人物です。第五回十字軍では,イスラーム教徒間の争いを利用して,イェルサレムをアイユーブ朝の〈アル=カーミル〉との外交交渉で開城してしまうというスゴ腕の持ち主です。ただイスラーム教徒とべったりしているように見えた彼の行為には批判も多く,教皇から破門された状態での十字軍となりました(「破門十字軍」といいます)。
また,教皇の下で設立されたボローニャ大学に対抗して,ナポリ大学も開いています。
しかし,ドイツを留守にしがちだった〈フリードリヒ2世〉はドイツの領邦の機嫌をとるために,“独立国”であることを事実上認める妥協をしてしまいました(「諸侯の利益のための協定」)。こうして領邦は,皇帝から貨幣の発行権や裁判権などを認められて“領邦国家“へと発展していきました。彼の時代に東方に植民したドイツ騎士団も有力な領邦として,のちのプロイセンにつながっていきます。
ホーエンシュタウフェン朝が断絶すると,皇帝不在の“大空位時代”(1256~73)【セH19】が始まりました。皇帝が短期間即位したこともありましたが,大して力のない諸侯や帝国の外の者であることが多く,不安定な時代でした。
有力諸侯による選挙で神聖ローマ皇帝が決められる仕組みもありましたが,「誰を選挙するか」を巡って難航したのです。「強力なリーダーシップを発揮できる強い人」が神聖ローマ皇帝になってくれればよいかというと,そういうわけでもありません。そんな人が皇帝になってしまったら,「自分の領邦がとりつぶされるかもしれない」と不安になりますし,ローマ=カトリック関係者も「ローマ教皇や教会に口出しをするようになるかもしれない」と危ぶみます。だから,みな強い皇帝を望まないわけです。
1273年には,しかし,当時シチリア王に即位していたアンジュー家の〈カルロ1世〉が,フランスの王を神聖ローマ皇帝に就任させてローマ帝国を復活させようともくろんだことに対して,1273年に「フランス王が神聖ローマ皇帝につくよりは,もっと弱いハプスブルク家【セH26ホーエンツォレルン家ではない】の〈ルドルフ1世〉についてもらったほうがマシだ」ということで,ドイツ王兼神聖ローマ皇帝に就任させることを決定しました。
こういうわけで,当時はまだ弱小諸侯だったハプスブルク家の〈ルドルフ〉(位1273~91)に,“大空位時代”に使い始められた「神聖ローマ皇帝」の称号が与えられました。名前だけで,実質的には“神聖”でも“ローマ”を支配しているわけでもありません。
なお,教皇の取り決めで,ホーエンシュタウフェン朝の支配していたシチリア王国は,シチリア島がイベリア半島北東部のアラゴン王国に,ナポリ王国はフランスのアンジュー家に分割されて相続されました。
○1200年~1500年のヨーロッパ 中央ヨーロッパ
◆ハプスブルク家がオーストリアを拠点に成長する
オーストリアのハプスブルク家が成長 スイスは抵抗
ハプスブルク家【セH4ヤゲウォ朝とのひっかけ】は11世紀にスイス北東部に“鷹の城”(ハビヒツブルク)を築いたことが発祥の弱小貴族でした。しかし,〈ルドルフ1世〉(位1273~91)は,ベーメン(ベーメンはドイツ語。ラテン語ではボヘミア) 【セH13オスマン帝国最盛期の領域には含まれない】の〈オタカル2世〉(当時オーストリア公にも就任していました)からオーストリアを奪うと一気に強大化します。これ以降,ハプスブルク家の拠点はオーストリアとなります。でもオーストリアの獲得により,力がつきすぎてしまったハプスブルク家は,今後は諸侯に敬遠され,ドイツ王位が巡ってこなくなってしまいます。
のちに1291年に,スイスのウリ,シュヴィーツ,ウンターヴァルデンの3州が,神聖ローマ皇帝に抵抗してスイス盟約者同盟を結成しました。これが現在のスイスの起源です。共和政が重んじられるとともに,スイス兵はヨーロッパ諸国で優れた傭兵として知られました。1499年にはシュヴァーベン戦争により,神聖ローマ帝国から実質的に13州が独立しました。
神聖ローマ皇帝の位を巡り,“大空位時代”のような混乱が起きてしまっては,ドイツ地方はフランスやイングランドの進出を受けるおそれもでてきます。そこで,「皇帝を選ぶための手続きや原則が必要だ」という話になりました。
こうして,ルクセンブルク家のベーメン王(位1346~1378)〈カレル1世〉であり、神聖ローマ皇帝に即位していた〈カール4世〉(位1355~1378)【東京H18[3]】【セH23】によって1356年に出されたのが「金印勅書(黄金文書(おうごんもんじょ))」【東京H18[3]】【セH19ユトレヒト条約ではない,H23】【セH8】【追H30】【立教文H28記】です。7人の「選帝侯」が決められ,彼らによって神聖ローマ帝国の皇帝が選挙されることになりました【追H30世襲されることになったわけではない】【セH8諸侯権力を制限し,皇帝権力の優位を確立したわけではない】。
彼はボヘミア王とハンガリー王も兼任し,神聖ローマ帝国の首都はプラハに移されて,「黄金のプラハ」と呼ばれ栄えました。
14世紀にはイングランドの〈ウィクリフ〉や,ベーメンの〈フス〉など,カトリック教会を批判する勢力が支持を集めていました。これに対し,神聖ローマ皇帝の〈ジギスムント〉(位1411~37)は,混乱収拾のためにコンスタンツ公会議(1414~18) 【東京H18[3]】【セH14トリエント公会議(宗教裁判所による異端の取り締まりが強化される中での開催)ではない,セH18ニケア(ニカイア)公会議・メルセン条約・アウクスブルクの和議ではない,H22
15世紀ではない,H26エフェソス公会議ではない,H29トリエント公会議ではない】を開催し,ローマ教皇の権威を確認して教会大分裂(シスマ)(1378~1417) 【セA H30】を終結させるとともに,〈フス〉派【東京H18[3]】【セH29】や〈ウィクリフ〉派【セH2215世紀ではない,セH30】を異端として,〈フス〉を火刑【セH29】としました【セH29試行 図版(クローヴィスの洗礼とのひっかけ)】。このとき祭壇に掲げられていたのは,『聖書』と〈トマス=アクィナス〉(1225?~74) 【共通一次 平1〈アウグスティヌス〉ではない】の『神学大全』【共通一次 平1】でした。
ベーメンにおける〈フス〉【東京H18[3]】の教会批判は,ドイツ人(神聖ローマ帝国)の支配に対する批判の意味も込められており,〈フス〉支持者が反ドイツのフス戦争(1419~36) 【セH17時期・地域,H22】【セA H30時期】を起こします。チェック人の民族運動の側面もあったということです。
1438年の〈アルブレヒト2世〉(ドイツ王在位1438~39)以降,神聖ローマ皇帝は,ハプスブルク家が事実上世襲するようになっていきました【セH26時期,ホーエンツォレルン家ではない】【セH8プロイセン王ではない】。「汝,結婚せよ」の家訓のもと,ハプスブルク家はヨーロッパの名門家系に一族を嫁がせまくり,ヨーロッパの支配階層の乗っ取りを初めていきます。
なお,神聖ローマ皇帝の〈フリードリヒ1世〉と〈2世〉のころ,ドイツ人の東方植民が盛んになりました。12世紀にはブランデンブルク辺境伯領が成立【セH30キエフ大公国とのひっかけ】,13世紀にはドイツ騎士団が成立しました。ブランデンブルク辺境伯は,1356年の金印勅書により選帝侯国となり,神聖ローマ皇帝を選ぶ権利を獲得し,のちに南ドイツの名門によるホーエンツォレルン家の支配を受けるようになりました。
○1200年~1500年のヨーロッパ 中央ヨーロッパ
◆ハプスブルク家が「結婚政策」によりブルゴーニュとスペインを獲得した
さて,ハプスブルク家にはしばらく王位・皇帝位が回ってきませんでしたが,1440年に〈フリードリヒ〉がドイツ王に即位し,さらにローマで神聖ローマ帝国皇帝〈フリードリヒ3世〉に即位すると,勢力を盛り返します。一方,ハプスブルク家は,ヨーロッパの名門貴族と一族を親類関係にする戦略(結婚政策)を開始。〈フリードリヒ〉の息子〈マクシミリアン〉は,当時栄華を極めていたブルゴーニュ公国に接近します。ブルゴーニュ公国はスペインとフランスの干渉に悩まされており,ハプスブルク家と提携する理由がありました。彼は女公〈マリー〉と1477年に結婚し,マリーの父〈シャルル豪胆公〉が戦死するとブルゴーニュ公国を領有しました。
2つ目に,スペイン王女の〈ファナ〉と王子〈ファン〉に,〈マクシミリアン1世〉は息子と娘をそれぞれ嫁がせることに成功。フランスを“挟み撃ち”にしようという意図から実現したのですが,運良く(?)スペイン王家が断絶したことで,1516年にスペインを領有しています。
西スラヴ人のポーランド人,チェック人【セH30ハンガリー人とのひっかけ】,スロヴァキア人は,ローマ=カトリック【慶文H30「10世紀にポーランドが受容したキリスト教の宗派」を問う】に改宗し,ラテン語の文化圏に入っていました。
10世紀初めにピアスト朝を建国したポーランド人は,内紛により分裂していました。そんな中,モンゴル人の〈バトゥ〉【セH11ガザン=ハンとのひっかけ,セH12フラグではない】の侵攻を受けます。ポーランドの諸公国は,ドイツ騎士団とともにモンゴル人を撃退することに成功しましたが,その後東方植民やドイツ騎士団の誘致によってドイツ人の人口は増え続けていきました。移民の労働力を用いて農業生産力は拡大し,ドイツ商人が流入したことから都市も多く建設されました。
ドイツ商人とともにユダヤ人も1264年に〈ボレスワフ敬虔公〉(1221?~1279)によって発布されたカリシュ法により誘致され,移動してきました。ヨーロッパで迫害を受けていたユダヤ人は,ポーランドに来れば信仰が守られることを知り,押し寄せて来たのです。
そんな中,14世紀前半に即位した〈カジミェシュ大王〉(位1333~70)は, ドイツ騎士団に領土を譲ることで争いを避け,ボヘミア王国の拡大を押さえつつ,ウクライナの領土を獲得し,王権を強めることに成功しました。内政では,クラクフに大学を設置(のちのヤギェウォ大学)し,ユダヤ人を手厚く保護しました。
大王の次は,フランスのアンジュー家出身のハンガリー王〈ラヨシュ1世〉(位1370~82)が王位を継承しました。しかし,ドイツ騎士団の勢力は強まる一方。しかも〈ラヨシュ1世〉に男の子の後継ぎがいなかったことが問題になります。
そこで,バルト海沿岸でまとまっていたバルト語系のリトアニア人と手を結び,ドイツ人に対抗しようとする動きが出てきたのです。早速,〈ラヨシュ1世〉の孫娘〈ヤドヴィガ〉(位1384~1399)ポーランド国王にして,リトアニア大公国【慶文H30】の〈ヨガイラ〉と結婚させて,1386年にカトリックに改宗した〈ヨガイラ〉(ポーランド王在位1386~1434)もポーランド国王に即位しました。こうして,リトアニア大公国【セH13】はポーランド王国と合同してヤゲウォ(ヤゲロー)朝【東京H6[3]】【セH4ハノーヴァー・ハプスブルク・ロマノフではない,セH7イヴァン4世は無関係】【セH14ポーランド分割によって滅亡したわけではない,セH30ハノーヴァー朝ではない】のリトアニア=ポーランド王国【セH20世紀を問う】を立ち上げ,共同してドイツ騎士団に立ち向かう体制を整えたのです。
15世紀にはドニエプル側下流域のウクライナ西部にまで進出し,黒海沿岸にいたる大帝国を形成しました。これにより,バルト海と黒海を南北に貫(つらぬ)く交易ルートを支配し,リトアニア=ポーランドは黄金時代を迎えます。1410年には,ポーランドとリトアニアの連合軍がグルンヴァルトの戦い(ドイツ語ではタンネンベルクの戦い)でドイツ騎士団に勝利しています。
・1200年~1500年のヨーロッパ 中央ヨーロッパ 現②・③チェコ、スロヴァキア
ルクセンブルク家のベーメン王(位1346~1378)〈カレル1世〉は、1355年に〈カール4世〉(位1355~1378)【東京H18[3]】【セH23】として神聖ローマ皇帝に即位。彼によって1356年に出されたのが「金印勅書(黄金文書(おうごんもんじょ))」【東京H18[3]】【セH19ユトレヒト条約ではない,H23】【セH8】【追H30】【立教文H28記】です。
7人の「選帝侯」が決められ,彼らによって神聖ローマ帝国の皇帝が選挙されることになりました【追H30世襲されることになったわけではない】【セH8諸侯権力を制限し,皇帝権力の優位を確立したわけではない】。
彼はボヘミア王とハンガリー王も兼任し,神聖ローマ帝国の首都はプラハに移され,プラハの市域は拡大されて新市街が建設され、ヴルタヴァ〔モルダウ〕川の東岸・西岸を結ぶカレル橋や、王宮、1365年に建設されたティーンの聖母聖堂などは、「黄金のプラハ」と讃えられます(◆世界文化遺産「プラハの歴史地区」、1992(2012範囲変更))。
・1200年~1500年のヨーロッパ 中央ヨーロッパ 現④ハンガリー
◆バルカン半島西部ではハンガリー王国が強大化し,オスマン帝国の進出を受ける
フィン=ウゴル語形ウゴル語派のマジャール人は,ウラル山脈周辺のヴォルガ川中下流域を現住地とし,ドナウ川中流域のパンノニア平原で10世紀末にハンガリー王国を建国していましたが、次第にドナウ川上流からはドイツ人の圧迫,下流からはオスマン帝国の圧迫を受けるようになっていきます。
のち,ハンガリー王〈ジギスムント〉の提唱で十字軍が提唱され,フランス,ドイツ,イングランド,イタリア地方の騎士が参加し,オスマン帝国の進出を防ごうとしました。しかし1396年にドナウ川沿いのニコポリス(ブルガリアの北境)【追H21】【慶文H29】で,オスマン帝国の〈バヤジット1世〉(1360?~1403, 位1389~1402)に惨敗し,オスマン帝国のバルカン半島の支配は決定的となりました。
○1200年~1500年のヨーロッパ バルカン半島
バルカン半島…現在の①ルーマニア,②ブルガリア,③マケドニア,④ギリシャ,⑤アルバニア,⑥コソヴォ,⑦モンテネグロ,⑧セルビア,⑨ボスニア=ヘルツェゴヴィナ,⑩クロアチア,⑪スロヴェニア
◆ビザンツ帝国は,第四回十字軍で首都がヴェネツィアに占領され,のちオスマン帝国により滅ぼされる
バルカン半島はオスマン帝国の支配下に置かれる
第四回十字軍のときに,ヴェネツィア共和国【セH12フィレンツェではない】の商人がイェルサレム奪回の目的からそれ,商圏獲得のためにコンスタンティノープルを攻略してしまったため,ビザンツ帝国はニケア帝国(1204~61)という亡命政権を建てました。一方のヴェネツィア主導の十字軍は,コンスタンティノープル【セH30】にラテン帝国【セH29第七回十字軍ではない】を樹立しましたが,その後東ローマ帝国は1261年にジェノヴァの支援を受けてコンスタンティノープルを奪回して復活します。
のち,ハンガリー王〈ジギスムント〉の提唱で十字軍が提唱され,フランス,ドイツ,イングランド,イタリア地方の騎士が参加し,オスマン帝国の進出を防ごうとしました。しかし1396年にドナウ川沿いのニコポリス(ブルガリアの北境)【追H21】【慶文H29】で,オスマン帝国の〈バヤジット1世〉(1360?~1403, 位1389~1402)に惨敗し,オスマン帝国のバルカン半島の支配は決定的となりました。
しかし,1453年にオスマン帝国の〈セリム2世〉の攻撃でコンスタンティノープルが陥落し,東ローマ帝国〔ビザンツ帝国〕(395~1453)は約1000年の歴史に幕を下ろします。
・1200年~1500年のヨーロッパ バルカン半島 現②ブルガリア
◆第二次ブルガリア帝国が勢力を増したが,のちオスマン帝国に敗れる
第二次ブルガリア帝国が拡大する
第二次ブルガリア帝国(1185~1396)は,ビザンツ帝国の影響力を排除しブルガリアを独立教会とするためにローマ教皇〈インノケンティウス3世〉に接近し,1204年に使節を派遣しました。折しも1204年にはコンスタンティノープルが第四次十字軍により陥落し,ブルガリア王はヴェネツィアがコンスタンティノープルで建国したラテン帝国と戦い皇帝〈ボードワン1世〉(位1204~05)を処刑しています。
その後、〈イヴァン=アセン2世〉(位1218~41)の時代が第二次ブルガリア帝国の最盛期で,ハンガリー王女とも結婚し国際的な地位を高めました。しかし,民衆反乱や地方の領主貴族が台頭しモンゴル人の進入も受け,次第に王権は衰えていきます。
のち,ハンガリー王〈ジギスムント〉の提唱で十字軍が提唱され,フランス,ドイツ,イングランド,イタリア地方の騎士が参加し,オスマン帝国の進出を防ごうとしました。しかし1396年にドナウ川沿いのニコポリス(ブルガリアの北境)【追H21】【慶文H29】で,オスマン帝国の〈バヤジット1世〉(1360?~1403, 位1389~1402)に惨敗し,オスマン帝国のバルカン半島の支配は決定的となりました。
・1200年~1500年のヨーロッパ バルカン半島 現④ギリシャ
クレタ島は東ローマ帝国〔ビザンツ帝国〕が支配し、東地中海の拠点としていました。
しかし、1204年に第四回十字軍を主導したヴェネツィア共和国の領土となっています。
・1200年~1500年のヨーロッパ バルカン半島 現⑥コソヴォ、⑦モンテネグロ、⑧セルビア、⑨ボスニア=ヘルツェゴヴィナ
◆バルカン半島南部ではセルビアが強大化したが,オスマン帝国の進出に敗れた
同じく南スラヴ系のセルビア人は,東ローマ帝国の影響下でギリシア正教に改宗していました。1180年以降,〈ステファン=ネマニャ〉(位1168~96)の下でネマニッチ(ネマニャ)朝が勢力を拡大し,セルビア正教会は1219年に独立教会となりました。14世紀前半にはブルガリアとの戦争にも勝利してバルカン半島におけるセルビアの優位を確立。
その後14世紀の〈ステファン=ドゥシャン〉(位1331~55)はビザンツ帝国の法典を基礎に「ドゥシャン法典」を聖帝し,ボスニア=ヘルツェゴヴィナ,アルバニア,マケドニアを含むバルカン半島西半分を領土におさめた「大セルビア王国」を実現し強盛を誇りました。封建領主のプロニア(世襲領地)を保護し支持を取り付け,1346年には首都スコピエ(現在のマケドニアの首都)でセルビア総主教から「セルビア人とギリシア人の皇帝」として戴冠されました。第一次世界大戦(⇒1870~1920年の特集「第一次世界大戦」)のときに,セルビア人青年がボスニアを併合したオーストリアの皇太子夫妻を暗殺したのは,かつてセルビアの領土であったボスニアを併合してしまったオーストリアへの非難を表明する思想に基づいたものです。
しかしバルカン半島には,刻一刻と小アジア(アナトリア半島)からオスマン帝国の勢力が迫っていました。1355年に〈ドゥシャン〉が亡くなると,〈ウロシュ5世〉(位1355~71)の下で諸侯は独立傾向を強めバラバラになっていました。これをチャンスとみたオスマン帝国は1360年にまずアドリアノープル(エディルネ)【京都H19[2]】【慶文H29】を占領し,そこを足がかりに1389年6月15日にコソヴォの戦いでオスマン帝国の〈ムラト1世〉(位1362~89) 【早政H30】を殺害したものの戦闘自体に敗れると,オスマン帝国による支配が始まりました。
・1200年~1500年のヨーロッパ バルカン半島 現⑨ボスニア=ヘルツェゴヴィナ
ボスニア北部・中央部はハンガリーの支配下にありましたが,非常に山がちな地形のため統一的な支配は難しく実権は地方貴族が握っていました。12世紀後半に有力者〈クリン〉(位1180~1204)が首長(バン)となり1377年までハンガリーから事実上独立します。南部のフム地方(現在のヘルツェゴヴィナ)は1326年に北部の首長(バン)の国家が獲得。
この地域はローマ教会と正教会との覇権争いが熾烈でしたが,1347年にバンの〈コトロマニッチ〉はカトリックに改宗しました。
1377年には〈スチェパン=トヴルトコ〉が国王(位1353~91)として即位し「セルビア人,ボスニア人,沿岸地方の王」と名乗り,ボスニア王国となりました。晩年には「ダルマチアおよびクロアチアの王」も名乗り急成長を遂げます。
しかし〈スチェパン=トマシェヴィチ〉(位1461~63)のときにオスマン帝国に敗れ,抵抗が続けられたものの1483年に完全に征服されました。
・1200年~1500年のヨーロッパ バルカン半島 現⑩クロアチア
クロアチアはハンガリーの影響下に置かれていました。
ドゥブロヴニク共和国と改称したアドリア海沿岸の港市国家ラグシウムは,ヴェネツィアとハンガリー王国の宗主権の下で交易活動が認められ西ヨーロッパとバルカン半島を結ぶ拠点として栄え,のちにオスマン帝国の支配下においても交易活動が保障されました(◆世界文化遺産「ドゥブロヴニクの旧市街」、1979(1994範囲拡大))。
アドリア海沿岸のダルマチア地方にある都市ザダルは,第四回十字軍の際にヴェネツィアにより奪われましたが,ハンガリー王にしてクロアチア王である〈ラヨシュ1世〉(位1342~82)がダルマチア地方を奪回しています。
のち,ハンガリー王〈ジギスムント〉の提唱で十字軍が提唱され,フランス,ドイツ,イングランド,イタリア地方の騎士が参加し,オスマン帝国の進出を防ごうとしました。しかし1396年にドナウ川沿いのニコポリス(ブルガリアの北境)【追H21】【慶文H29】で,オスマン帝国の〈バヤジット1世〉(1360?~1403, 位1389~1402)に惨敗し,オスマン帝国のバルカン半島の支配は決定的となりました。
○1200年~1500年のヨーロッパ イベリア半島
イベリア半島…現在の①スペイン,②ポルトガル
◆ポルトガルとカスティーリャ=アラゴンは,レコンキスタの完了後,イタリア諸都市とも連携して地中海を介さない東方貿易ルートを開拓していく
イベリア半島は,12世紀までにマドリードやトレドを含む北半分がキリスト教圏となり,ポルトガル王国,カスティーリャ王国,アラゴン連合王国(アラゴン=カタルーニャ連合王国)が建国されていました。
イベリア半島の北部~中央部のカスティーリャ王国と,北西部のアラゴン王国は,イベリア半島を支配していたムワッヒド朝【追H21時期(10世紀ではない)】との戦いを進めていました。ムワッヒド朝はベルベル人を中核とした初期の軍事力が衰えをみせる中,1212年にキリスト教諸国の同盟軍によってラス=ナーヴァス=デ=トローサ(コルドバの東)で敗北し,13世紀後半には滅びました。
一方,イベリア半島南部のグラナダを都に,1232年に〈ムハンマド1世〉がナスル朝(グラナダ王国) 【東京H24[3]】【立命館H30記】が建国されます。グラナダ【東京H11[1]指定語句】【セH6バルセロナではない,セH8】に残る,アラベスクの美しいイスラーム建築【セH21ロココ様式ではない】のアルハンブラ宮殿【セH6】【セH16コルドバではない】【立命館H30記】【※意外と頻度低い】(アラビア語の「赤い城」(al-Kalat-al
Hamrah)に由来)は,〈ムハンマド1世〉により建造が開始され,ナスル朝の繁栄を今に伝えています【セH28ビザンツ様式ではない】。
しかしカスティーリャ王国による攻撃も受け,王位の継承にモロッコのマリーン朝(1196~1465)が介入して政権は混乱します。しかし,グラナダ朝は14世紀中頃の黒死病(ペスト)の流行や,カスティーリャ王国とアラゴン連合王国の対立にも助けられ,14世紀末にかけて〈ムハンマド5世〉(位1354~59,1362~91)の下で最盛期を迎え,アルハンブラ宮殿も改築されました。
ポルトガル王国は,イベリア半島の他のキリスト教国に先駆けてイスラーム勢力の駆逐に成功していました。1249年に南端の都市ファロをイスラーム政権から取り返した〈アルフォンソ3世〉(位1248~79)のときのことです。レコンキスタの終了後もイスラーム教徒との交易は活発に行われたほか,フランドル地方,イギリス,フランスとの貿易も盛んに行われました。1255年には都がリスボン【セH8】となり,13世紀に開通していたイタリアとフランドルを結ぶ定期航路の中継点として,ポルトとともに商業で栄えました。ポルトガルはイタリアのジェノヴァ商人と提携し,資本,技術,軍事力を導入していきます。ポルトガル王国は,すでに1340年代までには,北東の風に乗りモロッコ沖のカナリア諸島に上陸。しかし,1348年には黒死病【東京H27[1]指定語句】が猛威をふるい,総人口の3分の1が失われました。
〈エンリケ航海王子〉(1394~1460) 【セH15,セH18時期(17世紀ではない)】【追H20フランスではない】は,ジェノヴァ共和国の支援も受けて航海学校を設立し,西アフリカの黄金を直接手に入れるルートを開拓しようとし【セH15アフリカ西海岸の探検を行わせたかを問う】,1427年には大西洋の沖合のアゾレス諸島を発見させています。1450年にはマリ帝国に到達し,彼らに武器や織物などの日用品を提供する代わりに,奴隷や黄金を得るようになっていました。これがヨーロッパ人による,アフリカ人奴隷貿易の初めです。安く仕入れた物を高く売る。この行為がついに,ユーラシア大陸とアフリカ大陸をまたいで(のちに南北アメリカ大陸にまで広がって)展開されるようになります。
さらに,1450年にはポルトガル人が,ジェノヴァ人の投資を受けてカナリア諸島の北のマデイラ諸島で砂糖プランテーションを開始。プランテーションはカナリア諸島でも始まりました。植民地におけるプランテーションの初めです。
こうしてポルトガル王国の都リスボン【セ試行 16世紀前半に世界商業の中心の一つであったか問う】【セH30】【同志社H30記】は繁栄の時代を迎えるのでした。
◆カスティーリャ王国とアラゴン連合王国が統一しスペイン王国となり,レコンキスタを完了させた
カスティーリャ王国は1348年に黒死病(ペスト)の影響を受け,人口減少・物価高騰・領主の没落ににつながり,14世紀後半~15世紀前半にかけた混乱の中でユダヤ教徒に対する迫害(反ユダヤ運動)も発生しました。レコンキスタ真っ最中の頃には,“共通の敵”であるイスラーム教徒の存在があったためユダヤ人とキリスト教徒の関係は良好でしたが,レコンキスタがいよいよ最終局面を向かえる頃となると,キリスト教徒はユダヤ教徒に対する敵視を深めていくようになったのです。1391年にはセビーリャで反ユダヤ運動が起きています。ユダヤ教徒の中にはキリスト教徒に改宗する者(コンベルソ)も現れますが,今度はコンベルソがキリスト教徒から「隠れユダヤ教徒」との汚名を着せられ迫害の対象となりました。
カスティーリャ王国では,14世紀後半に〈エンリケ2世〉(位1369~79)はトラスタマラ朝を創始し,歴代の国王は王権を強化しようとしていきましたが,国内の有力貴族の力は依然として強く,政治的には混乱が続きます。
経済的には,フランドル地方に輸出するために有力者による牧羊業が盛んとなり,造船業も発達しました。輸出産業の担い手となったのは,イタリアのジェノヴァ商人です
アラゴン連合王国も,やはり1348年にペストの猛威を受け,人口減少・物価高騰・領主の没落を招きます。14世紀後半ともなるとオスマン帝国の地中海への進出を受けて経済が衰え,反ユダヤ暴動の影響もあり社会も混乱しました。そんな中,15世紀前半にカスティーリャ王国の摂政が,カタルーニャとアラゴンとバレンシアの代表者らにより国王〈フェルナンド1世〉(位1412~16)に推され,アラゴン連合王国はカスティーリャ王国と同じくトラスタマラ朝となりました。次の〈アルフォンソ5世〉(位1416~58)は,ナポリに宮廷を移してルネサンス文化を保護し,地中海交易を支配しようとしましたが,死後には内紛で混乱をみます。
こうして王権が強化され勢力を増していたカスティーリャ王国と,衰えをみせるようになったアラゴン連合王国の支配層は,「互いに争っていては,イスラーム政権のナスル朝にとって有利になるだけだ」と考え,政治的な統一を目指すようになっていきます。一方ナスル朝では王位継承をめぐる内紛が続き,両国による攻撃も激しさを増していきました。もともと小国であったナスル朝の経済は,ジェノヴァ商人を介する北アフリカやヨーロッパからの輸入頼みであり,ポルトガル王国の南下により北アフリカとの交易がしにくくなり,ジェノヴァ商人が交易から撤退すると大きな打撃を受けることになります。
そんな中,カスティーリャ王国王女〈イサベル〉【セH6イギリスにジプラルタルを譲っていない】【セH15,セH23,セH27】と,アラゴン連合王国王子の〈フェルナンド〉が1469年に結婚。1474年に〈イサベル〉はカスティーリャ女王(位1474~1504)に,〈フェルナンド〉は1479年にアラゴン国王(位1479~1516)に即位し,ポルトガルを除くイベリア半島を共同統治しました。一般に,この2人の王国の領域をもってスペイン王国(モナルキーア=イスパニカ)が成立したとされますが,2王国の立法・行政・司法・軍隊は別々であり,あくまでも2人は別々の国の王の肩書きを維持する複合的な王国でした。
1492年には,スペイン王国がイベリア半島におけるイスラーム教徒による最後【セH16イベリア半島最後の政権かを問う】の政権であるナスル朝(グラナダ王国) 【セH3ムラービト朝ではない】【セH16,セH21時期】の首都グラナダを陥落させ,最後の〈ムハンマド12世〉が北アフリカに逃亡すると,足掛け800年近くかかったレコンキスタがようやく幕を閉じました。
レコンキスタの完了した1492年には,〈イサベル〉と〈フェルナンド〉の“カトリック両王”は,ユダヤ教徒追放令を発布。スペイン【セH13フランスではない】を追放されたユダヤ人やイスラーム教徒のなかには,オスマン帝国領内に移住した者もいました。なかにはキリスト教徒に改宗したり,改宗したように偽装したりする者もいました(キリスト教に改宗したイスラーム教徒のことをモリスコといい,改宗ユダヤ人のことをコンベルソといいます)。こうしたユダヤ教徒に対する迫害は14世紀後半以降高まっていた反ユダヤ運動運動の延長線上にあるものです。
〈イサベル〉と〈フェルナンド〉は1496年に教皇から“カトリック両王”の称号を授けられ,言葉や制度は別々でありながらも宗教的なまとまりは強化されました。言語に関して言えば,人文主義者の〈ネブリーハ〉が当時としては画期的な文法書である『カスティーリャ語文法』を記し,以降のポルトガルを除くイベリア半島ではカスティーリャ語が“スペイン”の言語としての地位を獲得していくこととなります。
◆ポルトガルはレコンキスタの完了後,東方交易の新ルート開拓のため,西アフリカを南下した
スペイン王国に先んじてレコンキスタを終えたポルトガル王国は,サハラ沙漠を通過せずに塩金貿易を,地中海を通過せずに東方交易をするため,西アフリカ沿岸への探検を開始しました。
その過程でポルトガル人は,1450年代に入るとキプロス島などの地中海で行っていたプランテーション(大農園制。広い土地で多くの労働力を使って,少ない種類にしぼって商品作物を大量生産し,市場に輸出するための農園)を,モロッコの東方のマデイラ諸島に導入し,サトウキビの生産を開始しました。
その労働力として連行されたのが,アフリカ大陸(ギニア湾岸)の住民です。サトウキビの植え付けと刈り取りには,労働力が大量に必要になるのです。こうして,ヨーロッパ人によるギニア湾沿岸(西アフリカから中央アフリカにかけて)から大西洋を超える黒人奴隷貿易【セH24】が本格化していきます。産業革命(工業化)以前の社会では,奴隷と家畜は,重要な“動力源”だったのです。
ポルトガルはその後,アフリカ大陸の西端のヴェルデ岬沖に浮かぶ,カーボヴェルデでも同じようにプランテーションと奴隷貿易を行いました。また,スペインもカナリア諸島で同様の栽培・奴隷貿易を行いました。1488年には〈バルトロメウ=ディアス〉(1450?~1500)【セH14】が喜望峰【セH14地図(ディアスの航路を選択する)】(注)を発見しています。
(注)岬なのに峰と呼ぶことについては,朝野洋一「喜望岬はどうして喜望峰なのか」を参照。http://open-university.yokappe.net/assignments/xiwangjiahadoushitexiwangfengnanokayuancichengxuexisentasuozhangchaoyeyangyi
スペインはレコンキスタの完了後,ポルトガルに対抗して東方交易の新ルートを開拓した
遅れてスペイン王国(アラゴン王国とカスティーリャ王国が合同して1479年に成立した【セH29ポルトガル王国ではない】。スペイン語ではエスパニャ王国)は,最後のムスリムの政権であるナスル朝(1232~1492) 【東京H24[3]】を滅ぼし,レコンキスタを完了させました。
スペイン王国は支配下にあった全住民にキリスト教を強制したため,非キリスト教徒はイベリア半島から逃れました。その場にとどまり隠れて信仰を守る者もありました。ユダヤ人の中には,北アフリカや中東に逃れる者も多く,彼ら「離散ユダヤ人」はセファルディムと呼ばれています。
スペインの援助を受けた〈コロン〉は,アメリカ大陸に到達した
スペインは1492年,ジェノヴァ【上智法(法律)他H30】出身の〈コロン〉(コロンブス,1451?~1506) 【セH15イサベルの援助を受けていたかを問う,セH27カブラルではない】【上智法(法律)他H30】に投資し,大西洋に船体を向かわせました。大西洋を西にすすめば,インドや日本(マルコ=ポーロは黄金の国「ジパング」と伝えていました)に近道で着けると考えたからです。〈コロン〉の弟は地図職人で,かつてポルトガルのリスボンに住んでいたときには,アイスランドにまで航海をしています。さらに,リスボン時代に地理学者〈トスカネリ〉(1397~1482) 【セH4大航海時代の始まった要因か問う】【セH15】との運命的な出会いを果たし,彼の主張する「地球球体説」【セH15】の正しさを確信しました。
1484年,〈コロン〉はポルトガルの〈ジョアン2世〉(任1481~95) 【上智法(法律)他H30 支援は受けられなかった】に西回り航路への資金援助を打診しますが,断られます。すでにポルトガルは,アフリカ南端から東回りでインドをめざす航路開拓の事業をすすめていたからです。
がっかりした〈コロン〉はスペインの港町パロスに移り,地元の貴族に資金提供をつのり快諾。さらにそのつてで,1486年スペインの〈イサベル〉女王【セH23】と〈フェルナンド〉王への謁見がゆるされたのです。しかし,またなかなか許可がおりません。
そこで,イングランド王の〈ヘンリ7世〉(位1485~1509)やフランスの〈シャルル8世〉(位1483~98)にも援助を打診し,フランスに向かおうとしていたところ,ちょうど1492年1月にイベリア半島最後のイスラーム教徒の拠点であるグラナダが陥落し,ナスル朝が滅亡。財政的余裕ができたこともあり,〈イサベル女王〉はふたたび関心を示し,ようやく〈コロン〉への資金援助が決まります。
王室と〈コロン〉は,次のような契約をします。
「〈コロン〉は発見した土地の副王・総督に就任する」
「発見した土地からの利益の10%は〈コロン〉のものになる」
満を持してインドを目指した〈コロン〉。ですが,彼が到達したのはカリブ海に浮かぶサン=サルバドル島【セH23】でした。たしかに地球は球体だったのですが,「アメリカ大陸」の存在を前提にしていなかったので,地球を実際よりも1/3の大きさに見積もっていたのです。
その後の3度の航海中に,住民のアラワク人を奴隷として連れ去ったり,現地でプランテーションをはじめたりした〈コロン〉は,最後までこの地の住民を「インド人」【上智法(法律)他H30】と考えていましたので,住民は“インド人”(スペイン語でインディオ)ということになりました。
1492年には,〈イサベル〉女王のスペインの要請を受けたジェノヴァ生まれの〈コロン〉が,第一回航海に乗り出し,カリブ海のサンサルバドル島に到達しました。〈コロン〉は実はコンベルソ(改宗ユダヤ人)で,迫害を逃れユダヤ人の新天地を探していたのではないかという説もあります。当時のイベリア半島では,隠れユダヤ人や改宗ユダヤ人に対する異端審問が厳しくおこなわれていたのです。
〈コロン〉は,ユーラシア大陸・アフリカ大陸になかった多くの新しい植物・動物を持ち込みました【セH14時期】。ジャガイモ【セH14時期,セH29試行 新大陸原産かを問う】,トウモロコシ【セH18】,トマト【セH18】,トウガラシ(南アメリカにおける総称は「アヒ」(注)),カカオ【セH18コショウ・ブドウではない】は,〈コロン〉以前は南北アメリカ大陸にしかなかったものです。ジェノヴァ生まれの彼がイタリアにトマトを持ち込んだことで,パスタのトマトソースが誕生することになります。また,シナモン・クローブ・ナツメグの香りをあわせもつとされることからオールスパイスと名付けられた香辛料もヨーロッパに持ち出されました。
反対に〈コロン〉が南北アメリカ大陸に持ち込んだものもあります。馬,鉄,車輪,さらに感染症(天然痘,ペスト,梅毒など)です。とくに感染症は,免疫のない南北アメリカ大陸の人々に猛威を振るいました。
(注)山本紀夫『トウガラシの世界史』中公新書,2016,p.5。
この知らせを受け,1493年に教皇〈アレクサンデル6世〉(スペイン出身,在位1492~1503)が,大西洋上にスペインとポルトガルの境界線を引いた。これが教皇子午線です。
しかし,スペインのライバルであった〈ジョアン2世〉は,「スペインに有利な引き方だ。ずるい! もっと西に引かせてほしい」と,〈イサベル〉女王に話を持ちかけ,境界線を教皇子午線よりも西に引き直した。これが1494年のトルデシリャス条約【セH23すべてがスペイン領になったわけではない,セH27】【追H20スペインとイギリスの間の条約ではない】です。
なお,のちにフィレンツェ【セ試行 イタリア人か問う】の〈アメリゴ=ヴェスプッチ〉(1454~1512) 【セ試行】【上智法(法律)他H30】【※意外と頻度低い】が〈コロン〉の到達した地がアジアではなく「新世界」(“新大陸”とは言っていません)【セH18】であることを指摘したことから,ドイツの〈ヴァルトゼーミュラー〉(ヨーロッパ初の地球儀をつくった人物)が〈アメリゴ〉の名(ラテンゴ名はアメリクス)をとって,新大陸を「アメリカ大陸」と命名しました。これがアメリカの語源です【セ試行】【セH23先住民の言語由来ではない】。
◆〈コロン〉のアメリカ大陸発見後,ポルトガルはアフリカ大陸まわりのインド航路を開拓した
西まわりをとった〈コロン〉に対し,ポルトガルは喜望峰まわりでのインド航路を開拓しようとします。1498年には〈ヴァスコ=ダ=ガマ〉(1460?~1524)が,喜望峰をまわって,東アフリカ沿岸のスワヒリ文化圏の都市国家マリンディに寄り,その地の航海士〈イブン=マージド〉のガイドでインド洋を渡り,西南インドのカリカットに到達しました【セH29試行 地図資料と議論(ヴァスコ=ダ=ガマの航海以降にインドと東アフリカの交流が始まったわけではない)】。
カリカットは,香辛料【東京H23[3]】【セH29試行 ジャガイモではない】貿易の中心地で,コショウ【セH11アメリカ大陸が原産ではない】とシナモンを積荷として持ち帰りました。これだけで航海費の60倍の価値があったそうです。
○1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ
西ヨーロッパ…現在の①イタリア,②サンマリノ,③ヴァチカン市国,④マルタ,⑤モナコ,⑥アンドラ,⑦フランス,⑧アイルランド,⑨イギリス,⑩ベルギー,⑪オランダ,⑫ルクセンブルク
◆西ヨーロッパで農業生産力が高まり、商業が活発化する
封建社会は,自給自足の社会です。だから,土地こそが“命”です。土地がなければ,食っていけないからです。自給自足といっても“エンジョイ田舎ライフ”のようなのん気なものではありません。外敵が進入し,世の中が混乱。広い地域を統一的に支配する権力者が不在なので,道すがら盗賊が現れても,捕まえたり裁いたりしてくれる権力がありません。そこで,商業が不振になります。
商業は,物資をある地点から別の地点に運ぶことで,「利ざや」を稼ぐ行為です。物自体に手を加えているわけではなく,ただ単に“珍しい”ものを地域に運ぶことで価値を生み出すわけです。しかし,高価な物は,山賊や海賊などに狙われるおそれがあります。安全な移動が商業活動にとっての生命線なので,その土地の支配者が誰なのかわからない状況であるよりは,統一的な権力が広い範囲にわたって平和を保障してくれていたほうが都合がよいのです。
中世の前期,つまり5世紀の西ローマ帝国滅亡から,ノルマン人の移動が激しかった10世紀くらいまでのヨーロッパは,不安定な情勢が続きました。
しかし,11世紀~12世紀くらいになると,農業生産力が向上して村落共同体が生まれ【セH15 11~12世紀にかけて封建社会が崩壊したわけではない】,停滞していた商業が復活します。そこには,この時期の地球が「温暖期」に突入していたことが関係しているともいわれています。例えば,1000年頃のヨーロッパの人口は3800万人ほどと推定されますが,これが12世紀には5000万人,13世紀には6000万人,14世紀のペスト流行の直前には8000万人になっていました。
○1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ
◆従来の農村拠点の修道院に代わり,都市を拠点とするフランチェスコ会が活発化する
托鉢修道会が都市と都市を結んだ
12世紀までの修道会は農村に大土地を所有して定住し,祈りや労働を主体とした生活を営むのが一般的でした。6世紀に設立されたベネディクト修道会が代表例です。
ヨーロッパの社会が安定し人口が増大すると,12~13世紀にはシトー修道会【追H30托鉢修道会ではない】などの修道院が,当時はまだヨーロッパ内陸部一帯に広がっていた森林を伐採し,耕地を広げる運動を起こすようになりました。この動きを大開墾運動【セH17リード文】ともいいます。
それに対してシトー修道会は,クリュニー修道会【立命館H30記】を「豪華な服を着て儀式をする,貴族的なやつら」と敵視し,生地を染めずに白い法服をまとって,人里離れたところで農民の中に入って布教活動を行っていました。自給自足のつもりで経営していた農場は,いつしか利益を生むようになっていき,結果的に商業の活性化に貢献することにもなりました。
しかし,所領が広がれば広がるほど修道院の財産は増え,「清貧」を重んじるキリスト教の精神に反する傾向も生まれます。
そんな中、イタリアの修道院長〈フィオーレのヨアキム〉(1135~1202)の思想の影響を受けた人々が「これからの時代は、修道士がキリスト教世界を担うのだ」という運動をおこしていました(ヨアキム主義,異端とされました)。
〈ヨアキム〉の説は、彼の思想は『新約聖書』の以下の記述に触発されたもので、千年王国論といいます。
「彼らは生き返って、キリストと共に千年の間統治した。」
「彼らは神とキリストの祭司となって、千年の間キリストと共に統治する。」
(「ヨハネの黙示録」第20章4,6節)
初期キリスト教の時代以来、この部分の解釈をめぐっては様々な説が展開されてきました(注)。
「今はつらいけれども、千年王国がすべてを解決してくれる…」
この魅力的な千年王国思想は、辛い境遇にある人々にこそ支持をひろげていきます。
こうした思想の影響を受け,キリスト教の原点に立ち戻り,托鉢(たくはつ,寄付を募ること)を行いながら説教をして都市を渡り歩く新しいタイプの修道会が現れます。これを托鉢修道会といいます。
12世紀末からすでに教会の刷新運動は起きており,1170年には,リヨンの商人の〈ワルド〉も,財産をなげうってラテン語ではなく話し言葉でイエスの教えを説いて回りました(注)。しかしこのワルド派は“異端”とされ,教会から破門されました。
(注)聖書の口語訳の最初。『世界史年表・地図』吉川弘文館,2014,p.121
その後,中部イタリアのアッシジの〈フランチェスコ〉(1181?82?~1226)自らすすんでセレブ暮らしを捨てて極貧生活を選び,托鉢(たくはつ。お金をくださいと人にお願いすること)をしながら人々に説教をしました。1209年に創設されたフランチェスコの修道会は,教皇の堕落にウンザリしていた人々の心を捉えていくと,フランチェスコ会の中でも穏健なグループが1210年に教皇〈インノケンティウス3世〉により公認されました。人々は,カトリック教会による神秘的な儀式よりも,わかりやすい説教を求めていたのです。なお修道会は,カトリック教会と目的や生活スタイルが異なるだけで,信仰の内容はカトリック教会と同じです。
1215年には〈ドミニコ〉が南フランスでアルビジョワ(カタリ)派の改宗に尽くして,ドミニコ修道会を創設しました。ドミニコ修道会には過激な武闘派が集まりましたが,教皇は彼らの勢力をカタリ派退治に利用したわけです。
彼らはパリ大学での教義研究にも熱心で,12世紀にイスラーム世界から伝わっていた古代ギリシアの〈アリストテレス〉の学説をキリスト教に導入するなど,最先端の知の導入にも積極的でした。
フランチェスコ修道会とドミニコ修道会といった托鉢修道会が,都市を中心に学問・経済・文化・外交において活躍をした13世紀のことを「托鉢修道会の時代」ともいいます。
○1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ
◆西ヨーロッパ各地で開墾・開拓運動が活発化し,遠隔地交易が発達する
北の毛織物・ニシン,南からの香辛料
ネーデルラントの工業地帯フランドルでは修道院が中心となって干拓(海の水を抜いて,陸地をつくること) 【セH7 11世紀以降の西欧で農業生産力が向上した要因か問う】を積極的にすすめ,運河も建設されるようになります。また,土地を持った農民は協力して堤防を築き【セH7 11世紀以降の西欧で農業生産力が向上した要因か問う】,開墾をすすめました。アムステルダムやロッテルダムなど,現在のオランダに残る地名の「ダム」は,堤防のことです。
大開墾運動や鍛冶技術(かじぎじゅつ)の改良による鉄製農具の使用,さらに重量有輪犂(じゅうりょうゆうりんすき。重い犂を牛に引かせるトラクターのこと)の利用にともない農業生産が増大していきました。
地中海周辺の二圃制農業を夏に雨の降るアルプス山脈以北の気候向けにアレンジし,農地を大きく3区分(大麦・ライ麦の春耕地,小麦・えん麦の秋耕地,休ませる休耕地)し,年ごとにローテーションさせる三圃制【セH7 11世紀以降の西欧で農業生産力が向上した要因か問う】【※意外と頻度低い】が,9世紀にフランク王国の一部,12世紀にはロワール川以北の西ヨーロッパで見られるようになりました。こうすれば,ライ麦やえん麦を家畜のエサにしつつ,休耕地を設けることで土地を休ませることができるため,生産力がアップしました。三圃制が導入された地域では,城主が広い土地を一円的に支配する動きがみられます。
これら農具や家畜の共同管理,共同の農作業【セH7】の必要から,農民たちは団結して農村共同体をつくるようになります【セH7 11世紀以降の西欧で農業生産力が向上した結果,農民相互の結びつきが強くなったか問う】。
他方,南フランスなどの地中海沿岸では穀物栽培よりもブドウ栽培や牧畜が盛んで,三圃制は普及せず(二圃制のまま),広い地域を支配する城主も現れませんでした。
人口が増え,余剰生産物が発生し,それらを交換する人々が増えていきます。交換を効率よく行うには,欲しい人と売りたい人が出会う時間と場所が決まっていれば好都合です。初期のころは,「毎月1日に,どこどこに集まろう」と決めておいて,そこでマーケットを開きました。
人が集まりやすいところというのは決まっています。川と川が交わるところとか,交通の便のよいところです。例えば12~13世紀の北フランスのシャンパーニュ地方【セH23,H30】では,4つの都市で開催されていた6つの市場をつないだ「大市」(大規模な定期市) 【セH23】が開かれていたことで有名です。
ヨーロッパの南北を結ぶ交易路は,ミラノ北方のサンゴタール峠を抜け→ストラスブール→ヴォルムス→マインツ→ケルン→ネーデルラントに至るルートや,スイスのジュネーヴ方面からアルプスを越え,ブザンソン→シャンパーニュ地方に至るルート,マルセイユからアヴィニョンに北上し,ローヌ川をさかのぼって→トロア→パリに向かうルートなどがありました。
それが,1300年頃にヴェネツィアが北方のブレンナー峠を抜けてアウクスブルク→ニュルンベルクに至るルートを開通して以来,さらに活発化していくことになります。
海路でも,1291年頃にジェノヴァ人がジブラルタル海峡を抜けて,ネーデルラントに至るルートを開拓。ジブラルタル海峡を挟むイスラーム教勢力のせいで阻まれていたルートに,光明が差し込みます。
(1) 南から北へ …地中海に面するイタリアの港町や内陸都市から,東方の物産や工業製品がアルプスを越えて贅沢品が運ばれて来る。
(2) 北から南へ …バルト海沿岸の木材・海産物・穀物や,フランドル地方(現在のベルギー)の羊の毛織物【東京H17[3]】が運ばれてくる。
(1)と(2)が出会う場所が,シャンパーニュであったということですが,イベリア半島のイスラーム政権の衰退とともに,海路ルートが盛んとなって次第に衰退に向かい,金融の中心もネーデルラント(低地地方)のアントワープに移っていきました。
○1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ
◆イタリア諸都市が商業によって栄え,金融業が発展し複式簿記も発達した
イタリア商人とドイツ商人が,自治を求めた
ちなみに,地中海に面するイタリアの港市としては,ヴェネツィアやジェノヴァ,ピサが有名です。ビザンツ帝国などの東方から,香辛料・絹織物などのぜいたく品(奢侈品(しゃしひん))が運び込まれます。ピサには14世紀の教会大分裂の時期に,教皇庁が置かれたこともあります【セH24フィレンツェではない】。
ジェノヴァは13世紀には,櫂船(オールでこぐ船)により,ジブラルタル海峡を経由して北海(イギリスとスカンディナヴィア半島,ユーラシア大陸の間に囲まれた海)に入りフランドル地方,バルト海に到達する交易ルートを開いていました。
彼らの中には,お金を出資する人と,船を出して遠隔地交易をする人の役割分担がなされるようになり,コンパニア(カンパニーの語源です)やソキエタスといった共同事業を行う会社が作られるようになっていきました。遠距離航海には難破のリスクがありますが,成功すれば利益をがっぽり得るチャンスもあります。巨大プロジェクトの場合には莫大な資金が必要になりますが,利子(キリスト教で禁止されていましたが“罰金”という屁理屈で許可されました)をつけて後から返済する形で資金を集める仕組みも開発されていました。
取引が複雑化するにつれ,すでに地中海沿岸の商人により使用されていた会計を「貸方」と「借方」に分けて記録する複式簿記も発達していきました。13世紀以降のイタリアでは「…記憶にしたがって取引することをやめ,みずからペンを執って取引にかかわることがらを克明に書き留めるようになった」。この「商業の文書化」が,「各地にはりめぐらされた商業通信網をつうじて代理人と連絡をとりながら取引をすすめるように」なる「商業の定地化」を促します。すると,商人から離れ他者に委託された貨幣も商品の安全を保証する仕組みとして,貨幣については為替や振替銀行,商品については運送業と保険が発達します。「このように入り組んだ取引関係を一望のもとに把握する手段として,簿記が発達して」いったのです(大黒俊二「為替手形の「発達」―為替のなかの「時間」をめぐって―」板垣雄三ほか編『シリーズ世界史への問い3 移動と交流』,p.114)。
イタリアの内陸都市としては,フィレンツェやミラノ、シエナが有力で,11世紀以降,水車を利用した毛織物工業【セH24,セH30フィレンツェで栄えたのは綿織物工業ではない】や,それでもうけたお金を個人や外国政府に貸し付ける金融業(きんゆうぎょう)で栄えます。工業というのは,「物を作ること」だと思ってください。金融業は,「お金を貸して,利子でもうけること」です。
フィレンツェで金融業により栄えた一族を,メディチ家といい,のちに市政を牛耳るだけでなく,〈レオ10世〉(ジョヴァンニ=デ=メディチ)のように教皇になる者も現れました。
また,イタリアからドイツ方面を結ぶルートにあたる南ドイツでは,アウクスブルクや,その北のニュルンベルク【追H20地図問題】が発達しました。アウクスブルク【セH24フィレンツェではない】の銀山を支配し,金融で栄えたのはフッガー家【セH7新大陸の銀を利用したわけではない】【セH22・メディチ家ではない・地図上の位置,セH24】です。神聖ローマ帝国に資金を貸し付けて,皇帝を手のひらで転がすようにもなっていきます。
物資の交易が盛んになればなるほど,12世紀中頃までに農村部にも貨幣経済は広まっていきました。
領主は所領でとれた収穫物を「市場に売ってお金に変えたい」と考えるようになりました。領主は生産物ではなく,貨幣によって地代(貨幣地代)をとるようになっていきます【セH5 「14~15世紀に領主の貨幣需要の増大,戦費の増加などにより,領主財政は危機に見舞われた」か問う(正しい)】。
都市の起源はさまざまで,ローマ帝国に軍隊が駐留していた都市もあれば,ローマ教会の司教座都市(司教が置かれた教会のあるところ)を起源とするものもありました。しかし,商人にとってみれば「汗水たらして手にした財産を,支配者に税として取られるのは嫌だ」と思うのが自然です。
領主は,自分の領地の中に商人の集まる商業都市ができると,商人から税金がたんまりとろうと画策します。当初都市は領主に従っていたものの,商工業の発達によって力をつけていくと,だんだんと領主から自治権【セH14不輸不入権・叙任権ではない】が与えられる動きがみられるようになります。こうして,11~12世紀以降に領主の支配を脱した都市を,自治都市といいます。都市は行政と立法の機能をもつ市参事会や,裁判・軍事・外交の機関を持っていました。
北イタリアでは,司教を倒して自治都市(コムーネ) 【追H30】となる例が多く,周辺の農村も含めて【追H30「周辺の農村を支配に組み込んで」】完全に独立した都市国家となりました。
フィレンツェでは平民層が都市の支配権を握ります。
ヴェネツィアでは総督と都市貴族が評議会を結成してヴェネツィアと海外領土を支配しました。後背地の森林地帯は船の材料となるため伐採がすすみ,ヴェネツィアの海上進出を支えました。
やがてミラノを中心に12~13世紀に2度ロンバルディア同盟を形成し,神聖ローマ帝国の進入に対抗するようになります。
ドイツでは,神聖ローマ皇帝が「領邦と同じ地位を与える」特許状を与えて,自由都市(帝国都市)となる例が見られました。神聖ローマ帝国では,いくつもの領邦が立ち並ぶ“どんぐりの背くらべ”状態でした。そこで,とくに南ドイツの都市に,領邦と同等の権利を与えて帝国都市とし,皇帝・国王に直属させることで,他の領邦を牽制(けんせい)したのです。
自由都市にはほぼ完全な自治権が与えられ,バーゼル,ケルン,マインツ,ヴォルムス,シュトラスブルク,シュパイアー,レーゲンスブルクの7都市が指定されました。のちに帝国都市と自由都市の区別はなくなり,帝国自由都市とされます。ライン川の重要な支流であるマイン川(マイン川を上流にさかのぼると,ドナウ川の上流に繋がります)の流れるフランクフルト=アム=マイン(フランクフルト)も帝国自由都市の一つで,市の参事会(さんじかい)には自分たちで指導者を選出する権利が認められていました。ただし自分たちで選べるといっても,投票できるのは一部の上層市民たちでした。
リューベック【セH22,セH26地図上の位置,セH29フィレンツェではない】を中心とする諸都市の通商同盟であるハンザ同盟(13世紀~17世紀) 【セH21自由競争を保障する組織ではない】は,14世紀になると北ヨーロッパ商業圏(北海からバルト海にかけての商業圏)を支配するようになりました。互いの都市に支店や倉庫を置くことで,無用な争いを避けたのです。ハンブルク【セH19アントウェルペンとのひっかけ】やブレーメンのほか,遠隔地のロンドン,ブリュージュ,ノヴゴロド,ベルゲンにも商館が設置されました。リューベックには西方からは毛織物が,東方からは小麦,コハク,毛皮や木材・樹脂が運び込まれ,北ヨーロッパにおける東西貿易の中心部として栄えました。
ハンザとは「組合」という意味で,共通の貨幣・法・度量衡・軍隊も保有していました。花形商品は“海の銀貨”と呼ばれたニシンです。バルト海のニシンは年に1度産卵のために浅瀬にやってくるのですが,春にニシンがやってくるスウェーデン南部の漁場には,毎年8~9月に塩漬けニシンの魚市場が開かれるよぬいなりました。ここはバルト海~北海を回遊するニシンの通り道でもあり,ドイツのリューベック商人などヨーロッパ各地から来る承認でにぎわいました。キリスト教徒には四旬節(しじゅんせつ)という期間(40日間)は肉を控えて金曜に魚を食べるという習わしがあったため,ニシンが重宝(ちょうほう)されたのです。(現在でもスウェーデン北部ではシュールストレミングという世界一臭い食べ物に認定されたニシンの発酵食品があります。まず口に近づけるだけでも大変なので,一人で食べきることは難しいと思います)。
○1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ
◆都市の内部にはギルドが形成された
都市内部では,自由競争ではなくギルドによる団結
イングランドでは,諸侯〈シモン=ド=モンフォール〉(1208頃~65) 【立教文H28記】の反乱により,都市の代表が議会にはじめて招集されるようになりました【共通一次1989イギリス最初の議会ではない】。彼はのちに内戦で敗死しています。
中世の自治都市【セH9城壁で囲まれていたか問う】の中には,ギルド【セH9】【セH21自由競争を保障する組織ではない】という同業組合がありました。ギルド(同業組合)とは何でしょうか。都市内部に,靴屋が3軒あったとします。この3軒が,たがいに安い価格を競ったら,体力が持たずにつぶれてしまうかもしれません。そこで「茶色い男性用革靴のLサイズの価格は最低でも1万円にしよう」などと取り決める。すると,お客さんはこの3軒のうちどの店に行っても1万円なので,それが予算内に収まっていれば,本当に欲しいなら1万円で買ってくれるはずです。短い目で見れば,他の2軒はお客さんを取られてしまったわけですが,長い目で見れば,競争を回避できます。また,1軒ずつ違う場所から材料の革を仕入れるよりも,3軒まとめて仕入れたほうが,輸送費・交通費・手数料は低く抑えられますね。人が足りないときには,従業員をシェアすることもできます。
商人もギルドを作りました(商人ギルド【セH14時期(15世紀以降ではない)】)。遠く離れた場所に共同で使える旅館や休憩所,資金を借りることができる場所や,商品を置いておく倉庫が設置され,お互い助け合ってビジネスをする関係を築いていました。また,お金もうけは「情報戦」でもあります。「卵を一つのカゴに盛るな」という言葉どおり,資金のすべてを一つのビジネスにつぎ込んでしまったら,失敗したときのリスクは大きい。そこでリスク分散のために,商人はしばしば協力をしました。そのネットワークが広範囲で強いほど,その商人グループには多くの資金が集まっていくでしょう。彼らは都市の中で大きな声で意見を主張するようになり,やがて市政を独占するようにもなっていきました。市民のことをブルジョワと言います。誓約をたてて市民権を獲得した市民たちは,都市への愛着や結びつきが強く,都市の紋章・印璽(いんじ。公文書に押すハンコのこと)・年代記(13世紀頃から俗語による記録がみられるようになっています)・詩などが多く作られました。
しかし,商人の輸出する商品をつくらされているのは手工業者です。手工業者が丹精込めて作った靴の値段を決めるのは,商人ギルド。
それに対して,不満を持った手工業者は,組合(同職ギルド(ツンフト)【セH2親方と職人・徒弟は対等ではない,セH10時期(古代ギリシアではない),セH12「自由競争を保証し,生産統制を撤廃した」か問う】【セH23自由競争を保障する組織ではない】)をつくって商人ギルドから分離し,商人ギルドの持っている市政に参加する権利を求めて争いました。これをツンフト闘争【東京H26[3]用語の説明】といいます。
しかし,同職ギルドの組合員には,独立して自分の店を持つ親方しかなることができませんでした【セH2親方と職人・徒弟は対等ではない】【セH28職人・徒弟が加入できたわけではない】。親方になるためには,徒弟や,その上の職人の身分で長い下積み経験を経る必要があったのです。誰でも自由に親方になって店を開けてしまったら,店が多すぎて過当競争になってしまうという面があるからです。「自由(競争)」か「平等(規制)」かという選択は,今後も人類にとって大きな課題となっていきます。
ちなみに,職人が親方として暖簾(のれん)を分けることが認められるには,マスターピースという作品をつくって,その出来を親方に認められる必要がありました。マスターピースには英語で「傑作」という意味がありますね。都市にはほかにも,共通の守護聖人を信仰する兄弟団という相互扶助組織がありました。少しずつお金を出し合って,困っているときや冠婚葬祭のときに少しずつ助け合うための組織です。
なお,「都市の空気は自由にする」(Stadtluft macht frei,都市の空気は「その人を」自由にするという意味)【東京H23[3]】【慶文H29】という言葉のように,領主の支配下から逃亡された農奴や手工業者は,1年と1日,が経過すれば都市の住人として自由になれるとする法もありました。
○1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ
◆大聖堂の建設は,ヨーロッパの経済発展を象徴するもの
聖母マリア信仰,ゴシック様式の大聖堂,聖歌
さて,これだけ商業が発達すると,その経済力を背景に各都市には,天高くそびえ立つゴシック様式【セH23】の聖堂が建てられるようになります。最初の例は1135年頃にフランスに建てられたサン=ドニ大聖堂(フランス王が埋葬される教会)です。尖ったアーチ(尖頭アーチ)と,太陽光がカラフルで幻想的な光となって入り込む仕掛けとなっているステンドグラス【セH25ビザンツ様式の特徴ではない】,石積みの壁の重みを分散させるためのフライング=バットレスが特徴。
以下の大聖堂が特に有名です。
・現在のフランス:パリのノートルダム大聖堂,シャルトル大聖堂【セH17】【追H30ロマネスク様式ではない】,アミアン大聖堂,ランス大聖堂
・現在のドイツ:ケルン大聖堂(◆世界文化遺産「ケルンの大聖堂」1996,2008範囲変更)
・現在のイギリス;カンタベリ大聖堂
ステンドグラスに表現されたのは,聖書の話や都市にまつわる聖人の物語です。聖堂には鐘楼が付けられており,鐘の音が都市の時間を支配していました。
特にシャルトル大聖堂のステンドグラス「美しき絵ガラスの聖母」は,青を基調とした幻想的な仕上がりで有名です【セH17宗教改革を記念して建設されたわけではない(時期が異なる)】。この時期には聖母〈マリア〉のモチーフが,ノートルダム(=我々の貴婦人)という名前からもわかるように,広く信仰を集めます。
ゴシック様式以前の,1000年頃から1200年頃には,厚い石壁と小さな窓を特徴とするロマネスク様式(【東京H24[3]】【セH10ロマネスク様式ではない】【セH23】斜塔のあるピサ大聖堂【セH10ビザンツ様式のサン=ヴィターレ聖堂とのひっかけ】【セH30】が有名)が有名でした。採光が弱いので,中に入ると薄暗く,重厚な雰囲気に包まれています。
初期の頃は和音ではなく単音のフレーズから成り立っていたグレゴリオ聖歌も,天井の低いロマネスク式の教会の中なら音がこもって厚みが出ます。これにより,複数の旋律を合わせた多声の音楽(ポリフォニー)が発達していくことになります。
神聖ローマ帝国の皇帝が,自らの権威を示すために各地に建てたのが始まりです。聖堂以外にも,市庁舎や商館など,さまざまな建物が建てられました。都市の中心には広場があって,政治的な発表,公開処刑,定期市が催されました。
1300年頃からは,封建社会の仕組みがだんだんと変化し,新たな仕組みが見られるようになっていきます。
主君から頂いた土地が“命”ほどの大切さとして感じられるには,「自給自足」の経済が前提です。土地がなければ何も手に入らない状況。それが崩れ始めるのは,商業が復活していったからです。小麦粉が欲しければ,小麦を栽培し,それを挽かなければなりませんが,商業が盛んになれば,市場に行けば簡単に手に入るようになります。
農民の中には,自分で生産物を売って,貨幣を貯める者も現れます。領主も貨幣が欲しくなりますから,農民から貨幣で税をとろうとするようになる。従来,領主は自分の土地で農民に働かせる形の税(賦役(ふえき)といいました)を課していましたが,「これからはお金で納めてくれればいいから」と方針転換する領主も現れました。
しかし,14世紀に入ると気候が寒冷化し,飢饉や不作が相次ぎ,追い打ちをかけるように黒死病(ペスト,ブラック=デス)が大流行し,人口が激減。そこで領主は,少ない農民で領地を経営していくために,生き残った農民たちを大切に扱うようになります。待遇を向上させた農民の中には,不自由な身分である農奴から解放される者も現れ始めました(イギリス,フランス,西南ドイツに多いです)。
○1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ
◆「14世紀の危機」を越え,各地で領域国家が形成されていく
この「14世紀の危機」を乗り越え,ヨーロッパには排他的な支配領域を持つ領域国家が成立していくことになります。領域国家を建設していった国王らの支配層は,官僚制・常備軍を整え,域内のさまざまな身分の権力を押さえつつ財政基盤を確立しようとしました。
しかし,諸侯の中には没落して,さらに格上の大諸侯や国王に領主を取られるものも出てきます。
さらに,14~15世紀には火砲が発明され従来の一騎打ちの戦法が歩兵と砲兵を主力とする戦法に変化し,諸侯や騎士は用無しになり始めていました。没落した騎士は,国王のいうことを聞く形で生き残りを図るようになります。
国王は諸侯・騎士にいうことを聞かせるため,商人と結んで経済力をつけていきました。商人にとっても,統一的な権力があったほうがビジネスを安全におこなうためには有利なので,国王に戦争資金を援助するなどして,権力に取り込みます。国王は一部の商人に特権を与え,彼らを保護していきました。
・1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ 現①イタリア
神聖ローマ帝国とローマ教皇との叙任権闘争は,1122年に〈ハインリヒ5世〉(位1106~25)と教皇との間に締結されたヴォルムス協約で,皇帝にドイツの司教に封土を与える権利があることを確認して,一応の決着をみました。
〈ハインリヒ5世〉と次の〈ロータル3世〉(位1125~37)には子がなかったので,ザリエル朝が断絶し,諸侯の選挙でホーエンシュタウフェン家の〈コンラート3世〉がドイツ王に選ばれました。彼はイタリアへの積極的な進出をしたために,交易の活発化で成長していたイタリア諸都市の反発を招き,ホーエンシュタウフェン家の皇帝派のギベリンと,教皇派のヴェルヘン家によるゲルフとの間に内乱が勃発しました。
しかし,〈コンラート3世〉の甥〈フリードリヒ1世〉が,ドイツ王(位1152~90)と神聖ローマ帝国皇帝(位1155~90)に即位しました。彼は通称・赤ヒゲ王(バルバロッサ)と呼ばれ,第三回十字軍に参加したほか,第三回十字軍(1189~92)にも参加しました。
しかし,彼も和平を撤回してイタリア政策を推進し,1258年に北イタリアを占領しました。それにたいして,ミラノを中心にロンバルディア同盟【セH19】が結成されました。
〈フリードリヒ1世〉の孫〈フリードリヒ2世〉(皇帝在位1215~50)【セH27ハプスブルク家ではない】はシチリア島を相続し,宮廷をもうけて官僚制を整備しました。〈フリードリヒ2世〉に対しても,イタリア北部の都市はロンバルディア同盟を結成しています。【セH30】。
13世紀になると,イタリアの諸共和国では都市の貴族と民衆(武装した民衆。ポポロといいます)との対立が表面化し,紛争につけこんだ有力者(地方の地主貴族)によって市政が乗っ取られることもありました。この有力者はシニョーリ(領主)となって,都市の安全を保障するかわりに,一族により市政を牛耳るようになりました【セH2イタリアでは富裕な市民たちが政権を握る共和国が成立したか問う】。
さて,〈フリードリヒ2世〉は,地中海の十字路ともいわれるシチリア島で,イスラーム教徒たちとも交遊しながら,幅広い知識を身に着けていた人物です。第五回十字軍では,イスラーム教徒間の争いを利用して,イェルサレムをアイユーブ朝の〈アル=カーミル〉との外交交渉で開城してしまうというスゴ腕の持ち主です。ただイスラーム教徒とべったりしているように見えた彼の行為には批判も多く,教皇から破門された状態での十字軍となりました(「破門十字軍」といいます)。
また,教皇の下で設立されたボローニャ大学に対抗して,ナポリ大学も開いています。
しかし,ドイツを留守にしがちだった〈フリードリヒ2世〉はドイツの領邦の機嫌をとるために,“独立国”であることを事実上認める妥協をしてしまいました(「諸侯の利益のための協定」)。こうして領邦は,皇帝から貨幣の発行権や裁判権などを認められて“領邦国家“へと発展していきました。彼の時代に東方に植民したドイツ騎士団も有力な領邦として,のちのプロイセンにつながっていきます。
ホーエンシュタウフェン朝が断絶すると,皇帝不在の“大空位時代”(1256~73)【セH19】が始まりました。皇帝が短期間即位したこともありましたが,大して力のない諸侯や帝国の外の者であることが多く,不安定な時代でした。
14世紀にはイングランドの〈ウィクリフ〉や,ベーメンの〈フス〉など,カトリック教会を批判する勢力が支持を集めていました。これに対し,神聖ローマ皇帝の〈ジギスムント〉(位1411~37)は,混乱収拾のためにコンスタンツ公会議(1414~18) 【セH14トリエント公会議(宗教裁判所による異端の取り締まりが強化される中での開催)ではない,セH18ニケア(ニカイア)公会議・メルセン条約・アウクスブルクの和議ではない,H22
15世紀ではない,H26エフェソス公会議ではない,H29トリエント公会議ではない】を開催し,自体の収拾を図ります。
そんな中,15世紀前半にはミラノとヴェネツィアがイタリア東部をめぐり争いますが,1454年に和約を締結しています。ヴェネツィアは,一部有力家系が大評議会をつくり,ドージェ(頭領)を選出して政治を行っていました。
○1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ 現①イタリア
◆イタリア諸都市では商人が政治・経済を独占し,ルネサンスのパトロンになった
メディチ家は,「古代ギリシア」文化を旗印とした
シエナ
シエナには12世紀にコムーネが成立して、自治が行われていました。しかし約60km北にあるフィレンツェ共和国【セH22地図上の位置】とたびたび衝突し、14世紀中頃のペスト〔黒死病〕の流行により人口が激減し、衰退に向かいます。
1382年に完成した大聖堂(ドゥオーモ)や、カンポ広場、マンジャの塔(102m)をもつゴシック様式の市庁舎が、当時の繁栄を物語っています(◆世界文化遺産「シエナの歴史地区」、1995)。
フィレンツェ
フィレンツェ共和国【セH22地図上の位置】は交易により栄え,1252年にフローリン金貨を鋳造し,国外でも使用されています(◆世界文化遺産「フィレンツェの歴史地区」1982、2015範囲変更)。
1378年に毛織物業者のチョンピの反乱が暴動を起こしています。毛織物をつくる過程のなかでも特に大変な工程である「梳毛(そもう)」を担当していたのは,都市のなかでも特に下層の職人。数ヶ月ではあるものの,下層労働者による政権がフィレンツェに樹立されますが,直後に上層労働者により崩壊しています。
その後は上層市民への資本の蓄積がすすみ,1434年に銀行家のメディチ家【セH22・H24フッガー家ではない,セH15・H27ともに芸術家を保護したか問う】が支配的となっていました(#漫画 〈惣領冬実〉による漫画『チェーザレ 破壊の創造者』はこの時代を扱っています。〈マキャヴァッリ〉〈コロン〉なども登場)。
〈ジョヴァンニ〉が銀行業で成功し,死後に長男の〈コジモ=デ=メディチ〉(1389~1464)が一時フィレンツェを追放されるも,翌年には復帰。
彼はフィレンツェの美化に努め,フィレンツェ市民の支持を受けて地歩を固めていきました。愛称は“イル=ヴェッキオ”(おじいさん)。
しかし,1453年。オスマン帝国によるコンスタンティノープル陥落のニュースはイタリア半島に衝撃を与えます。相争っている場合ではないと,〈コジモ〉はみずから動き,1454年にはイタリア諸都市,ナポリ王国,教皇との間の和約を取りまとめます(ローディの和)。
このときの協定参加国は次の通り。
①メディチ家支配のフィレンツェ共和国
②スフォルツァ家支配のミラノ公国
③寡頭支配のヴェネツィア共和国
④ローマ教皇領
⑤ナポリ王国
キリスト教の登場する前のギリシアやローマの思想を研究する学者を保護した〈コジモ=デ=メディチ〉【慶文H30記】は,古代の〈プラトン〉の私塾アカデメイアに憧れたてプラトン=アカデミーを開き,学者の活動を支援しました。例えば〈ピコ=デラ=ミランドラ〉(1463~1494)は,『人間の尊厳について』で人間には自由な意志があるのだことを主張。〈フィチーノ〉(1433~1499) 【慶文H30問題文】は〈プラトン〉研究をおこなっています。
〈コジモ〉はほかにも,新しい技法を美術に導入していた〈ブルネレスキ〉【セH24】【慶文H30記】(1377~1446,フィレンツェ出身,フィレンツェのサンタ=マリア大聖堂【セH10ビザンツ様式ではない。サン=ヴィターレ聖堂とのひっかけ】のドームを設計【セH24ハギア=ソフィア聖堂ではない】),〈ドナテッロ〉(1386~1466,フィレンツェ出身,線遠近法を開発)を保護しました。
〈コジモ=デ=メディチ〉の死後に跡を継いだ〈ピエロ〉は短期間で亡くなり,その子の〈ロレンツォ=デ=メディチ〉(1449~1492) 【慶文H30記】が後を継ぎました。しかし,フィレンツェの支配権をめぐり教皇〈シクストゥス4世〉(位1471~84システィーナ礼拝堂を建設した人。システィーナとは彼の名)がメディチ家のライバルのパッツィ家と協力し,〈ロレンツォ〉と弟〈ジュリアーノ〉を襲撃。〈ジュリアーノ〉は殺害されたものの,生き残った〈ロレンツォ〉はこの“パッツィ家の陰謀”の事実を暴き,パッツィ家の人々を処刑。教皇は今度はナポリ王国と協力して攻めますが,〈ロレンツォ〉は和平に持ち込みます。
彼は,ギリシア神話をモチーフとした「春」「ヴィーナスの誕生」を生み出した〈ボッティチェリ〉(1445~1510)【セH4時期(15~16世紀か問う)】を保護し,「ダヴィデ像」で有名な〈ミケランジェロ〉の才能も発掘しました。
しかし,〈ロレンツォ〉の息子〈ピエロ〉は外交政策で失敗し,フィレンツェから追放されます。
代わって,1497年にドミニコ会士〈サヴォナローラ〉がメディチ家による市政の独占やローマ教皇を批判し,フィレンツェで宗教改革を目指し,「虚栄の焼却」と名付けて多くの書物や美術品を焼きました。しかし,ライバルのフランチェスコ会士の反発を受け,1498年に火刑に処されました。この混乱の直後,〈ミケランジェロ〉は巨人に立ち向かう「ダヴィデ像」を制作(1501~1504)。しかし,フィレンツェが活力を取り戻すことはありませんでした。
ヴェネツィア
ヴェネツィアでは1284年にドゥカート金貨が鋳造されています。この金は西アフリカからエジプト経由でもたらされたものです。当時の西アフリカではマリ帝国が栄えています。
この頃,父と叔父とともに陸路で東方に旅行したヴェネツィア共和国【セH29場所を問う】の商人〈マルコ=ポーロ〉(1254~1324) は,大都で元の〈クビライ〉につかえたとされ,帰路は元の皇女を結婚のためイル=ハン国まで運ぶ船に同乗しました。体験談を『世界の記述(東方見聞録,イル=ミリオーネ)』にまとめ,大きな反響をもたらします。
○1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ 現①イタリア
◆シチリア島はノルマン人の支配下で,中央集権的な国家機構を発達させていった
シチリアには,最先端の政治・文化が栄え,諸国の争奪の的となる
ナポリとシチリアにノルマン人によって1130年に建国されていた両シチリア王国(ノルマン=シチリア王国)です【セH29アヴァール人ではない】はのちに断絶し,神聖ローマ皇帝〈フリードリヒ2世〉を出したドイツのシュタウフェン朝にわたります。
この時代のシチリア島はまさに「文明の十字路」で,古来さまざまな文化の行き交う“最先端”の島でした。両シチリア王国の〈ルッジェーロ2世〉には,イスラーム教徒の地理学者〈イドリーシー〉がつかえ,当時としてはかなり正確な世界地図を描いています。
彼はローマ法を整え,中央集権的な官僚制度が整えられていき,ヨーロッパにおける近代国家の“先駆け”の様相を呈します。「中央集権的な官僚制度」とはいっても,中国のように官吏任用試験をおこなったわけではありません。1224年にナポリ大学を設立し,ここで官吏を養成したのです。さしずめ“公務員養成予備校”といったところです。
この時期を通して,フランス王国と神聖ローマ帝国は,互いに競ってイタリアへの支配権を獲得しようとしていました。特に,神聖ローマ皇帝の支配下に置かれた都市は「ギベリン(皇帝派)」,教皇の配下の都市は「ゲルフ(教皇派)」に属し,互いに抗争を繰り返すようになっていきました。狙われるということは,それだけイタリア都市国家が栄えていたということでもあります。
「シチリアの晩鐘」(1282)以降は,シチリア=アラゴン家,ナポリ=アンジュー家の支配に
シチリアとナポリの支配権は,シュタウフェン朝からフランスのアンジュー家へと代わります。
しかし,アンジュー家貴族による過酷な支配へのシチリア島民の反乱をきっかけに,1282年“シチリアの晩鐘(ばんしょう)”と名付けられた騒乱が起き,シチリア島はイベリア半島のアラゴン家の支配下となりました。
一方アンジュー家は,ナポリ王国を支配しつづけたので,シチリア王国とナポリ王国に別れることになりました。
1442年にアラゴン王国〈アルフォンソ5世〉の征服で,ナポリもアラゴン家の支配下に
1442年にアラゴン王国〈アルフォンソ5世〉の征服により,シチリア=アラゴン家,ナポリ=アラゴン家となります。
そこへ,1494年にフランスの〈シャルル8世〉がナポリ王国の継承を要求して始まったのが,第一次イタリア戦争なのです【セ試行 時期(1558~1603年の間か問う)】。こうして,1454年に成立していたイタリア半島の5大国によるローディの和は破られ,イタリア半島は衰退の時代を迎えます。
フランスの南進に対し,ボルジア家出身のローマ教皇〈アレクサンデル6世〉(位1492~1503)は対抗し,愛人との子〈チェーザレ=ボルジア〉(1475~1507)に軍を率いさせます。ボルジア家は“陰謀”の使い手で,権謀術数をもちいてイタリアの諸勢力を混乱させつつ,自身は権力を掌握していきました。この様子をみていたのは,のちに『君主論』をあらわすことになるフィレンツェの外交官〈マキャヴェッリ〉(1469~1527)でした。
メディチ家の失策と,ローマ教皇のやりたい放題ぶりをみて,フィレンツェでは1498年に〈サヴォナローラ〉による教皇批判も起きています。
○1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ 現①イタリア
◆イタリアの都市国家は東方貿易を通して新技術や情報を次々に導入する
イタリアは,ユーラシアに向けた「窓」に
イタリアの都市国家の人々は,オスマン帝国との東方(レヴァント)貿易によって都市が商業的に栄えるとともに,イスラーム教徒を通して,キリスト教文化とは異なる文化に接するようになっていました。12世紀に始まるイスラーム教徒を通した【共通一次 平1】,古代ギリシア【共通一次 平1】などのキリスト教以前の文化の流入を12世紀ルネサンスといいます。
ヨーロッパに羅針盤【セH4】【セH27中国で生まれたことを問う】【セA H30発祥はポルトガルではなく中国】・火器【セH2「火薬」が中国で発明されたか問う】・活版印刷術が伝わり,改良,発達されていくのもこの時期です。羅針盤は大航海時代を刺激【セH4】,火器は騎士の没落を促進,活版印刷術は情報伝達により宗教改革などの新しい思想の伝達に威力を発揮しました。製紙法の伝播【セH27モンゴル人による伝播ではない】もこの頃でした。
また,1494年にイタリアの商人・数学者〈ルカ=パチョーリ〉(1445?~1517)が,複式簿記に関する解説を著作『スムマ』の中でしており,これが複式簿記についての現存する最古の記録となっています(複式簿記自体は12世紀頃から使用されていました)。
○1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ 現①イタリア
◆イタリアで,古代ギリシア文化やローマ文化を再評価する人文主義の運動(ルネサンス)が活発化した
ヨーロッパ文化にギリシア・ローマ文化が接続される
こうした革新的な情報の交流を背景に,「人間らしさ(人間性)」を我慢せずに自由に表現しようとする運動が,14世紀から16世紀にかけてヨーロッパで起きます。これがいわゆる“ルネサンス”です。
その大きな特色は,ギリシア文化・ローマ文化【セH26ゲルマン文化】のように人間に中心を置く考え方である人文主義(ヒューマニズム) 【セH17スコラ学とのひっかけ】です。この考え方をとった知識人をヒューマニストと呼びます。
中世ヨーロッパはキリスト教のカトリック教会の権威が絶対で,それに歯向かうことが許されていませんでした。しかし,いざ国家が宗教の束縛から自由になると,「自分の国のことだけ」を考えて,国家どうしが血も涙もない戦争に明け暮れる時代に突入したのです。これからの時代の君主たるもの,権謀術数(相手をだましたりはめたりしようと策をめぐらすこと)が必要だと解き,キリスト教に代わる新たな「正義」について考えたのが,フィレンツェの〈マキャヴェッリ〉【東京H22[3]】【セH7史料が引用。モンテーニュ,エラスムス,トマス=モアではない】【セH14ホッブズではない】です。「キツネのずる賢さと,ライオンのどうもうさ」というフレーズで有名な『君主論』【東京H22[3]】【セH14『リヴァイアサン』とのひっかけ】は,「権謀術数」のほうが強調されて広まりましたが,時代の変化に対応した国家運営について,この時期にもっとも深く考えていた人です。
〈ダンテ〉(1265~1321) 【セH4時期(15~16世紀ではない)】 【セH15・H17】【追H30】はフィレンツェで『神曲』【セH15・H17】【セH8時期(14~15世紀)】【追H30】を口語で書き,カトリック教会を物語の中で批判しています。物語の中には,古代ローマの詩人〈ウェルギリウス〉(英語名はヴァージル,前70~前19) 【追H30】が登場し,〈ダンテ〉本人とともに地獄・煉獄・天国をめぐるという内容です。中世のキリスト教の世界で使われていたラテン語はヨーロッパ文化圏の共通言語でしたが,教育を受けていない一般の民衆は読むことができませんでした【セH12「(12~13世紀の西ヨーロッパの)大半の人々は,ラテン語で書かれた聖書が読めなかった」か問う】。親しみのある口語(フィレンツェ地方のトスカナ語【セH15】)で記されたところが,今までになかった革新的な特徴です。
〈ダンテ〉の影響を受けた〈ボッカチオ〉(1313~75) 【共通一次 平1〈ラブレー〉ではない】【セH8時期(14~15世紀)】【セH15画家ではない】は『デカメロン』【共通一次 平1】を書いています。またボローニャ大学で法律を学んだ〈ペトラルカ〉(1304~74)【セH24時期】は,古典の研究をしながら,人間の内面を深くとらえた多くの恋愛抒情詩【セH24】を残し,“最初の近代人”ともいわれます。
彼らの影響はヨーロッパの他の地域にも広がり,イングランドでは〈チョーサー〉(1340?~1400) 【共通一次 平1】が『カンタベリ物語』【共通一次 平1『ユートピア』ではない】【セH8時期(14~15世紀),セH12騎士道物語ではない】をロンドンの俗語【共通一次 平1:英語か問う】で書き“イギリス文学の父”と称されました。ネーデルラントでは〈エラスムス〉(1469~1536) 【セH4時期(15~16世紀か)】【セH24時期・H28】【追H20スコラ学(スコラ哲学)とは関係ない】が『愚神礼賛』【セH24,H28】を書き,社会を風刺しています。イングランドでは16世紀末~17世紀初に〈シェイクスピア〉(1564~1616)が戯曲を発表しています。
絵画では,15世紀前半に遠近法が確立され,「より本物らしく描く」ことが重要視されるようになります。古代ローマの建築が導入されて,大きなドームが印象的なルネサンス様式【セH10ロマネスク様式とのひっかけ】【追H20ロマネスク様式ではない】がつくられます。
16世紀には,「ダヴィデ像」の作者の〈ミケランジェロ〉(1475~1564)らにより,ローマでサン=ピエトロ大聖堂【セH10サン=ヴィターレ聖堂とのひっかけ】【追H20ロマネスク様式ではない】が新築されました(◆世界文化遺産「ヴァチカン市国」、1984)。
「最後の晩餐(ばんさん)」「モナ=リザ」を描いた「万能の天才」〈レオナルド=ダ=ヴィンチ〉【セH4時期(15~16世紀か問う)】【追H9 ガリレオ=ガリレイとのひっかけ,追H20】もこのときの人で(注),聖母子像を描いた〈ラファエロ〉【セH14イエズス会の宣教師ではない(カスティリオーネとのひっかけ)】【大阪H30図版「アテネの学堂」】とともに,ルネサンスの三大巨匠といわれます。
なお,美術の影響は他の地域にも広まります。
ネーデルラントでは,〈ファン=アイク兄弟〉(兄1370?~1426,弟1380?~1441)が油絵技法を改良しフランドル派の祖となりました。ただし,兄の実在には疑問もあります(兄は「ヘント祭壇画」,弟「アルノルフィニ夫妻の肖像」が代表作)。「四使徒」(四人の使徒)【追H20図版(解答には不要)】【慶文H29問題文】で有名なドイツの〈デューラー〉(1471~1528) 【追H20リード文】【慶文H29】は版画を制作し,ルターの考えに共感して〈ルター〉の訳した新約聖書からドイツ語の聖句が抜き出され「四使徒」の絵の下部に刻まれています【追H20リード文】。ザクセン選帝侯の宮廷画家〈クラナッハ〉(1472~1553)も,宗教改革を支持し「磔刑図」(たっけいず)や〈ルター〉の肖像画を残しています。
(注)「最後の晩餐」はミラノのサンタ=マリア=デッレ=グラーツィエ修道院に収められ、壁画自体も世界文化遺産に登録されています(◆世界文化遺産「同修道院とレオナルド=ダ=ヴィンチの『最後の晩餐』、1980」)。
・1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ 現⑧アイルランド、⑨イギリス
北部のスコットランド王国ではイングランドの支配が強まり、1296年にはイングランド国王〈エドワード1世〉によって、スコットランド王家の象徴である「スクーンの石」(運命の石)が戦利品として略奪されます。
その後、13~14世紀にかけてイングランドからの独立戦争が起きます。抵抗運動に立ち上がった英雄として〈ウィリアム=ウォレス〉(1270?~1305)が有名です。1306年に戴冠した〈ロバート1世〉(ロバート=ドゥ=ブルース。1306~1329)の下で勝利しています。
(注)運命の石はウェストミンスター寺院のイスに埋め込まれました。1950年にはスコットランド民族主義者により盗難に遭い破損。1995年に正式に返還されました。リチャード・キレーン、岩井淳他訳『図説
スコットランドの歴史』彩流社、2002、xxxii~xxxiii。〈ロバート=ブルース〉は1314年のバノックバーンの戦いでイングランド軍に決定的勝利をおさめます(同、p.73)。
・1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ 現⑦フランス
◆フランス王国は,南フランスへの拡大に成功し,北アフリカへの進出に失敗する
フランス王国は王権を強め,地中海岸に拡大する
カペー朝フランス王国の9代目〈ルイ9世〉(位1214~1270年)は,ローマ教皇のお墨付きを得て,南フランスへの進出を強めます。12世紀半ばからフランス南部のトゥールーズやカルカッソンヌなどのラングドック地方で一大勢力を築いていたアルビジョワ派(カタリ派【セH16オランダではない,セH29】)退治が名目です(アルビジョワ十字軍【セH29】)。カタリ派の教義は不明な点も多いですが,現世=汚い=悪,来世=汚れがない=善という善悪二元論に基づき,ブルガリアで始まったボゴミル派(10世紀中頃)との関連があるようです。結婚(生殖=汚い)をしないことや厳しい菜食主義(肉=汚い)が理想とされ,腐敗していたローマ=カトリックと比べ魅力的と写ったようです。
この十字軍はヨーロッパ国内の異端勢力を攻撃する者に,教皇が「イェルサレムの十字軍と同じくらいの功徳(くどく)がある」と認めて始まったもので,“ヨーロッパの内部における十字軍”でした。〈ルイ9世〉は1229年に,多大な犠牲を払って西南フランスのラングドック地方を制圧しています。
〈ルイ9世〉の時代はフランスが平和を迎えた時代でした。パリを流れるセーヌ川のシテ島にあるサント=シャペル(1248完成)も、彼の命令で完成したステンドグラスをもつゴシック様式の教会です(◆世界文化遺産「パリのセーヌ河岸」、1991の一つ)。
余裕ができた〈ルイ9世〉は,第七回十字軍を決行し,「聖王」(英語ではセントルイス)と呼ばれて権威を高めました。1248年に出発した〈ルイ9世〉はアイユーブ朝のエジプトを攻撃しましたが,マムルークである〈バイバルス〉に敗れて人質となり,莫大な身代金を支払って解放されました。
なお,アイユーブ朝でもクーデタが起こり,マムルーク朝が誕生しています。このマムルーク朝の〈バイバルス〉は,1258年にバグダードを占領したモンゴル人の〈フラグ〉と対決し,勝利しています。
前後しますが,〈ルイ9世〉は,イスラーム教勢力を挟み撃ちにできる相手を探すために,1253年にローマ=カトリック内部にあるフランシスコ会の修道士〈ルブルック〉【京都H20[2]】をモンゴル帝国へ派遣しています。さらに行政官や裁判官を整備して,国内の統治も強化していきました。
一方,フランス南部の異端に対するアルビジョワ十字軍は,第11代の〈フィリップ4世〉(位1268~1314年)のときに終わります。南部には独自のオック語文化が発展していて,フランス系の吟遊詩人(トゥルバドゥール。人名ではなく職業。宮廷で騎士の恋愛を抒情詩(気持ちをのせた歌)でうたった)は南部の出身者です。「愛する女性を見た瞬間 突然おじけづく 眼はかすみ,顔は青ざめ 風にさわぐ木の葉のように震える私」…〈ベルナール=ド=ヴァンタドゥール〉の傑作より。こうやって,貴婦人に対する恋愛をこのように歌に乗せて読んだわけです(注)。
(注)詩は筆者が一部改編。木村尚三郎編『世界史資料・上』東京法令出版,1977,p.421
◆フランス王〈フィリップ4世〉は身分制議会をひらき,財政基盤を確立しようとした
フランス王国の拡大を進めたカペー朝フランスの王には,増加していた宮廷費や軍事費を確保するために,国内の諸身分の合意を得ようとしました。商業の発達にともない生まれていた新興勢力の都市住民の代表を1つのグループ(第三身分)として,今までの貴族(第二身分)や聖職者(第一身分)とともに,フランス王国を構成する重要な身分の1つに位置づけ,この三身分のバランスを考えてコントロールしようとするようになります。
その例が〈フィリップ4世〉【東京H8[3]】【共通一次 平1】【セH18・H23・H26】【追H30三部会を招集したか問う】です。彼は,ノートルダム大聖堂の3つの身分を集めて,「これからローマ教皇〈ボニファティウス8世【共通一次 平1:グレゴリウス7世ではない】【セH25レオ3世ではない】【立教文H28記】と争うことになるけれどもいいか」と意見を聞いたんですね。ばらばらに一人ひとりの意見を聞いて回っていては収拾がつきませんから,これは効率のよい方法です。フランスの身分制議会を,三部会【共通一次 平1:フロンドの乱の拠点となった高等法院とのひっかけ】【セH12】【セH16,H23】【追H30】といい,初の招集は1302年です。三部会の支持をとりつけた後で,〈フィリップ4世〉は教皇〈ボニファティウス8世〉をアナーニで捕らえようとして失敗(アナーニ事件),〈ボニファティウス8世〉はショックのあまり3週間後に亡くなっています(しばしば「憤死」と表現します)。のちに新たに就任したフランス人の教皇(クレメンス5世)は,ローマの都市貴族同士の派閥抗争から逃れるためフランス南部のアヴィニョン【共通一次 平1 グレゴリウス7世をアヴィニョンに幽閉したわけではない】【セH17 12世紀ではない,セH22 15世紀ではない】に教皇庁を移動させました。〈ダンテ〉(1265~1321)などのイタリアの詩人らは,これを『旧約聖書』の事件になぞらえ「教皇のバビロン捕囚」(1309~77)と呼びましたが,教皇をフランス人に移動させられた”被害者”とみるのは後のローマ教皇庁の見解に過ぎません。〈クレメンス5世〉はむしろ積極的に教皇庁に高度な官僚組織を組み上げ,大司教や司教の選出にも介入し,彼らから手数料を徴収するようにもなりました(注)。事務処理の増加にともない,アヴィニョン教皇庁には法学をおさめた聖職者が実務をこなしていました。
このアヴィニョンの教皇が異端宣告をしたのが,イングランドの〈フランチェスコ〉修道会の〈ウィリアム=オッカム〉(1280?~1349?)です。信仰と理性は矛盾しないと訴え,教皇の権威よりも世俗の権力のほうが強いと主張したためです。
(注)聖職叙任権は理念としては教皇が持っていましたが,大司教や司教を選出する実権は聖堂参事会にありました。樺山紘一『パリとアヴィニョン―西洋中世の知と政治』人文書院,1990。
〈フィリップ4世〉はさらに十字軍のときに結成されたテンプル騎士団を1314年に解散します。テンプル騎士団はイェルサレムに本部を置き,現金を持たずに巡礼者が安全に旅行できるような送金システムを整えたり,各地の信者からの多額の寄付を集めたりしたことで,多額の資産を管理する団体になっていました。フランスは,イングランドと戦争をするときに,よくテンプル騎士団から資金を借りていましたが,〈フィリップ4世〉はこれを踏み倒そうとしたのではないかと考えられます。テンプル騎士団といえば,映画化された小説『ダ・ヴィンチ・コード』のなかで,“キリスト教の秘密を握る謎の組織”として扱われていたように,イエスの十字架や聖杯(最後の晩餐のときに使われたとされるうつわ)を持っているのではないかとか,さまざまな「都市伝説」をもっている組織でもあります。
◆イングランドとフランスは,工業地域のフランドル地方をめぐり百年戦争をたたかった
このように〈フィリップ4世〉のもとで一気に強大化したカペー朝ですが,1328年に跡継ぎがなくなり断絶。当時はフランスとイングランドの国としての違いは明確ではなく,支配者は血筋によってヨコにつながっていましたので,フランスの国王が亡くなったら,次は自分に王を継ぐ権利があると,イングランド王〈エドワード3世〉【セH4王権神授説を唱えていない】【セH27ハプスブルク家ではない,セH29試行「母方の血筋を理由として」継承を主張したかを問う】が主張したのです。彼は,〈フィリップ4世〉の娘と,〈エドワード2世〉の間に生まれた息子です。
フランスではカペー家の傍系(遠い親戚)にあたるヴァロワ家から〈フィリップ6世〉が即位しており,ヴァロワ朝【セH2プランタジネット朝とのひっかけ】が成立。しかもフランスでは伝統的に女系の王は認められていませんでした(フランク王国のサリカ法典(6世紀頃)が起源)。
フランスとイングランド【セH13神聖ローマ帝国ではない】は工業地域のフランドル地方【セH2】をめぐっても対立し,百年戦争【セH5時期を問う】が始まりました。〈エドワード3世〉が挑戦状をおくったのが1337年,実際に戦闘がはじまったのは1339年のことです。
百年戦争中にはペスト(黒死病)が大流行し,多くの犠牲者が出ました。労働力不足から農民の待遇が改善され,解放される農奴も現れました【セH5 14~15世紀に領主直営地において賦役が廃止されたことを問う】。しかし,黒死病もおさまったころ,手のひらを返したように農民に対する待遇をまた厳しくする領主が現れます(封建反動)。百年戦争の被害もあり,厳しい負担をかけられていたフランス北東部の農民が1358年にジャックリーの乱【セH2時期(百年戦争中か),セH5「農民に対する収奪の再強化に反抗」したものか問う,セH8ジェントリのひっかけ,セH10デカブリストではない】【セH17時期・地域・ジョン=ボールが引き起こしたわけではない,セH19時期,セH22・H30ともにイギリスではない】【慶文H29】を起こすなど混乱は続きます。
百年戦争は,序盤では,長弓兵【セH17】を武器にしたイングランド軍が,フランスの弩(石弓,いしゆみ)兵に対して優勢を誇り,〈エドワード黒太子〉(1330~76) 【セH17時期】はフランス南西部の大陸領をクレシーの戦い【セH27】とポワティエの戦いに勝利して,守り抜きました。
フランスでは黒死病がはやったり,戦争と重税に耐えかねた農民一揆のジャックリーの乱(1358)が起こったりと,内政も危機にありました。
1415年にはランカスター朝イングランドの〈ヘンリー5世〉(位1413~22)がアザンクールの戦いで,フランス軍に勝利。1420年にフランス王〈シャルル6世〉の娘キャサリンと結婚しトロワ条約によってフランス王位継承権を認めさせると,フランスは絶体絶命のピンチに追い込まれます。1422年にイングランド王〈ヘンリー5世〉もフランス王〈シャルル6世〉も亡くなると,〈ヘンリー5世〉の息子がイングランドとフランスの王〈ヘンリー6世〉(仏王位1422~53,英王位1422~1461)として即位。フランス側の〈シャルル王太子〉(1403~61)はフランス王位を継承できず,最後の重要拠点である都市オルレアンがイングランド軍に包囲されるのを黙ってみているほかありませんでした。
そんな中,ドン=レミ村の農民出身の〈ジャンヌ=ダルク〉(出現当時16歳,1412~31) 【セH2時期(百年戦争末期か)】【セH15・H17】が現れて,イングランド軍に包囲されていたオルレアンを包囲から解放し【セH15・H17ともにバラ戦争ではない,セH29試行 図版(クローヴィスの洗礼とのひっかけ)】,戦局を逆転させたといい,結果的に〈シャルル7世〉(位1422~61)がランス大聖堂で戴冠することができました。
しかし〈ジャンヌ〉には幻視(げんし)・幻聴(げんちょう)の兆候があったようで,パリ攻略に失敗し,当時イングランド側についていたフランス諸侯のブルゴーニュ公国に捕らえられると,「神の声を聞いた」ということを根拠に “異端”として裁判にかけられ,ルーアンで火刑に処されてしまいます。聖人に列せられ名誉回復するのは1920年のことでした(#寄り道「ジャンヌ=ダルク」(1999仏米)!刺激の強いシーンあり)。
〈ジャンヌ〉の活躍もあり,フランスは1453年に百年戦争に勝利しました。イングランドは,フランス北部沿岸のカレーを除きユーラシア大陸から撤退しました。しかしフランスは,長年の戦争で諸侯や騎士が没落し,国王〈シャルル7世〉は大商人〈ジャック=クール〉(1395~1456)の力を借りて財政を強化しました。
また〈ルイ11世〉(位1461~83)は,三部会によって国内の三身分の利害を調整しつつ,ブルゴーニュ公領を獲得するなど領土を拡大させ,常備軍(西ヨーロッパ初)も整備しました(ブルゴーニュ公国がスイスとの戦争に敗れたタイミングを狙いました)。
また,1438年にはフランスのローマ=カトリックの教会収入と司教の叙任権をコントロールする権利を獲得し,フランス国内の教会に対する支配を強めるきっかけをつくりました。この政策をガリカニスムといいます。
・1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ ⑧アイルランド,⑨イギリス
この時期は小氷期(リトル=アイス=エイジ)と呼ばれる寒冷な時期にあたり,森林が暖炉の薪(たきぎ)や製鉄の原料として伐採されていったことで,森林資源が枯渇に向かいました。草原の丘がゆるやかにひろがる,イギリスの田園風景は,実は森林破壊の跡なのです。そこで代わりの燃料や,製鉄の原料として石炭が使われるようになっていきます。1273年には石炭を燃やすことにより大気汚染が起きるのを防止する煤煙(ばいえん)規制法が制定されています。石炭は,のちに1760年以降に蒸気機関の燃料として脚光を浴びることとなります。
政治的には,1066年以来続いていたノルマン朝イングランド王国の支配が1154年に終わりを迎えます。最後の王〈ヘンリ1世〉が跡継ぎを残さぬまま亡くなってしまったのです(長男はいたが,船が沈没した亡くなりました(ホワイトシップの遭難))。
◆ノルマン朝の跡継ぎ争いが起き,フランス貴族がプランタジネット朝をひらいた
フランスのアンジュー伯が,大帝国を実現する
そこで,事故で亡くなった長男の姉〈マティルダ〉が後継者候補となります。彼女はザーリアー朝神聖ローマ皇帝〈ハインリヒ5世〉(ヴォルムス協約を結んだ人物)と結婚していましたが,彼が亡くなると,今度はアンジュー伯に嫁いでいました。
しかし,女性を王にすることに反対する意見も多く,〈ヘンリ1世〉の妹の息子〈スティーヴン〉を王にしようとする勢力との間で内乱が勃発。
ところが,最終的に〈マティルダ〉は,アンジュー伯との間に生まれた息子〈アンリ〉にイングランドの王位が回すことで妥協します。
「フランス【追H9〈アンリ〉の出身地を問う。スペイン,イタリア,ドイツではない】の貴族なのになぜイングランドの王になれるのか?」と思うかもしれませんが,彼らには現在のような国民意識はありません。それでもフランスとイングランドで言語には当時から違いがありましたから,フランスの貴族〈アンリ〉は,〈スティーヴン〉の死後,イングランドで〈ヘンリ2世〉(位1154~89) 【セH18ジョンとのひっかけ,セH27・H30】という名前で即位します。これが,プランタジネット朝【セH2ヴァロワ・カペー・テューダー・ランカスター朝ではない】【セH17時期,セH27・H30】のイングランド王国です(1154~1328)。ちなみに当初から「プランタジネット朝」と名乗っていたわけではありません(〈アンリ〉の父のアンジュー伯が帽子にエニシダをつけていたからだとか)。
即位直後に裁判制度を整備し,各地を定期的に巡回にする国王裁判官によって,民事(お金や家族などに関する揉め事)と刑事(殺人,傷害など)の裁判が実施されました。国王裁判に対しては,イングランドのローマ教会が反発し,〈トマス=ベケット〉大司教(1118頃~70)が〈ヘンリー2世〉の部下により暗殺されるなどの混乱も招いています。このときに積み上げられた判例(どういう場合に,どういう刑を課したかというデータ)が,コモン=ローという法体系にまとまっていきました。
イングランド王〈ヘンリー2世〉は,本拠地のフランス北西部アンジューにおいては,フランスの一諸侯に過ぎません。しかし,その領域は,イングランド+フランスの西半分です。アンジュー伯〈アンリ〉は,広大な領域を誇るアキテーヌ公国の公女〈アリエノール〉と結婚していたからです(#映画「冬のライオン」1968イギリス)。
こうしてプランタジネット朝は,フランス国王よりもはるかに広い領土を,ドーバー海峡を挟んだイングランドに拠点を構えながら支配するということになったわけです。
彼はウェールズ(イギリスに併合されるのは1536年)やアイルランド(イギリスに併合されるのは1801年)にも勢力を拡大し,その広大な領土からアンジュー帝国ともいわれました。
2代目の〈リチャード1世〉(位1189~99)は獅子心王(リチャード=ザ=ライオンハート)と呼ばれ,第三回十字軍に参加しましたが,捕虜になってしまい,身代金を用意して釈放されました。イェルサレムも。最期はカペー朝フランス王〈フィリップ2世〉(尊厳王(オーギュスト,ローマ皇帝アウグストゥスに由来),位1180~1223)と戦って,命を落とします。
3代目の〈ジョン〉【セH3】【セH18ヘンリ2世とのひっかけ】は,即位時のゴタゴタによって,カペー朝フランス王〈フィリップ2世〉【セH3】と戦争となり,1214年のブーヴィーヌの戦いで敗れた【セH3勝っていない】ためにノルマンディとアンジューを失ってしまいます【セH3フランス内のイギリス領を拡大していない】。アンジューは,初代アンジューの領地だったところですよね。そんなに大事なところを失った挙句の果てに,貴族や聖職者らの諸侯・都市から税をとろうとしたため,彼らは猛反発。「王は承認なしに課税してはならない!」とうたったマグナ=カルタ(大憲章) 【共通一次平1:イギリス最初の議会ではない】【セH14,セH18ヘンリ2世ではない,H25・H30】を〈ジョン〉王【セH14エドワード3世ではない,セH25】【慶文H30記】【慶文H30記】に突き付け,1215年【慶文H30記述】に守らせることに成功しました。王の権力を抑えるための法をつくったということで,マグナ=カルタはイングランド初の憲法(支配者をしばるための法)とされています。
しかし,4代目の〈ヘンリ3世〉(位1216~72) 【セH14星室庁を利用していない】がマグナ=カルタを無視して政治をおこなったため,1265年フランス貴族のシモン=ド=モンフォールの乱【共通一次平1:イギリス最初の議会ではない】【セH22デンマークではない,セH30】がおきました。彼の招集した身分別の議会が,イングランドの議会の起源とされ,5代目の〈エドワード1世〉(位1272~1307)による聖職者・貴族・都市の代表による身分制議会(1295年。模範議会といわれる【共通一次平1:イギリス最初の議会ではない】【セH4「王権に忠実」ではない】【セH29フランスではない】)に発展しました。
7代目の〈エドワード3世〉(位1327~1377)のときに,二院制議会(上院と下院) 【共通一次 平1:最初から二院制だったわけではない】のしくみが整いました。ただ,選挙権は現在のように広く国民にひらかれていたわけではありません【共通一次 平1:中世末期には国民代表的正確を強めていたわけではない。それは19世紀以降】。
この〈エドワード3世〉の母が,フランスの王〈フィリップ4世〉の娘だったため,当時断絶していたカペー朝の王位を主張して始まったのが,百年戦争ということになります。しかし戦争の最中にペスト(黒死病)が流行し,労働力が不足(人口の約3分の1が死亡するという未曾有の事態!)。農村では,人手を必要とする従来の穀物生産から,ヒツジの放牧へと土地利用が転換されていきました。
従来からイギリスの農奴解放はかなり進んでいて,自分の土地を保有した農民はヨーマン(独立自営農民) 【セH19ジェントリではない】【セH8ジェントリのひっかけ】と呼ばれるようになっていました。しかし,黒死病の流行で労働力が不足すると,領主もさらに農奴を解放して待遇を良くせざるを得なくなりました。
しかし,この傾向が進むと,領主の暮らしが悪化。黒死病もおさまったころ,手のひらを返したように農民に対する待遇をまた厳しくする領主が現れます(封建反動)。イギリスでは1381年にワット=タイラーの乱【セ18時期(18世紀ではない)・セH21時期】が起こり,身分制度を批判する動きが起きましたが,これらの農民一揆は鎮圧されてしまいます。〈ワット=タイラー〉の乱では,教皇権を批判し1378年(注)に聖書の英訳をはじめていた神学者〈ウィクリフ〉を支持していた聖職者〈ジョン=ボール〉(1338?~81)【セH17ジャックリーの乱は引き起こしていない,セH22イタリアではない】が『アダムが耕しイヴが紡いだとき,誰がジェントリ(貴族)【慶文H29】だったのか』と説教をして農民軍を勇気づけたとされます。
(注)1384年になくなった後,1400年頃に完了。『世界史年表・地図』吉川弘文館,2014,p.121。
このような社会の混乱期にあって,ローマ教会から贖宥状(しょくゆうじょう)を買って,生前の罪を軽くしようとする人も増えていました。贖宥状は免罪符(めんざいふ)とも訳され,買えば天国と地獄の間にある煉獄(れんごく)での滞在時間を短くできると信じられたのです。
もともとローマ=カトリックと正教会では,洗礼後に個人的な(宗教的な意味での)罪(つみ)を犯した信徒が聖職者にそれを告白し,聖職者がそれをゆるし,信徒が何かしらの行為によってそれをつぐなうことができるとされていました。これは教会に与えられた特別な儀式(サクラメント。カトリックでは秘蹟,正教会では機密という)の一つで,ローマ=カトリックでは「ゆるしの秘蹟」,正教会では「痛悔機密」と呼ばれます。免罪符を買えば,つぐないの行為が免除されるとされたわけです。
14世紀後半には,イングランドのオックスフォード大学神学部教授〈ウィクリフ〉(1320?~84)【セH2215世紀ではない】や,〈ウィクリフ〉の影響を受けたベーメン(現チェコ)のプラハ大学神学部教授〈フス〉(1370?~1415)が,「救いのへの道は,教会を通してではなく,聖書を通して得られる」と主張し,教会や教皇の批判を公然をおこなうようになります。〈ウィクリフ〉はロラード派という,聖職者の存在に反対する運動に参加していた人物です。
◆百年戦争を通して,フランスとイングランドは明確な領域に分離した
百年戦争は,序盤では,長弓兵【セH17】を武器にしたイングランド軍が,フランスの弩(石弓,いしゆみ)兵に対して優勢を誇り,〈エドワード黒太子〉(1330~76) 【セH17時期】はフランス南西部の大陸領をクレシーの戦い【セH27】とポワティエの戦いに勝利して,守り抜きました。
フランスでは黒死病がはやったり,戦争と重税に耐えかねた農民一揆のジャックリーの乱(1358) 【慶文H29】が起こったりと,政も危機にありました。
1399年には,プランタジネット朝が〈リチャード2世〉(位1377~99,エドワード黒太子の息子)の下で断絶すると,かつての王〈エドワード3世〉(位1327~77)の子どもの一人でランカスター公の〈ジョン=オヴ=ゴーント〉(~1399)の子どもが〈ヘンリー4世〉(位1399~1413)として国王に就任。
ランカスター朝【セH2プランタジネット朝とのひっかけ】を開きます。
1415年には,次の〈ヘンリー5世〉(位1413~22)がアザンクールの戦いで,フランス軍に勝利。1420年にフランス王〈シャルル6世〉の娘キャサリンと結婚しトロワ条約によってフランス王位継承権を認めさせると,フランスは絶体絶命のピンチに追い込まれます。1422年にイングランド王〈ヘンリー5世〉もフランス王〈シャルル6世〉も亡くなると,〈ヘンリー5世〉の息子がイングランドとフランスの王〈ヘンリー6世〉(仏王位1422~53,英王位1422~1461)として即位。
フランス側の〈シャルル王太子〉(1403~61)はフランス王位を継承できず,最後の重要拠点である都市オルレアンがイングランド軍に包囲されるのを黙ってみているほかありませんでした。
そんな中,ドン=レミ村の農民出身の〈ジャンヌ=ダルク〉(出現当時16歳,1412~31) 【セH15・H17】が現れて,イングランド軍に包囲されていたオルレアンを包囲から解放し【セH15・H17ともにバラ戦争ではない,セH29試行 図版(クローヴィスの洗礼とのひっかけ)】,〈シャルル7世〉(位1422~61)がランス大聖堂で戴冠するのを助けました。しかし〈ジャンヌ〉には幻視(げんし)・幻聴(げんちょう)の兆候があったようで,パリ攻略に失敗し,当時イングランド側についていたフランス諸侯のブルゴーニュ公国に捕らえられると,「神の声を聞いた」ということを根拠に “異端”として裁判にかけられ,ルーアンで火刑に処されてしまいます。聖人に列せられ名誉回復するのは1920年のことでした。
〈ジャンヌ〉の活躍もあり,フランスは1453年に百年戦争に勝利しました。イングランドは,フランス北部沿岸のカレー【セH24ボルドーではない】を除きユーラシア大陸から撤退しました。それ以降イングランドは,大陸への進出を試みることはなくなります。
戦後【セH2時期(百年戦争の末期ではない)】は,ランカスター家とヨーク家によるバラ戦争(1455~85) 【セH4有力貴族が弱体化したから絶対王政が始まったか問う】が起こります。
一方,イングランドでも〈ヘンリー6世〉(位1422~61,70~71)の王位が,かつてのプランタジネット朝〈エドワード3世〉の孫の孫〈エドワード4世〉(位1461~71,71~83)に移り,国王に就任。これが,ヨーク朝です。ランカスター家の〈ヘンリー6世〉との王位をめぐる争いは,百年戦争終結まで続き,ヨーク朝の王位は短命な〈エドワード5世〉(位1483)→〈リチャード3世〉(位1483~85)に継承されますが,風前のともし火という状態でした。
そんな中,ヨーク家の国王の娘の婿(むこ)である,テューダー家の〈ヘンリー〉がこれを収め,1485年に〈ヘンリ7世〉(位1485~1509)として即位し【セH30ジェームズ2世ではない】【追H30ルイ14世ではない】,テューダー朝【セH2プランタジネット朝ではない】を創始しました。
彼は,バラ戦争の戦後処理のために1530年代から星室庁(せいしつちょう,The Court of Star Chamber) 【セH14ヘンリ3世のときの利用ではない】【追H30】を整備して,国王大権下で司法権を掌握するなど,急速に中央集権化を進めていきました。本格的に星室庁裁判所が利用されるのは〈ヘンリ8世〉の1540年代のことになります。
・1200年~1500年のヨーロッパ 西ヨーロッパ 現⑩ベルギー,⑪オランダ,⑫ルクセンブルク
◆毛織物産業地帯フランドル地方をめぐり英仏が抗争したが,ブルゴーニュ公国の領土となった
ライン川河口周辺の低地地方では,フランドル伯領が,カロリング家やイングランド王〈アルフレッド〉大王とも婚姻関係を結び,権威を高めつつ神聖ローマ帝国とフランス王国の間でうまくバランスをとり勢力範囲を徐々に広げていました。11世紀頃からはイングランドから輸入した羊毛から毛織物【東京H17[3]】を生産し,ブルッヘやヘントといった都市を中心に先進工業地帯として栄えるようになりました。
フランドル地方の富を狙い,フランスの〈フィリップ4世〉が介入し,一時併合されたフランドル伯はイングランドの〈エドワード1世〉と手を組み,フランスを撃退しました。
一方,フランドルの諸都市にはフランドル伯からの自由を求める動きもあり,フランドルの諸都市の反乱に際して,フランスが支配者であるフランドル伯のほうを支援したことから,フランドル伯はフランスに接近。反対にフランスの介入をおそれるフランドルの諸都市は,イングランドに接近するようになります。
イングランドにとってもブリテン島の対岸の低地地方にフランスが進出することは,安全保障上の大問題だったのです。
イングランドとフランスが,王位継承問題やスコットランド問題(1200年~1500年のブリテン島・アイルランドを参照)をめぐって対立すると,イングランドの〈エドワード3世〉は大陸への羊毛輸出を禁止。これにより毛織物産業に打撃を受けたフランドルの諸都市は,1337年にフランスに接近していたフランドル伯に対し反乱を起こして追放しました。
その後1381年にフランドル伯の反撃で,フランドルの諸都市は再びフランドル伯領となりましたが,伯が亡くなるとその娘と結婚したブルゴーニュ公〈フィリップ豪胆公〉(ヴァロワ朝〈シャルル5世〉の弟,位1363~1404)が継承し,低地地方はブルゴーニュ公国の領域に編入されることになりました。
ブルゴーニュ公国では商工業が栄え,〈ファン=アイク〉(弟)(1390?~1441)により油絵(油彩)技法が確立されました。代表作は「ヘントの祭壇画」です。
ブルゴーニュ公〈シャルル突進公〉(位1467~77)はさらなる領域拡大を目指しましたが失敗し,娘〈マリー〉がオーストリア大公国のハプスブルク家〈マクシミリアン〉大公と結婚することを認めた後に,フランスとの戦いで亡くなりました。〈マリー〉はフランスの進出をおそれ,〈マクシミリアン〉大公と結婚。〈マクシミリアン〉はのちに神聖ローマ皇帝(位1508~19)に即位することになります。
こうして低地地方の諸都市は,ハプスブルク家の手にわたることになったのです。
なお,ルクセンブルクは1443年にブルゴーニュ公国の支配に入りました。
○1200年~1500年のヨーロッパ 北ヨーロッパ
北ヨーロッパ…現在の①フィンランド,②デンマーク,③アイスランド,④デンマーク領グリーンランド,フェロー諸島,⑤ノルウェー,⑥スウェーデン
この頃もサーミ人はスカンディナヴィア半島北部でトナカイの遊牧生活を送っており,周辺国から貢納を求められました。
・1200年~1500年のヨーロッパ 北ヨーロッパ ①フィンランド
フィンランドでは,13世紀にフィン人がスウェーデンの支配下に置かれるようになり,スウェーデン人の移住も行われました。現在のフィンランド南部に分布するスウェーデン系の住民には,このとき以来の子孫が含まれます。
・1200年~1500年のヨーロッパ 北ヨーロッパ ②デンマーク
北ヨーロッパのデンマークは王母〈マルグレーテ〉(1353~1412)を中心に1397年にスウェーデン,ノルウェーとともにカルマル同盟(カルマル連合)【セH17時期,セH27ポルトガルとのひっかけ】【立教文H28記】を形成し,デンマークの女王〈マルグレーテ〉を中心とする同君連合の王国が成立しました。バルト海【セH2地中海ではない】で交易活動を活発化させていたドイツ人のハンザ同盟【セH2】【セH21自由競争を保障する組織ではない】に対抗するために結成されましたが,スウェーデンやノルウェーは,デンマークによる支配に次第に反発するようになっていきました。
・1200年~1500年のヨーロッパ 北ヨーロッパ ③デンマーク
アイスランドは1262年に事実上デンマークの植民地となり,カルマル連合以降は連合の王がノルウェー王としてアイスランドを支配しました。
15世紀以降,バルト海とデンマークを結ぶエーレスンド海峡の交易が盛んとなり,バルト海沿岸から日用品や食料が大量に西ヨーロッパに帆船(はんせん)で運ばれるようになっていきます。